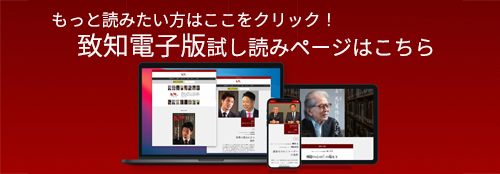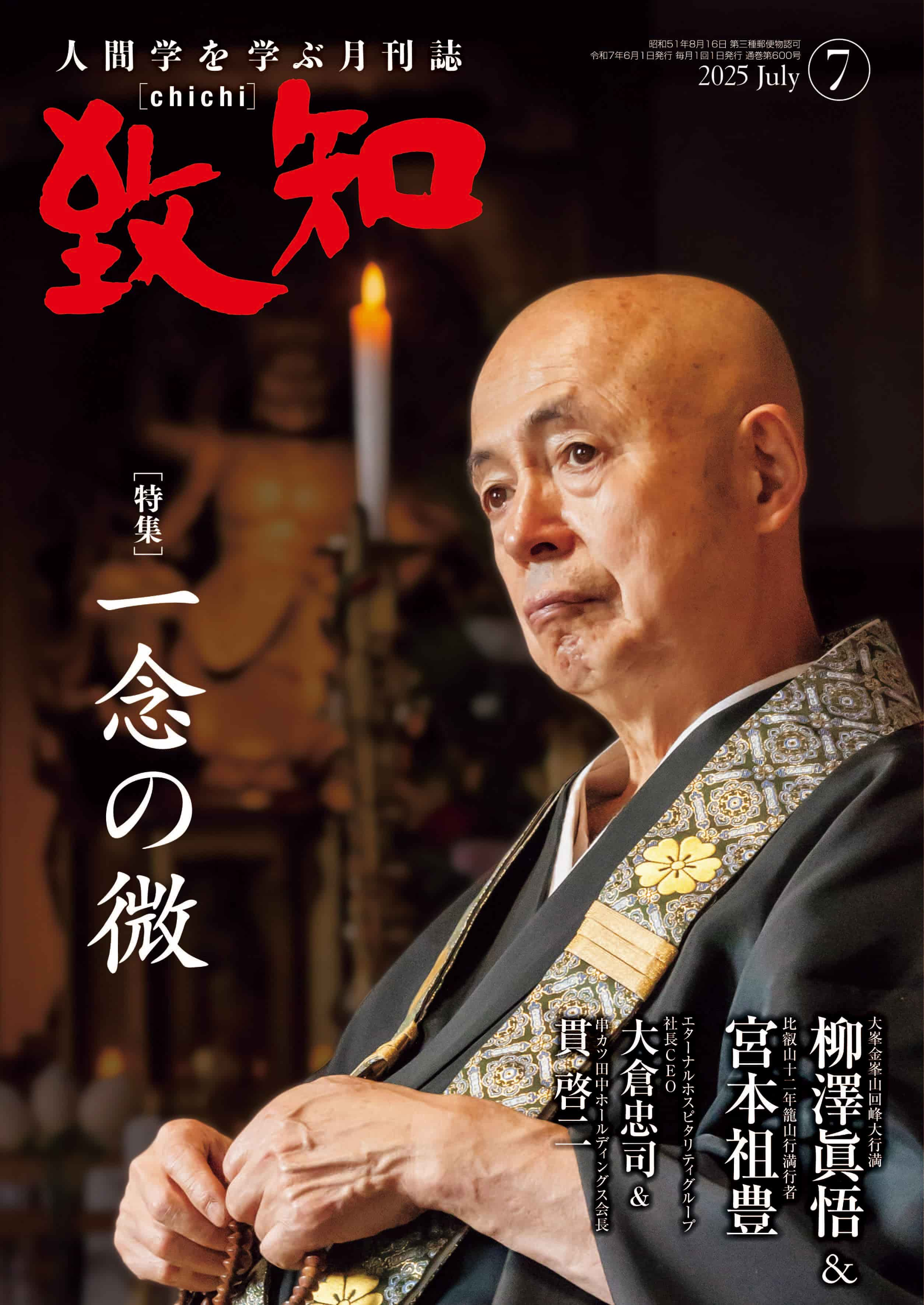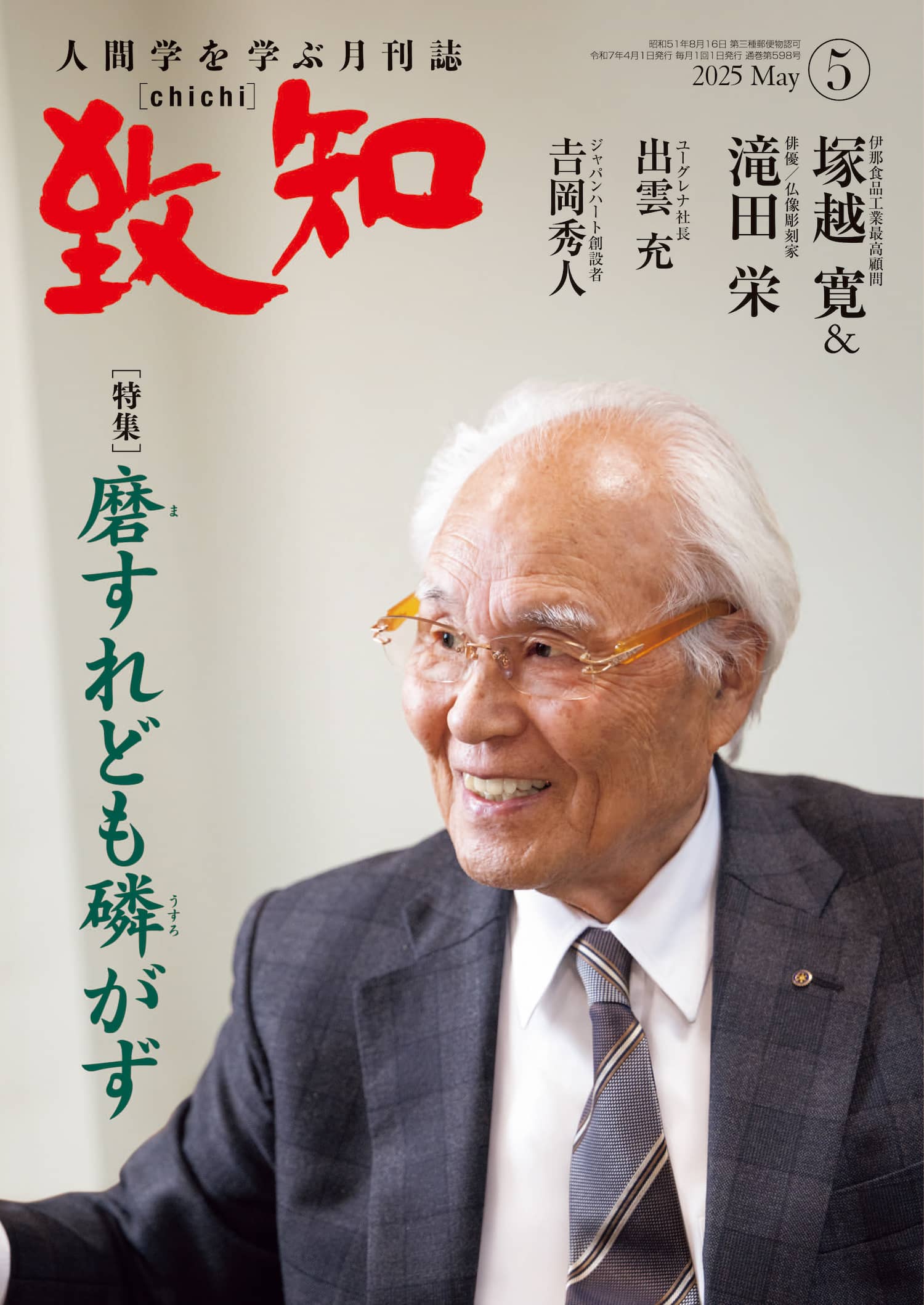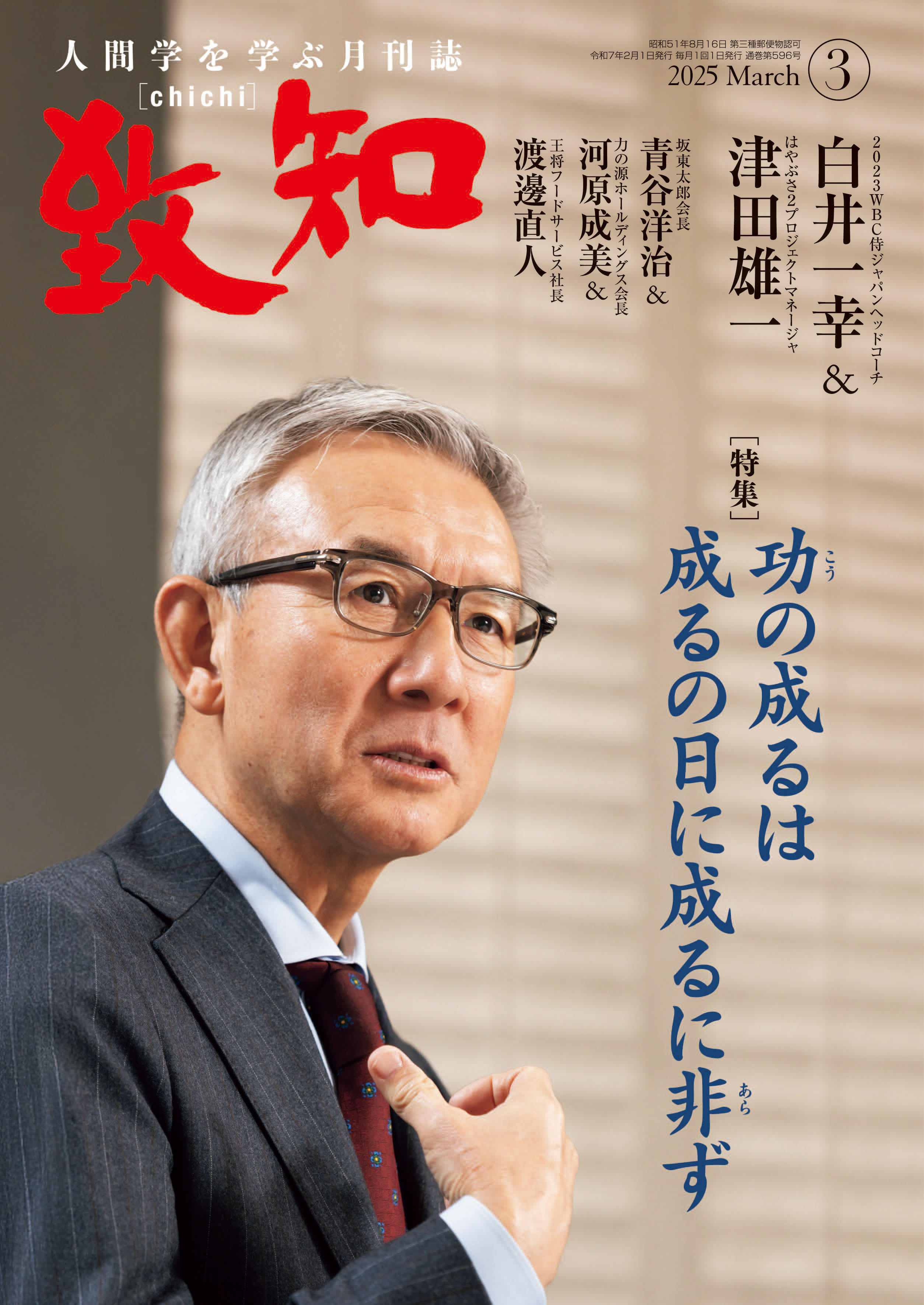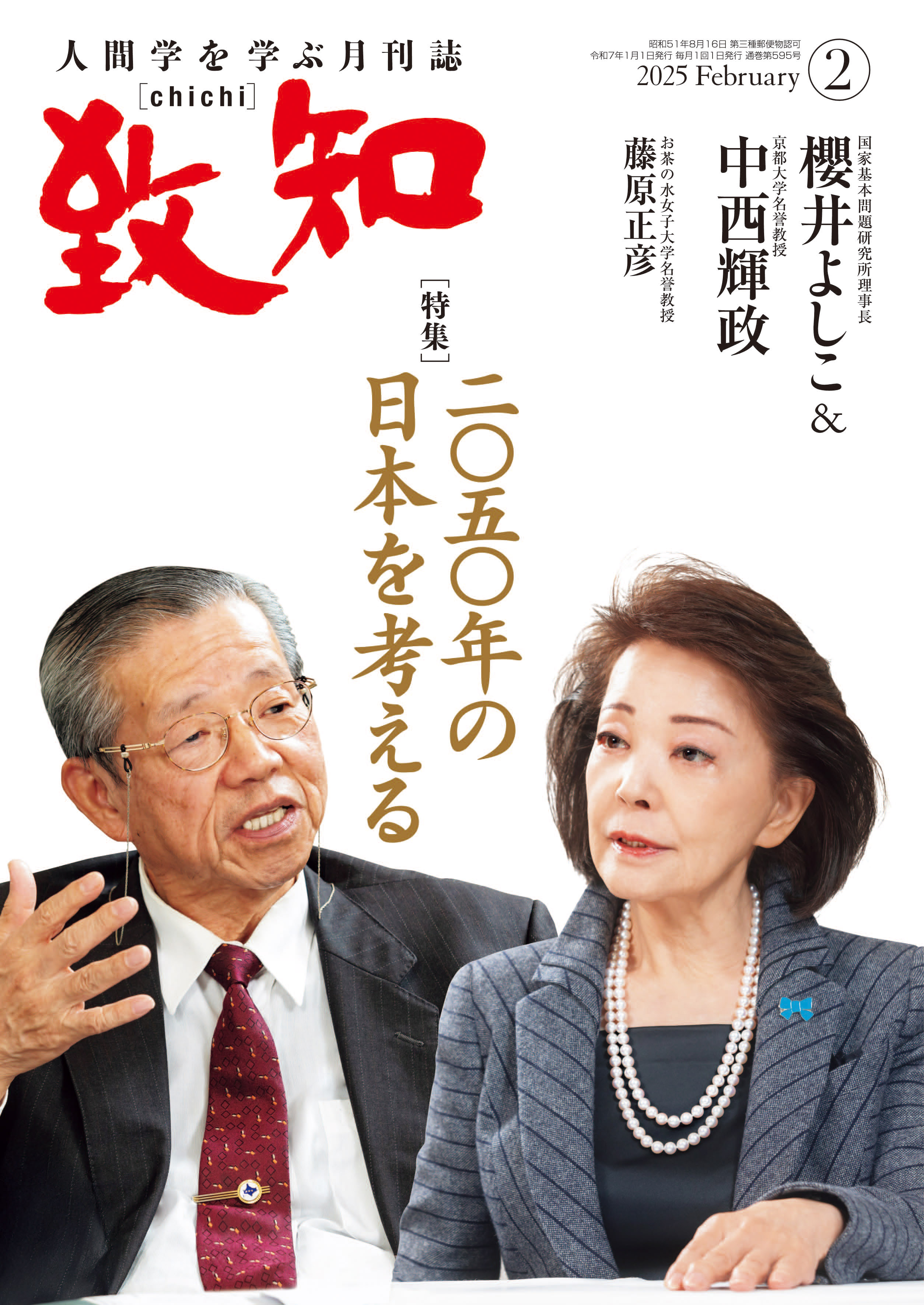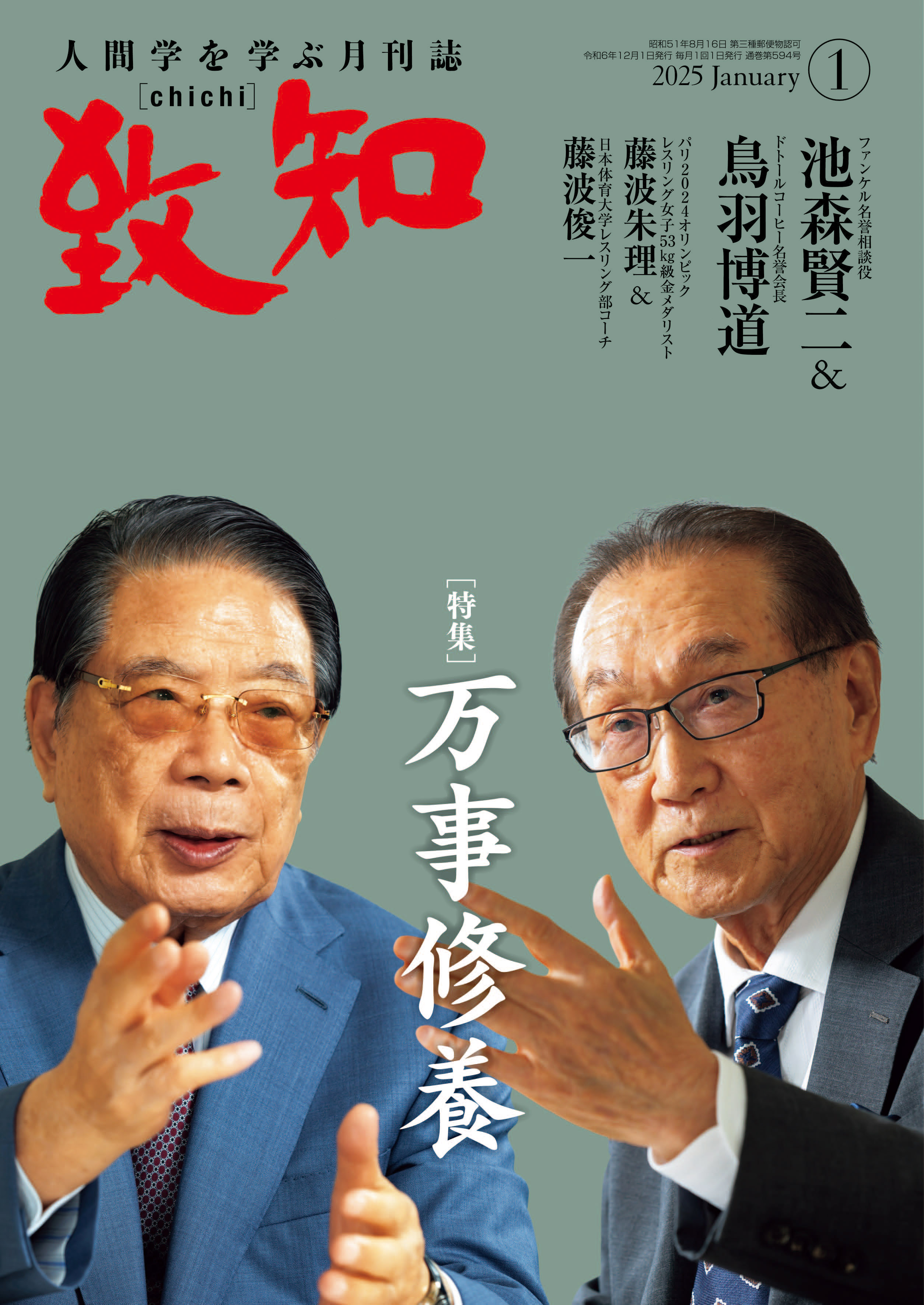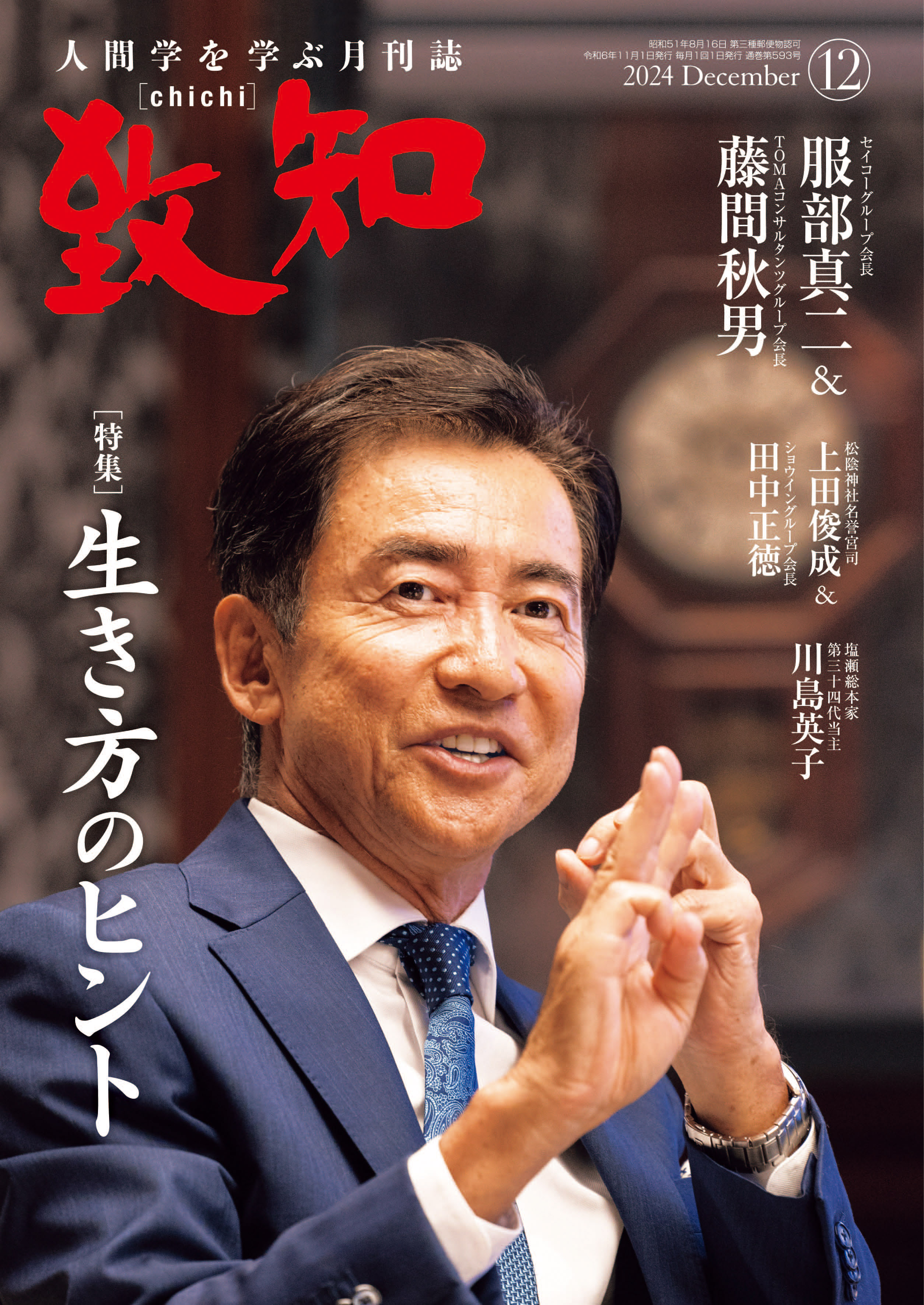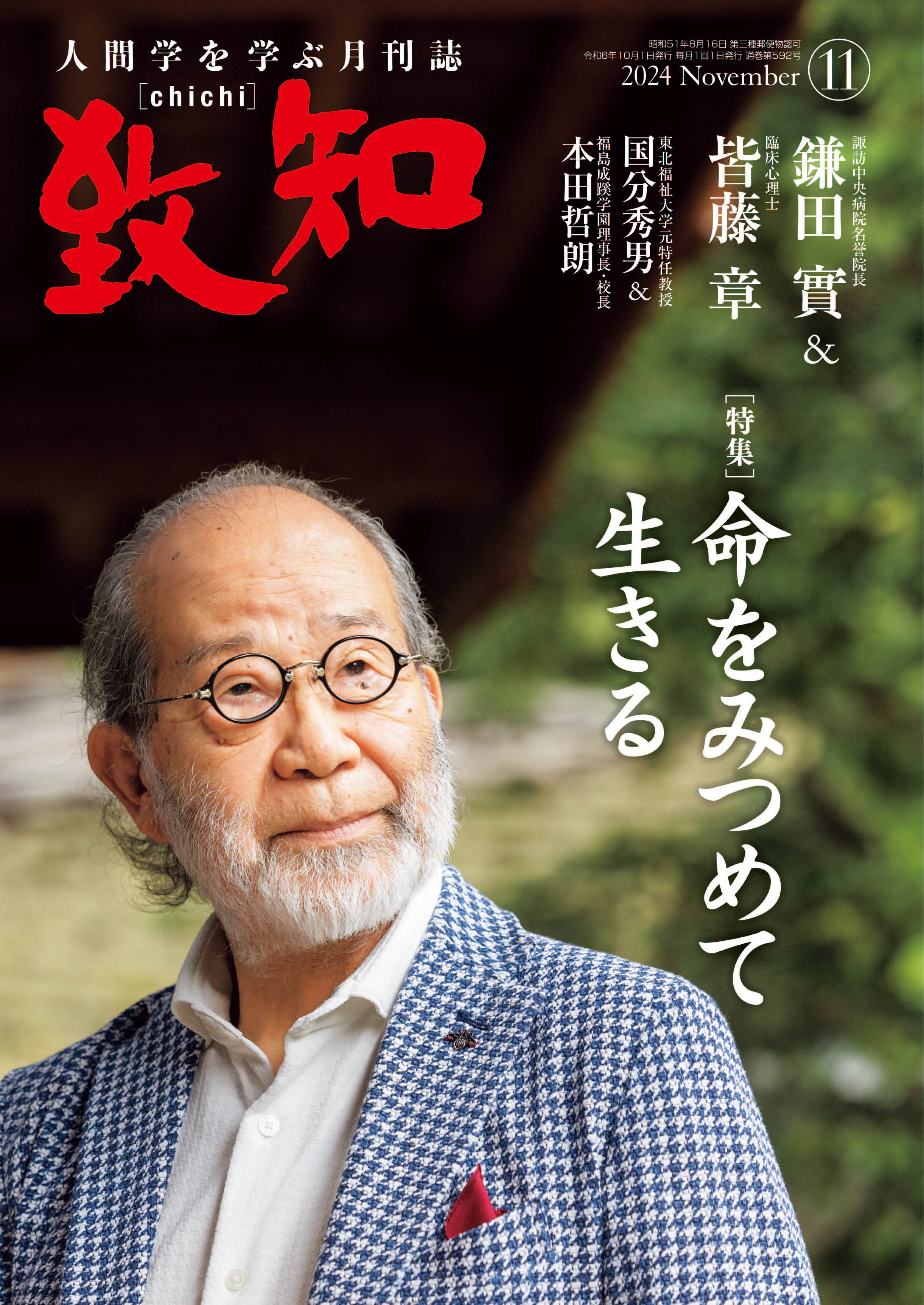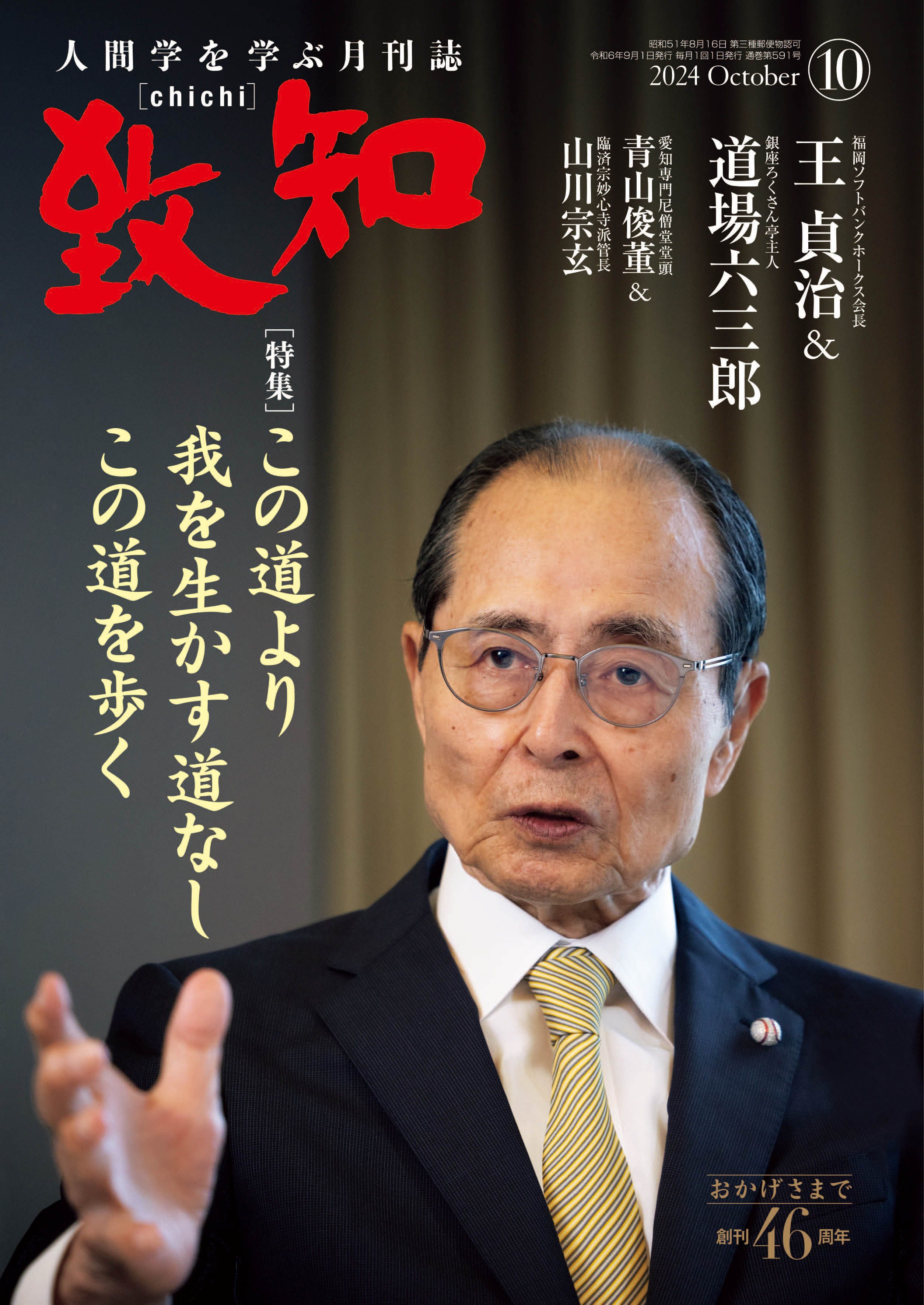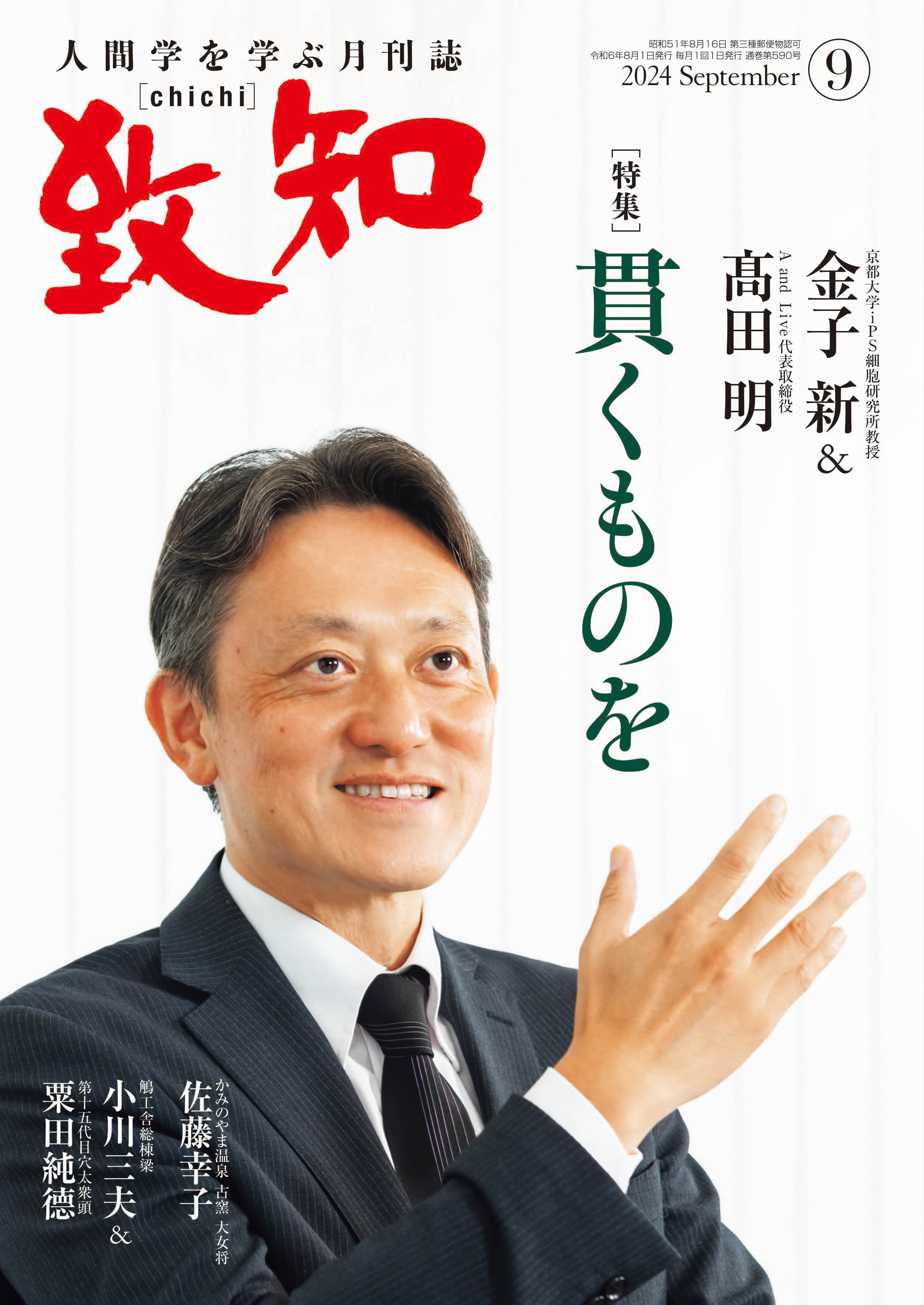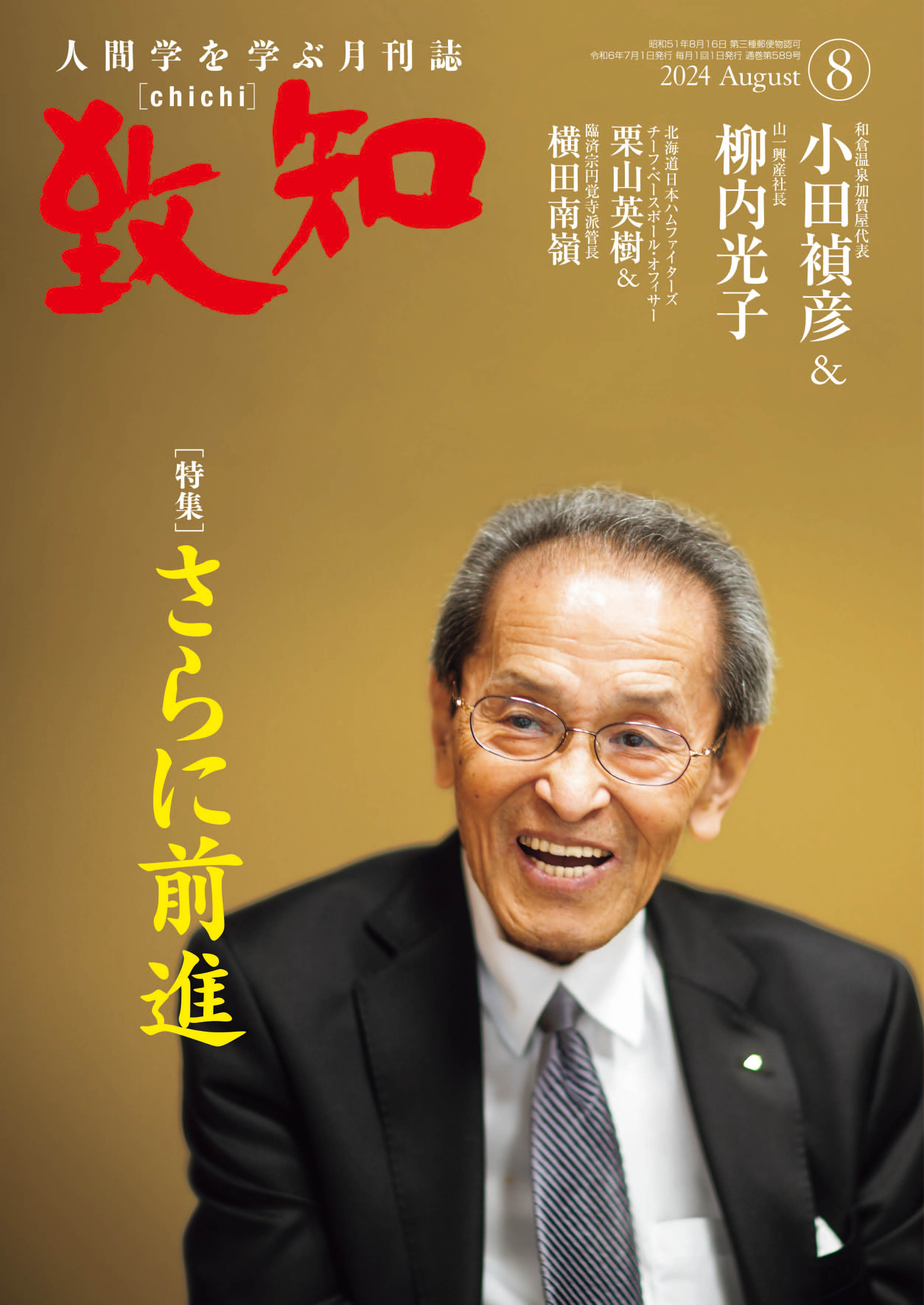7 月号ピックアップ記事 /インタビュー
試練によって安岡教学を活学した我が人生 田中昭夫(姫路師友会会長)

東洋学の泰斗・安岡正篤先生が逝去されて40年以上が経過した。姫路師友会会長の田中昭夫氏は数少なくなった面授の弟子のお一人である。様々な人生の逆境の中で、田中氏はいかに安岡教学を活学してこられたのだろうか。安岡先生との邂逅を交えて、その師資相承の歩みを伺った。
「学ばずして、煩悶する勿れ」。要は悩むようだったら早く学びなさいということですね。
いまはいろいろと悩みを抱えて悶々とするうちに心を病んでしまう人も多いようですが、そういう時はさっと頭を切り換えて安岡教学など人間学の教えに触れる。
そうすることで解決の糸口が見つかるのではないかと思います
田中昭夫
姫路師友会会長
――田中さんは長年、姫路師友会会長として安岡教学の伝承に努めていらっしゃいますね。
〈田中〉
はい。昭和47年の姫路師友会の設立以来、半世紀以上その活動に携わってまいりました。この間、安岡正篤先生のご高弟の先生をお招きした講義や研修会、『論語』『大学』『易経』『史記』など東洋古典の勉強会を今日まで続けてきております。
実は姫路の地は安岡先生との縁が深いんです。先生のご尊父・堀田喜一氏が姫路にある天台宗・書写山円教寺を訪ねて奥様の安産を祈願された時、本堂でお祈り中に偶然にも黄金の観音様を入手して持ち帰られ、ほどなくしてお生まれになった安岡先生に生涯のお守りとして授けられるんです。安岡先生は終生、腹部に巻いた晒の中にこの観音像を入れて大切にされていたと言います。
この話は姫路師友会初代会長の岩松保先生が赤穂にお越しになられた時、安岡先生から直接お聞きになった話なのですが、この岩松先生は私と安岡先生とのご縁を結んでくださった方であり、岩松先生の存在なしに今日の私は存在しません。その意味で掛け替えのない人生の師匠なんですね。
――安岡先生との出逢いはどのようなものだったのですか。
〈田中〉
それをお伝えするのに少し私の生い立ちからお話ししたいのですが、私は昭和16年に大分県別府市で生まれました。すぐに大東亜戦争が始まりまして、連合軍の日本本土への爆撃が激化した19年秋に母の故郷・国東半島の国東町に疎開し、その土地に住み着くようになったのです。ここは半農半漁の町で、田畑などの生活基盤がない両親が一家を養うのは並大抵のことではありませんでした。
おまけに……(続きは本誌にて)
~本記事の内容~
▼安岡教学を伝承し半世紀以上
▼「焦るな、そのうちに分かる」
▼先人の教えで苦難を乗り越える
▼大切なのは学ぼうという姿勢
プロフィール
田中昭夫
たなか・あきお――昭和16年大分県生まれ。大分県立大分工業高校卒業後、富士製鉄広畑製鉄所に入社。48年齊藤鋼材に入社し企業再建などに携わる。平成20年アビノに入社、社長、会長などを歴任。姫路師友会では昭和47年の設立から事務局長を務め、平成21年会長に就任。吟道清峰流猶興吟詠会総本部会長。
特集
ピックアップ記事
-
対談
孔子とその弟子たちの物語
宇野茂彦(斯文会理事長)
數土文夫(JFEホールディングス名誉顧問)
-
対談
己のコスモを抱いて生きる
後藤光雄(葆里湛シェフ)
奥田政行(アル・ケッチァーノ オーナーシェフ)
-
エッセイ
頭山満と幕末三舟【英傑に学ぶ日本精神の神髄】
田中健之(歴史作家)
-
インタビュー
感謝を忘れず粛々と精進するのみ
大倉源次郎(能楽小鼓方大倉流十六世宗家/人間国宝)
-
インタビュー
試練によって安岡教学を活学した我が人生
田中昭夫(姫路師友会会長)
-
インタビュー
人生の師・鍵山秀三郎氏に学んだこと
白鳥宏明(白岩運輸社長)
-
インタビュー
師資相承の要諦は直心にあり
河野太通(龍門寺長老)
-
エッセイ
齋藤秀雄と小澤征爾——二人の遺したもの
秋山和慶(指揮者)
-
対談
紛れもない私を生き切れ——師と弟子が語り合う「日本人にいま伝えたい魂のメッセージ」
行徳哲男(日本BE研究所所長)
松岡修造(スポーツキャスター)
好評連載
バックナンバーについて
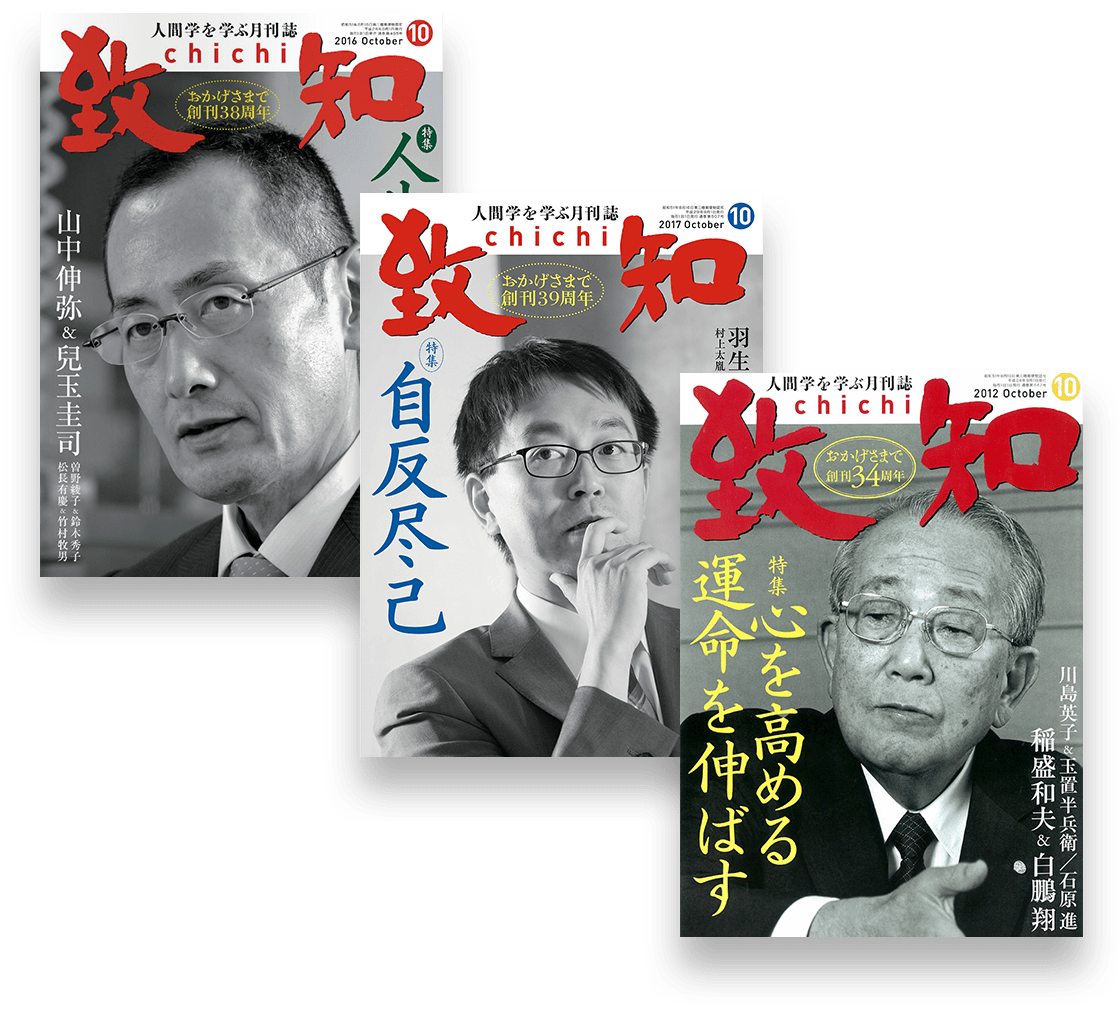
バックナンバーは、定期購読をご契約の方のみ
1冊からお求めいただけます
過去の「致知」の記事をお求めの方は、定期購読のお申込みをお願いいたします。1年間の定期購読をお申込みの後、バックナンバーのお申込み方法をご案内させていただきます。なおバックナンバーは在庫分のみの販売となります。
定期購読のお申込み
『致知』は書店ではお求めになれません。

電話でのお申込み
03-3796-2111 (代表)
受付時間 : 9:00~17:30(平日)
お支払い方法 : 振込用紙・クレジットカード