『致知』に寄せられたお客様の声
『致知』を読んでのうれしいお便りがたくさん届いています。 ご感想の一部を紹介いたします。
-
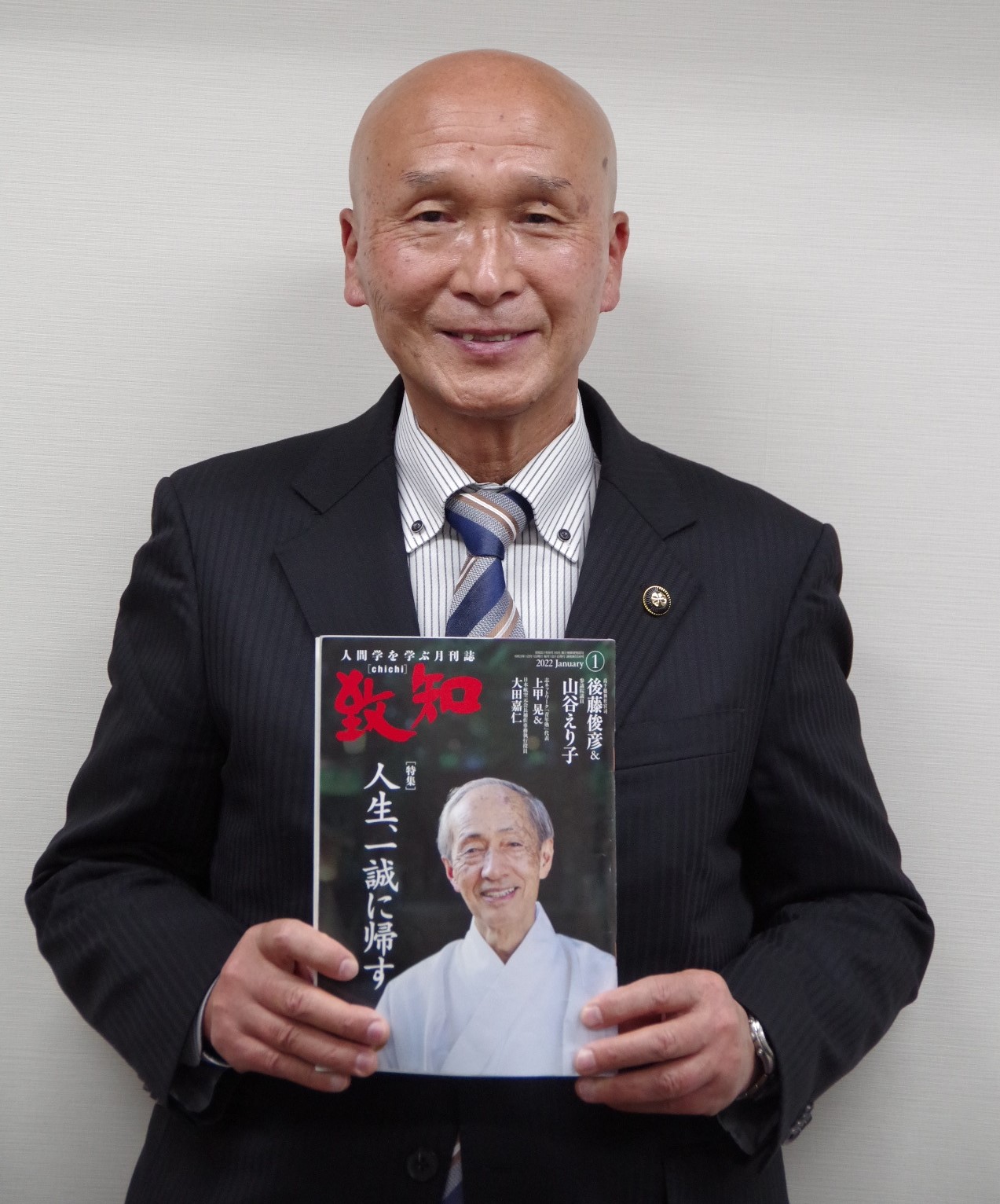
『致知』は人間力を高める1番の教材
宮崎県在住 西都市市長 橋田和実さん(69歳)『致知』との出逢いは、いまから約30年前、宮崎県議会議員を務めていた時のこと。宮崎県にあった西都木鶏クラブで熱心に勉強されていた知り合いから勧められたのがきっかけです。残念ながら西都木鶏クラブは6年ほどで解散したと記憶していますが、『致知』だけは今日に至るまで長く愛読させていただいています。
『致知』と歩んできたこの30年間は、私の政治人生と重なります。七転び八起きといいましょうか、これまで私は3度の落選を経験しました。平成17年2月から29年2月までは3期連続で市長に当選したものの、4期目に落選。このタイミングで「石井記念友愛社」の理事長で『致知』の愛読者でもある児嶋草次郎氏から「『石井十次の会』の会長をやってほしい」とお話をいただきました。
石井十次は、明治時代に日本で最初の孤児院を創設した人物であり、「児童福祉の父」といわれています。「石井十次の会」は、石井十次の愛と理念を継承して、福祉・文化・教育活動を続けている石井記念友愛社のさらなる発展のために、物心両面から支援する団体です。大自然の中で農業や掃除をはじめ集団生活を通して、親からの虐待を受けた子供たちの心にある人間不信を取り払い、志を育て、人間らしく教育していくことを主軸に置いています。 児嶋理事長から会長役をお願いされた時、初めは「私に務まるわけがない」とお断りしたものの、「いや、あなたにやってほしいんだ」という熱意に折れ、「それなら私も学ばせていただこう」と、会長に就任しました。4年間現場で学びながら子供たちと接し、政界には戻らないと決めるも、昨年1月に「どうしても出馬してほしい」と周囲からお声を何度もいただき、ありがたいことに2月に市長に就任したのです。
絶えず人生を前向きに開拓していくことが大切であり、苦難を試練と捉え、乗り越えることで人間性が高まるとは、『致知』で学んだ精神です。一度市長を退いたのは「現場での実践を通して『致知』の教えをさらに深めなさい」という、天からのメッセージだったと受け止めています。 昨年末から西都市で未来リーダー塾を発足し、『致知』を教材に推薦したのは、私自身、『致知』を指針に生き、政治や教育、どんな分野でも人間力を高めるには1番の教材だと思い至ったからです。主催者に伝えると「これはいい雑誌ですね」と意気投合し、以来16名の20代、30代の受講生で月に1回勉強会を実施しています。
『致知』では様々な人の生き方を学ぶことができます。実践せずとも、登場された方々の生きた学びを得られ、人生をより豊かにすることができると実感しています。
死ぬまでが勉強。仕事は修練の場です。常に前向きに、どんな苦難が起きても「ありがたい」「天が期待してくれている」と受け止め、これからも歩んでまいります。
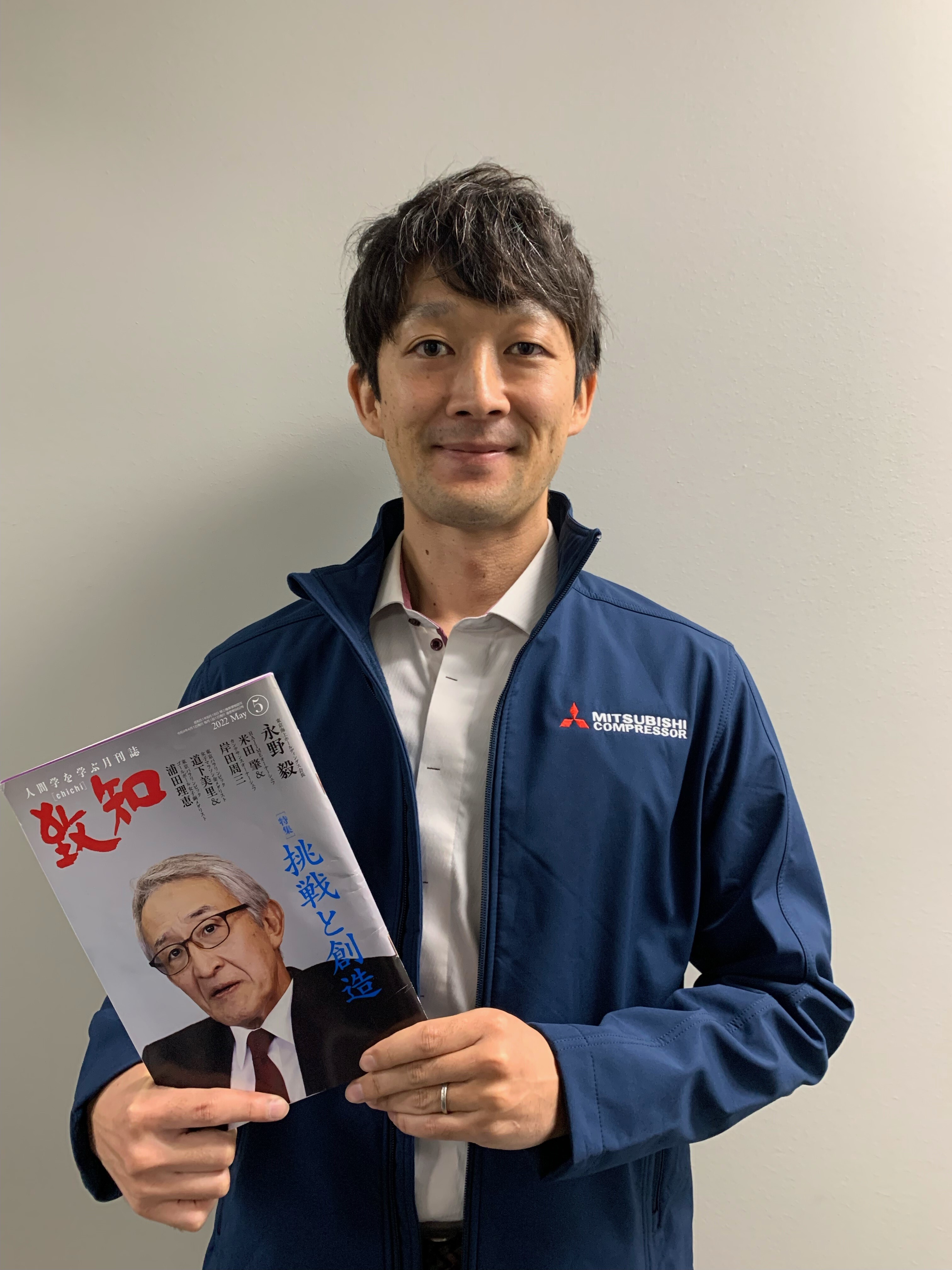
『致知』は私の人生の羅針盤
アメリカ在住 Mitsubishi Heavy Industries Compressor International Corporation 吉原大志さん(33歳)私と『致知』との出合いは2015年、25歳の時です。尊敬する上司が職場の本棚に並べていた『致知』に興味を持ち、昼休みに読み始めたのがきっかけでした。
『致知』に惹かれたのは、記事を通じて素晴らしい人生の師に出会えるからです。吉田松陰先生の「能わざるに非ざるなり、為さざるなり」、ダーウィンの「強いものが生き残れるのではない、変化に対応できるものが生き残れるのだ」等々、 『致知』や致知出版社の本を通じて学んだ数々の金言が、心が乱れたり、雑な行いをしたりしてしまった時に、スッと正道へ引き戻してくれる羅針盤となっています。
中でも印象に残ったのが、量子力学的な生き方を分かりやすく説かれている村松大輔さんの記事でした。普段自分が発する意識(バイオフォトン)が現実をつくる(物質化現象を起こす)という学びを得たおかげで、不都合な出来事に遭っても自分にベクトルを向け、周囲に感謝できるようになったと感じています。おかげさまで、『致知』を読み始めてほどなく最愛の妻と出会い、またエンジニアとして最難関国家資格である技術士に合格することができました。 『致知』の言葉が私の血肉となり、私から発せられる周波数が変わったからこそ、人生が大きく開けてきたのだと確信しています。『致知』と出合ったおかげで、私の本当の人生が始まったといっても過言ではありません。
現在は、文化も言語も異なるアメリカのヒューストンへ赴任し、赤ちゃんに戻ってしまったような感覚を味わいながら、試行錯誤の毎日を送っています。 人生の新たなステージで支えになっているのが、「致知電子版」です。使い慣れたスマートフォンでいつでもどこでも『致知』の記事を読み、視座を高めております。
これからも『致知』という人生の羅針盤を片時も手放すことなく、正道を歩み続けていきたいと思います。

僕のいのちと心を救ってくれた『致知』
大阪府在住 西出憲功さん(50歳)幼く、小さなことしかできない僕は、父や母に教えられて人生の航海へと旅立ちました。その旅の途中でいじめ抜かれました。そして恋をしました。けれども愛し過ぎたためにその女性の心が分からず、すれ違い、結婚は破綻しました。
その後、精神に亀裂が走りました。心に大きな穴があいてしまいました。うつ病でした。いまだに病気は完治していません。悲しくて、苦しくて、辛い出来事でした。腰も悪く、脊柱管狭窄症の手術もしました。いまはリハビリ中です。病院の先生がおっしゃるには、八十五歳の腰と同じだということです。
こんな腰で、この先いったい、何ができるんだ!
僕は、神を呪って、呪って、呪い尽くしました。
両親をどこにも連れて行けない。好きだった料理一つもつくれない。ただ涙の量が増えたことだけ知りました。
それでもいまは、前を向いて一所懸命生きています。そのきっかけをつくってくれたのは、去年から読み始めた『致知』です。『致知』は僕に、生きることを諦めちゃ駄目だ、と教えてくれます。勇気を持って困難・試練に立ち向かおうと背中を押してくれます。
いろいろなことがあったけれど、いまはその一つひとつに感謝しております。これらがなかったら、人間・人生を勉強させてもらえる『致知』と出合えていなかったかもしれません。
致知出版社の皆さん、本当にありがとうございます。これからも人間・人生を教えてくれる『致知』をつくり続けてください。
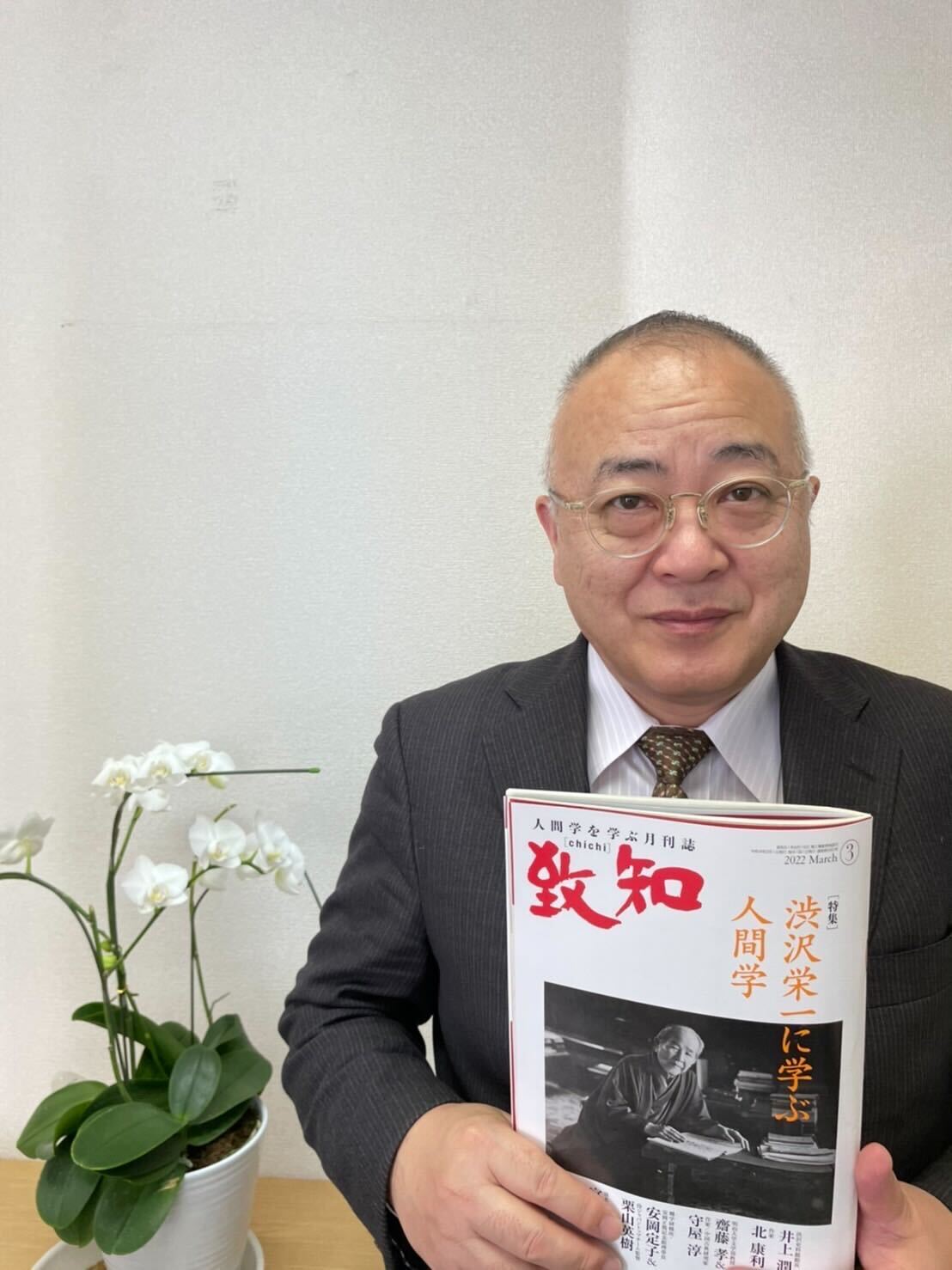
生き方を学ぶための最高の雑誌
千葉県在住 越川宗亮さん(59歳)『致知』と出逢ったのは、いまから約40年前、高校生の時でした。当時から「人間の生き方」に興味があった私は、書店で見かけた『致知』に、ほかの雑誌とは明らかに違う強烈なインパクトを感じたのです。 「もう少し年齢を重ねて、人生経験をしたら、この内容がもっと分かるんだろうな」 そんな思いで、書店で見かけるたびに手に取って読んでいましたが、定期購読を始めてからは今年で9年目になります。
その後、私が代表を務めるシンクロニシティ研究会でも、仲間と共に愛読してきました。 『致知』の魅力は、有名無名を問わず、様々な方の体験から「こんな生き方があるのか」「こんな考え方があるのか」という気づきを与えてくれるところにあります。 『致知』で学んだことは、少なからず私の血となり、肉となり、骨となっている――。自分の人生を形づくってくださったのが紛れもなく『致知』なのです。最も勉強になる雑誌だと思っています。
特に、2020年2月号で指揮者・西本智実さんと対談をされた、和紙デザイナー・堀木エリ子さんのお話は印象的でした。 スポーツの世界で体幹が大事だと言われるように、人生にも体幹となる、柔軟な自分軸を持つことが大切です。その軸をつくるための栄養素になってくれるのがほかでもない『致知』だと感じています。これからも生きている限り、学び続けていきたいと思います。

子供たちと共に学び続けて
愛知県在住 伊藤彰浩さん(57歳)「いい本があるから、読んでみてくださいよ」そう言われて2冊の『致知』を受け取ったのは2015年のことでした。私自身、『致知』に出逢うまで、人はどのように生きればよいのか、その答えを得られずにいました。『致知』には、宗教などの自分から遠い学びではなく、私たちの経験の中にある普遍的な出来事から得た教訓や、立派な方々の苦労話、感動的な話を読むことができます。自分にぴったりくる雑誌だと確信し、これは自分だけにとどまらず、周りの方にどんどん紹介したいという気持ちになりました。
そんな時、星稜中学校や大分中学校の学生たちが木鶏会をやっていると聞き、刺激を受けたことをきっかけに、私が会長を務める中学生の野球チームで子供たちの木鶏会をスタートさせたのです。人間の基礎をつくる中学生までに、子供たちをしっかり育てておかないといけない――。そんな想いで始めた木鶏会ですが、『致知』をしっかり読んで感想文を書く、この繰り返しの中で子供たちの理解はどんどん深まっていきました。指導者が真剣に取り組むからこそ、子供たちも真剣についてきてくれたのだと思います。 木鶏会を始めてからは、「本当にこれで中学生かな?」と思うくらい、子供たちがしっかりしてきたことを感じます。
『致知』はとにかく読むことが大事です。最初は難しく感じるかもしれませんが、その人の気持ちになって読めるように特訓すると本当に面白い。とてつもないパワーが出てくるような、その人の潜在能力が湧き出てくるような本です。今後も子供たちと共に、『致知』に学び続けていきます。







