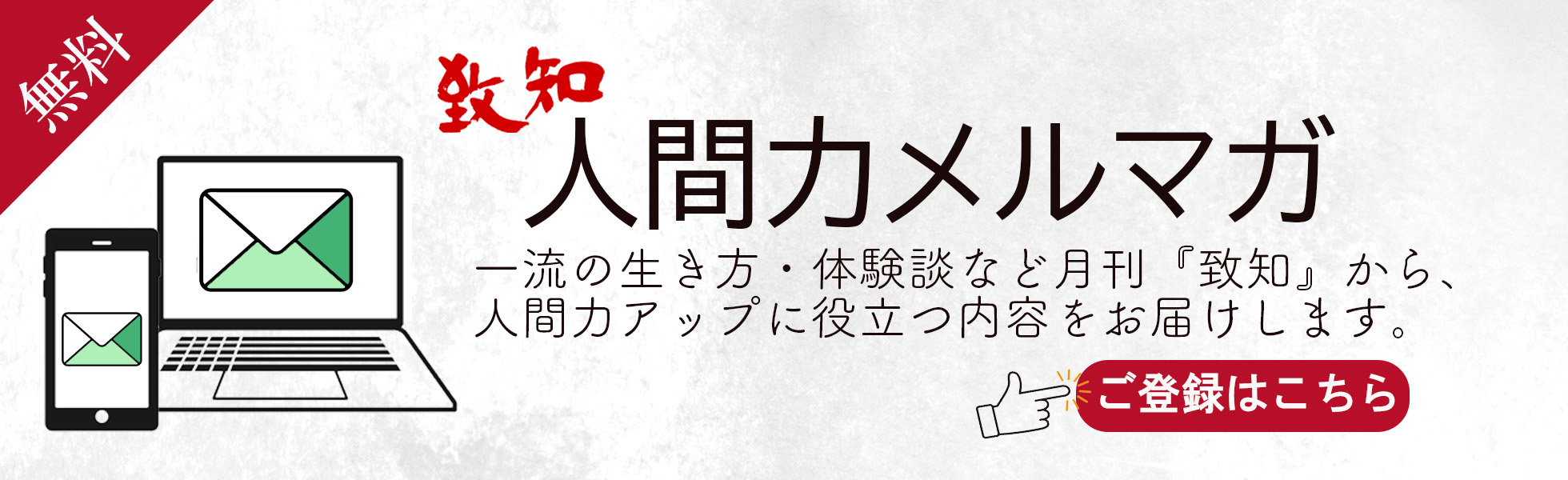2019年10月25日
 「デザイン」という言葉自体が知られていなかった戦後日本で、「バタフライスツール」をはじめとした優れたデザインを追求し続けた柳宗理(1915~2011年)。日本を代表する工業デザイナーとして活躍したその原点には、民芸運動の創始者だった父・柳宗悦が求めた「用の美」があったといいます。
「デザイン」という言葉自体が知られていなかった戦後日本で、「バタフライスツール」をはじめとした優れたデザインを追求し続けた柳宗理(1915~2011年)。日本を代表する工業デザイナーとして活躍したその原点には、民芸運動の創始者だった父・柳宗悦が求めた「用の美」があったといいます。
◎各界一流の方々の珠玉の体験談を多数掲載、定期購読者数NO.1(約11万8000人)の総合月刊誌『致知』。あなたの人間力を高める、学び続ける習慣をお届けします。 たった3分で手続き完了、1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。
※購読動機は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください
父・柳宗悦が説いた「用の美」
民芸運動の創始者であった父・柳宗悦は、“用の美“ということを説いた。手仕事で造られた使い勝手のよい道具は、自ずと美しいというのである。
私は、工業デザイナーとしての道を歩んできたが、この“用の美“の視点から見ると、世の中に氾濫するデザインには、目もあてられぬほど病弱で歪んだ醜いものが多く、残念でならない。実際、美しいものは少ないのである。それだけに、この“用の美“ということは、現代的な課題といってもいい。
30年ほど前、イタリアの企業家ルブロフスキーが来日した。芸術に造詣が深く、立派な本を出版していたこともあって、仲間うちで彼を招待してご馳走しようということになった。その時、たまたま私のデザインしたフォーク、ナイフ、スプーンが、食卓に並べられたのである。
友人の一人が、よせばいいのに「これは柳のデザインだ」と吹聴した。それを聞いたルブロフスキーから、「こんな悪いデザインはない。ナイフもスプーンもフォークも食べるための道具である。その食器がカチッというような金属では、食べ心地がよくない。日本の箸のほうが、よほど優れている」という手厳しい返事が返ってきた。私は、恐縮するよりも、ルブロフスキーの言葉に、すっかり感激してしまった。
彼は、食べるための道具として、何が一番ふさわしいかしか考えていない。ナイフ、スプーン、フォークといった食器の概念すら捨て去っている。私には「食べるための道具」を根本に立ち返って考えなさいと聞こえたのである。
常識を捨て、根本に立ち返ることは、大変勇気のいることで、非常に難しい。しかし、このことの大切さは、あらゆることに通じるのではないだろうか。
バウハウス理論と民芸論の共通点
工業デザイナーである私が、日本民芸館の館長になっていることに、奇異の念を持たれる方が多い。柳宗悦の長男だからと理解されているむきもときどきある。確かに私は青年の時分、父の民芸運動にかなり反発したものだ。しかし、自分がデザインの道に深く入れば入るほど、民芸への関心が強くなっていったことを覚えている。
20世紀初頭、ドイツでは、バウハウスが機械製品の美的価値を初めて称揚し、近代デザインの基礎を築いた。これは大変に興味深いところで、両者とも人間生活自体に関して大変示唆に富む主張を行っている。バウハウス理論は次の5項目に要約できるが、それは父の民芸論とほとんど同じといっても過言ではない。
私自身、デザインの勉強を進めていくうちに、バウハウスに近づき、逆にその類似性から、民芸への再認識が始まったのである。
1、「用」――これは、人間の造るものが大衆生活に密接に結びついていなければならず、そこにこそ、これからの芸術は存在するというもので、民芸論の「用の美」と共通する。
2、「技術」――時代の中で新しく生まれてきた技術をいかにうまく用いるか。技術そのものを生かす。
3、「材料」――材料そのもの、素材をなるべく生かして造るのが本当の美しさである。
4、「量産」――日常の生活に使われるものだから量産できなければいけない。純粋美術の作品が一点であることと、大きな違いがある。
5、「経済的」――大衆のためのものであるから、安価で誰もが手に入れられるものでなければならない。
以上の5項目の中で、民芸論との違いをいうと「技術」と「量産」のニュアンスが少し違う。つまり、民芸の手工芸的生産に対し、バウハウスでは、機械的生産であるから、手段が異なるだけでなく、量産の量に格段の差がある。
しかし、その説く基本は、いずれも人間の日常生活に欠かせない大衆的製品で、しかも、そこに美を認めているのである。民芸においては、手仕事ということを重視するが、新技術に対して否定するわけではない。ただ、新技術を使って出来上がったものに、醜悪なものが多いと危倶しているのである。
世界的デザイナーが日本民芸館に訪れる理由
民芸に、素朴でプリミティブな美しさがあることは異論があるまい。父が民芸論を展開していたのと同じころ、ヨーロッパでもプリミティブアートが認められ始めている。
人間が最初に作ったもの、初めに出た芽というものは、感覚的に非常にモダンだといっていい。その証拠に、日本民芸館には、海外の第一線で活躍しているデザイナーや建築家が来館して感激して帰っていく。コルビエ、グロチウスといった人などは、民芸館にたびたび来ているが、その作品に触発を受けると言っている。
そのデザインを模倣しているわけではないが、彼らは、作品から受ける素朴な美を体に受け入れて、自分の作品の中で生かしているのだ。
最先端のデザイナーが民芸から触発されることに対して、一般の方から見ると、何か不思議なことに思われるようだ。しかし、民芸作品は、その健全な純粋さとでもいうべきものがあるために、非常にモダンで、現代の求めているものに近いといえる。
父は、科学的技術を利用しての美は表現しにくいとし、むしろ本当の美というものは、かつての民芸の中にあったとしている。しかし、それだけに現代に生きるデザイナーの道が、その言葉の中に明示されているのではなかろうか。
手工芸の心というものを、新しい技術を使って、現代に引き継ぐことが、私たち現代に生きるデザイナーの役割だと教えているのである。そして、それこそが私の歩む道である。
(本記事は『致知』1988年10月号 特集 「個性的リーダー」より一部抜粋したものです) ◎各界一流の方々の珠玉の体験談を多数掲載、定期購読者数NO.1(約11万8000人)の総合月刊誌『致知』。あなたの人間力を高める、学び続ける習慣をお届けします。 たった3分で手続き完了、1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。
※購読動機は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください
◇柳 宗理(やなぎ・むねみち)=工業デザイナー・日本民芸館館長・金沢美術工芸大学客員教授