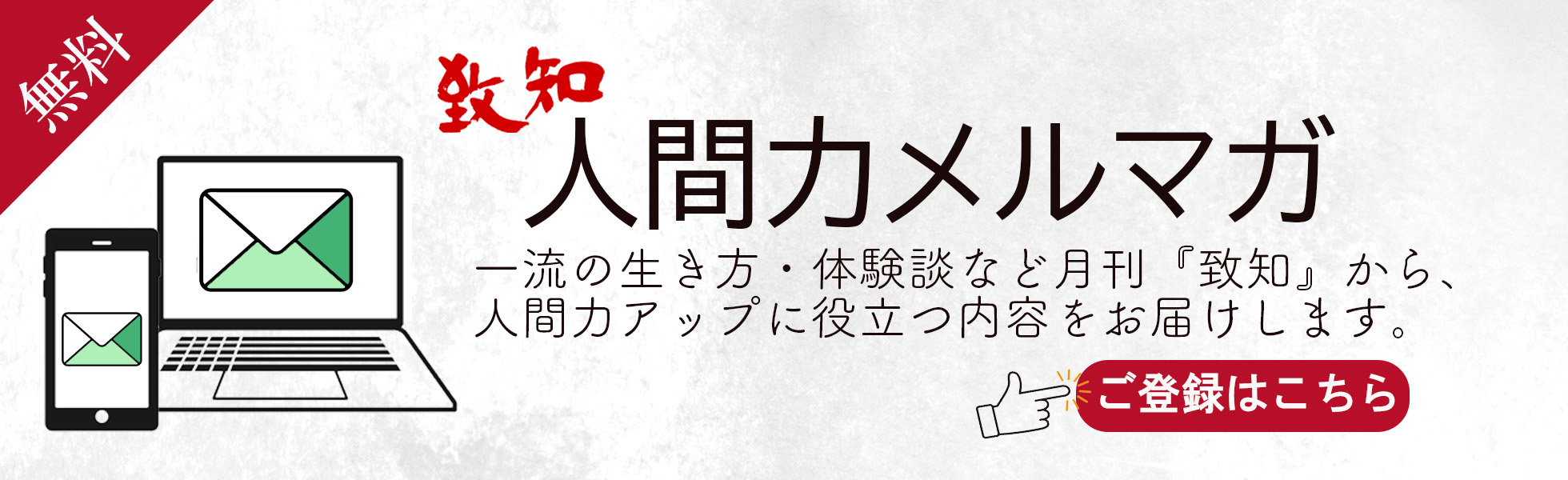2020年12月16日
 日本映画史を代表する美術監督として名高い故・木村威夫氏が、70代後半を過ぎて制作した『深い河』(原作・遠藤周作)。その撮影のために訪れたインドで偶然目の当たりにしたある風景を見て、木村氏は「私が映画の仕事に携わる意味、しいていえば、生きる意味」を教わったと述べています。木村氏の人生観・仕事観を大きく変容させたものとは一体何だったのでしょうか。
日本映画史を代表する美術監督として名高い故・木村威夫氏が、70代後半を過ぎて制作した『深い河』(原作・遠藤周作)。その撮影のために訪れたインドで偶然目の当たりにしたある風景を見て、木村氏は「私が映画の仕事に携わる意味、しいていえば、生きる意味」を教わったと述べています。木村氏の人生観・仕事観を大きく変容させたものとは一体何だったのでしょうか。
◎各界一流の方々の珠玉の体験談を多数掲載、定期購読者数NO.1(約11万8000人)の総合月刊誌『致知』。あなたの人間力を高める、学び続ける習慣をお届けします。
たった3分で手続き完了、1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。
※購読動機は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください
「インド人はガンガーに生まれ、ガンガーに死ぬ」
河の水面に、何か黒いものが見えた。プカプカと浮くその物体には、カラスが群れている。
「何だろう……」
そう思ったかたわらで一匹の犬が、いきなり河に飛び込んだ。犬は、その物体に向かってグングン泳いでいく。そして、物体に食らいつくや否や岸に戻ってきた。よほど腹をすかしているのだろう。ガツガツとむさぼり始めた。
「あれは、一体何ですか」
私の横で、やはり同じ光景を眺めていたインド人のガイドに尋ねる。
「死体です。人間の」
ガイドが事も無げにいったことが、私のショックをさらに大きなものにした。
つい先頃、熊井啓さんの監督作品『深い河』の撮影で、インドを訪れた。そのときに出会ったできごとである。ガンジス河流域では、身内の屍を河に流すことが珍しくないという。インドでは、家族の死体を焼く薪代すら払えない貧しい人が多い。彼らは身内が息を引き取ると、体を布にくるみ、河に葬る。その肉は、野良犬がむさぼる。そして、残った骨はガンジスの底に沈むのだ。
「インド人はガンガー(ガンジス河)に生まれ、ガンガーに死ぬ」
インドでは、そういわれている。おぼろげながらではあるが、その理由がわかるような気がした。
ガンジス河を眺めながら「生きること」の意味を考える
ガンジス河はインド人にとって「聖なる河」である。生も死も、日常も、人と河は完全に一体化している。人は、河に生まれ、河に帰る。そして、それは繰り返される。その真実の断片を目の当たりにしたような気がした。このとき私は、自分の中にあった一つの疑問が解かれたように思えたのだ。
「人はなぜ生まれ、何のために生きるのか」
その疑問に対する、答えである。いままで私は、「生きること」の意味を何度も自分に問うてきた。特に、仕事のなかでである。私の仕事とは、映画の美術監督。つまり、映画のなかで見えるもの、すべてが仕事の対象となる。
美術監督とは、映画のシナリオをもとに、具体的なシーンを考える仕事である。私はこの自分の仕事に満足感を持っていた。『サンダカン八番娼館 望郷』『千利休 本覺坊遺文』などでは、多くの評価をいただいた。
しかし、一つの仕事をやり終えた満足感は、そう長くは続かない。そして、次の仕事にそれを求める。その連続だった。
「より優れた作品をつくることは、私の根本。でも、自分の満足感のためだけにそうするのだろうか」
そんな思いが、絶えず私の頭のなかにあった。その答を見つけるヒントに、私はインドで出会ったのである。
「映画は、それが完成したときから、つくり手のものではなく、観る人のものになる」
生あるものは、必ず死ぬ。それは、悲しさやつらさを超えた、私たちにはどうすることもできない自然の理である。
「それならば、生きることによって、もしくは死ぬことによって、他の生あるものに対して少しでも多くを伝え、残していかなくてはならない。そしてそこから新たな何かが生まれ、つくられていく。それが繰り返される。ならば、生あるうちに私は、映画のなかで何かをつくり、伝えていこう」
心からそう思えた。この世のなかのすべては、循環している。
「映画は、それが完成したときから、つくり手のものではなく、観る人のものになる」
身に沁みて、そう感じた。より多くの観客を動員することは、必ずしも収益を上げるためではなく、より多くの何かを伝えていくのが本質的な目的である。インドは、私が映画の仕事に携わる意味、しいていえば、生きる意味を教えてくれた。
(本記事は『致知』1995年3月号 特集 「人間の味」より一部抜粋したものです)
◎各界一流の方々の珠玉の体験談を多数掲載、定期購読者数NO.1(約11万8000人)の総合月刊誌『致知』。あなたの人間力を高める、学び続ける習慣をお届けします。
たった3分で手続き完了、1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。
※購読動機は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

◇木村威夫(きむら・たけお)=映画美術監督