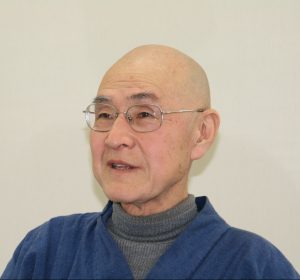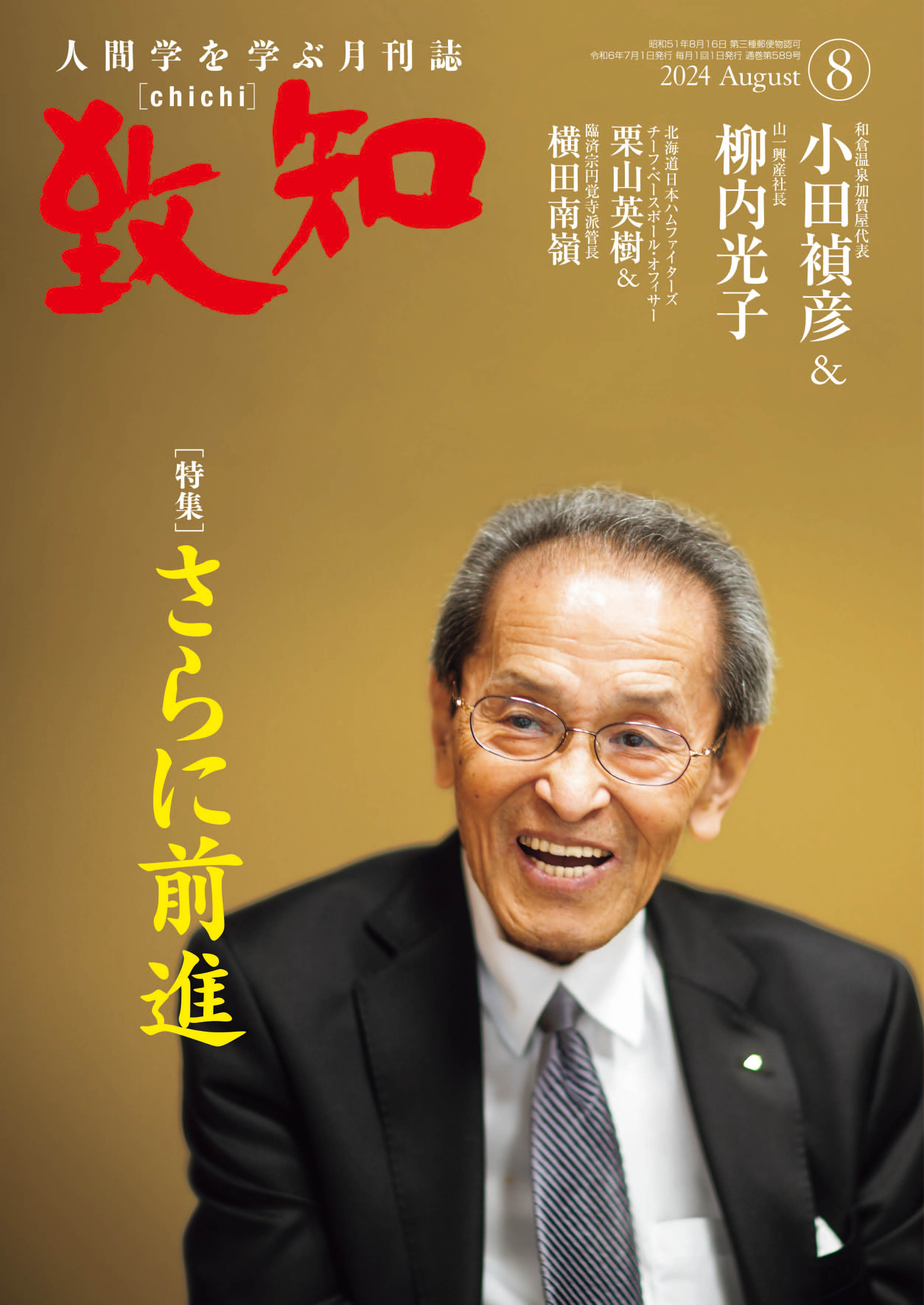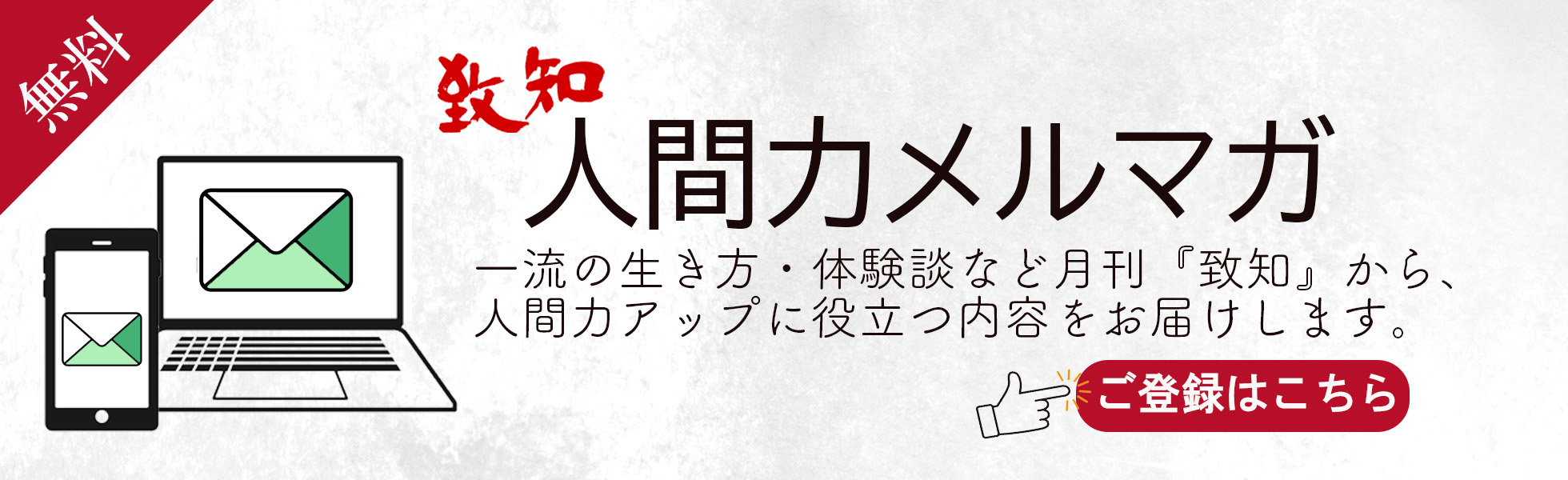2018年08月29日
 小林義功和尚は、禅宗である臨済宗の僧堂で8年半、真言宗の護摩の道場で5年間それぞれ修行を積み、その後、平成5年から2年間、日本全国托鉢行脚を行うという大変ユニークな経歴の持ち主です。義功和尚はどういうきっかけで仏道を志し、どのような修行体験をしてこられたのでしょうか。WEB限定で新たに配信する当連載では、ご自身の修行体験を軽妙なタッチで綴っていただきました。今回は苛酷な護摩行の思い出です。
小林義功和尚は、禅宗である臨済宗の僧堂で8年半、真言宗の護摩の道場で5年間それぞれ修行を積み、その後、平成5年から2年間、日本全国托鉢行脚を行うという大変ユニークな経歴の持ち主です。義功和尚はどういうきっかけで仏道を志し、どのような修行体験をしてこられたのでしょうか。WEB限定で新たに配信する当連載では、ご自身の修行体験を軽妙なタッチで綴っていただきました。今回は苛酷な護摩行の思い出です。
「ビリビリ、ビリビリ」と振動する障子
昭和63年12月24日に無文老師は遷化され、翌平成元年1月に御葬儀が厳修された。そして、2月に私は祥福僧堂を下山。伊丹空港から鹿児島へ飛び、バス、鉄道を乗り継いで、念願の修行道場高野山真言宗最福寺に来た。
道場の入り口に立つと太鼓を打ち込むたびに、2枚の障子が「ビリビリ、ビリビリ」と振動している。「気合が入ってるな」と思いつつ中に入った。護摩壇正面の不動明王はもとより、天井から壁まで真っ黒。煤(すす)だらけである。導師が祈願札を次々炉に投げ込むと、炎がフワーと舞い上がり天井を焼くかとばかりメラメラと燃え上がる。弟子たちは太鼓の音に勇み立ち、真っ赤な顔を燃え盛る炎にグイグイ突き出して、絶叫する。不動真言の声が割れんばかりに反響する。その凄まじい迫力と熱気が雑念を吹き飛ばして祈願を成就させるのか・・・。私もその道場の一角に正座していたが、いつしか不動真言が口からあふれ、腹の底から大きな声を発していた。
行が終わってから導師である池口恵観先生に呼ばれ面談を受けた。そして、翌日から行に参加することになった。後で分かったが、この行は通常の護魔行ではない。一日一萬本の乳木(護摩木)を焚く。それも百日間ですから百萬枚。これは前代未聞の荒行である。それに果敢に挑戦したのが池口恵観導師だった。たまたまこの行に遭遇したのも、不思議なご縁である。毎日この行に参加する人たちで堂内はあふれ、五月十四日無事に結願(けちがん)を迎えた。
私は禅宗の先輩から国際禅道場を開設するにあたり、以前から手伝いを頼むといわれていたから、一旦鹿児島を離れ、半年ほどか・・・。一段落したところで最福寺の弟子となり本格的に修行を始めた。
鹿児島は九州の最南端である。錦港湾に浮かぶ桜島とその噴煙。また、街路樹には椰子やフェニックスといった熱帯植物。日本であって日本でないようなこの南国鹿児島の風景は結構楽しい。
時には突如、ドーンと衝撃が走る。窓がガタガタ音を立てて揺れる。地震だと騒ぐと地元の人たちは「桜島の噴火ですよ」と笑っている。その噴煙は上昇し風向きにも寄るが、バラバラ、バラバラ灰となって地上に落ちてくる。珍しい風景である。修行、修行とのめり込んできた為とはいえ、この鹿児島の地まで来たかと思うと感慨深いものがあった。
わずかな隙も見せられない真剣修行
ここでの修行は常在戦場、緊張の連続である。師匠からの電話は恐怖である。リーンと鳴ったら1、2、3、4と数える中に、受話器を取らなければならない。また、用件に即答できないと罰が課せられる。電話1つで鉄槌が下るのだから弟子たちの神経は常にピリピリしている。
護摩行の前に師匠と弟子が集る部屋を集会所(しゅえしょ)という。これから行をするのですから気合が入る。油断は出来ない。行は戦場ですから気の弛みを嫌う。真剣に挑むのか、だらけた気持ちがないか、その心が試される。ですから弟子たちは極度に緊張する。わずかの隙も見せられない。動きはすばやく。これが鉄則である。「義功」と呼ばれたら「はい」と声を張り上げる。この返答1つで行をする気迫があるかないか判定される。ないとみなされれば行から外される。
また、師匠は「カン」の冴えを喜ばれる。これも油断は出来ない。師匠が行のノートをスーと引き寄せる。その時、フト現れる微妙な変化を察知した弟子がスッーと立ち上がる。事務所に駆け込むとボールペンを取って師匠の前に差し出す。阿吽の呼吸というか、その機転を評価しその弟子をそばに座らせ、そこに座っていた弟子は部屋から追い出されるのだ。
冗談をいって笑わせることもある。しかし、弟子たちは、笑いながらも何時怒りに転化するかと、警戒を弛めることはない。全身の神経をピーンと張り詰めたままじっと耐え忍ぶ。この重圧に負けるようでは行は出来ない。耐えて耐えて、さらには跳ね返す気力が要請される。
さて、護摩行である。中央の護摩壇に師匠が導師となって着座する。その檀を挟んで左右に弟子たちが二列に座る。板の間に直に正座である。しかも3時間以上行は続くのですから、はなはだきついが、やらねばならない。
前讃から始まり、次にお経(理趣経)を唱える。ただ唱えればと口をパクパクしていればいいというものではない。師匠の微妙な感性と合致しなければならない。ですから、おろそかには出来ない。護摩木に火が入ると矢倉(やぐら)に組んだ檀木(だんぼく)から火が燃え上がる。そして、後讃が終わるといよいよ不動明王の真言に移行する。ドン、ドン、ドン、ドンと太鼓が調子を合わせる。リズムをつかむと皮を破るかとばかりに撥(ばち)を打ち込んでいく。2本の撥が踊り跳ねると、堂内はいつしか忘我の境地、力強い不動真言で満ち溢れ清浄無垢(しょうじょうむく)の不動明王が出現するか。・・・目には見えないが。
護摩壇の炎は益々大きく燃え上る。修行僧は汗でびしょ濡れである。鼻の頭や頬、印を組む指先が火傷をする。熱い!熱い! しかし、導師のサインからは目を離せない。左手がサッーと動く。「前へ」のサインだ。グイと前進出来ればいいが、熱気に負けて首を振る顎が上がる。上体がふらつき後ろにのけ反る。あるいは疲れと不眠から眠気に襲われる・・・すかさず降檀。壇上の修行者は炎と自分との必死の戦いが続くのである。
つづく