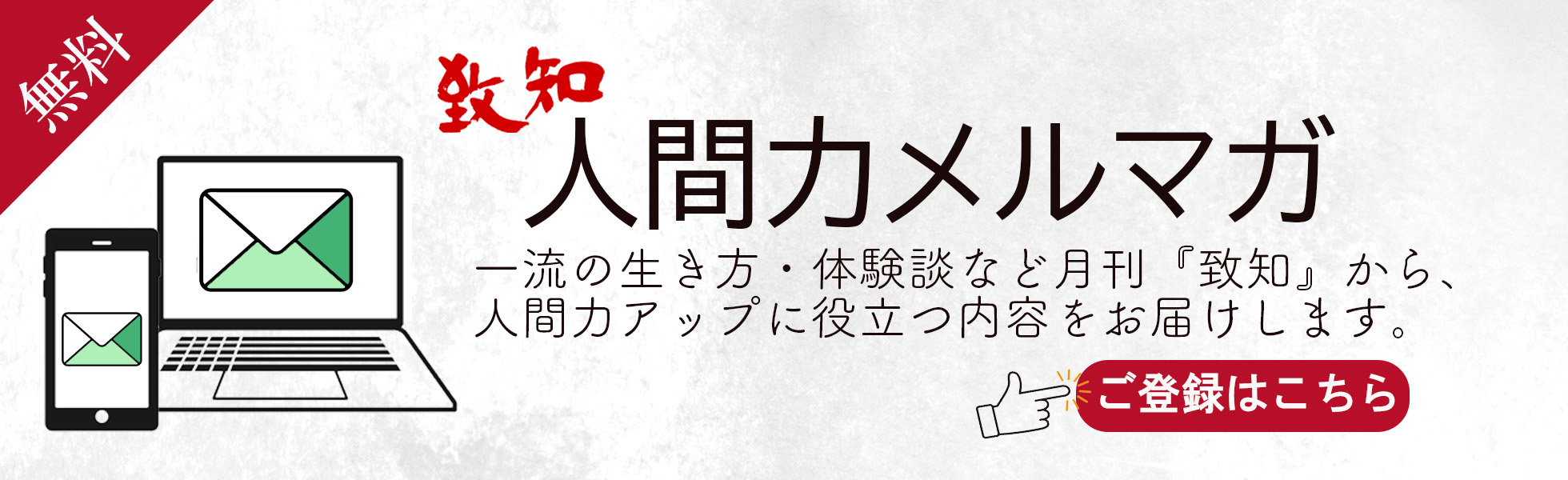2018年11月08日
 「古典と歴史と人物の研究――これなくして人間の見識は生まれない」
「古典と歴史と人物の研究――これなくして人間の見識は生まれない」
安岡正篤師の言葉です。古典力を養うことはそのまま人間力を養い、人生力を高めることに繋がっていくに違いありません。本記事では『致知』2004年2月号 特集「我流古典勉強法」より、古典を学ぶ意義、その継続が持つ力についての編集長コラムをご紹介します。
古典は人間形成に欠くべからざるもの
数年前、山口県萩に旅し、高杉晋作25歳のときの書というのを見た。墨痕鮮やかという言葉が陳腐化してしまうほど、それは雄渾な気品と力強い気迫、熟成した風格をもって迫り、25歳の青年が書いたものとはとても思えなかった。朝に武道に励み、夕べに四書五経をはじめとする古典に浸る。幼少期よりの朝鍛夕練の陶冶があって、あの書は結実したことは想像に難くない。
江戸期にさかのぼるまでもない。つい30年ほど前の日本にも、そこに存在するだけで人格的迫力を感じさせる、大人の風格を備えた経営者がたくさんいた。石坂泰三、土光敏夫、桜田武……。
あの人たちの大きさはどこからきたのか。たとえば石坂泰三の場合である。
石坂は学生時代、シェークスピア、テニスン、エマーソン、カーライル、ゲーテ、シラー、アンデルセンをすべて原書で読み、『古事記』『日本書紀』『祝詞』『万葉集』『古今集』を渉猟している。
そればかりではない。経団連会長として秒刻みの仕事をこなす中で、昭和37年、76歳のときにある試みに挑戦した。子どものころに学んだ古典の筆写を始めたのだ。画仙紙を和綴じにした筆写帳に筆で『大学』『中庸』『論語』『菜根譚』『古文真宝』、そして『万葉集』『徒然草』を写し終えたのは昭和40年。石坂は79歳になっていた。
石坂は言っている。「僕の場合、古典は年とともに自分の人間形成に欠くべからざるものになった。いろいろな場面で精神生活の大きな拠り所になった。実社会の生活にも大きく役立った」
幼いころから培った古典の教養。実社会の経験を積む中でそれを咀嚼し、己の実学としていった努力。そのたゆみない蓄積が厚みのある品格となって溢れだし、石坂を大きな存在にしたのである。
「最近は年輪を刻むように年を取る人が少なくなった」と言ったのは小林秀雄だが、年輪を刻むどころか、肉体的年齢はおとなだが精神的年齢は子どものままといった人がめっきり増えた。憂うべきことである。古典に親しみ、古典に心を洗う。その習慣を取り戻さなければならない。熟成したおとなの人格の涵養ために。