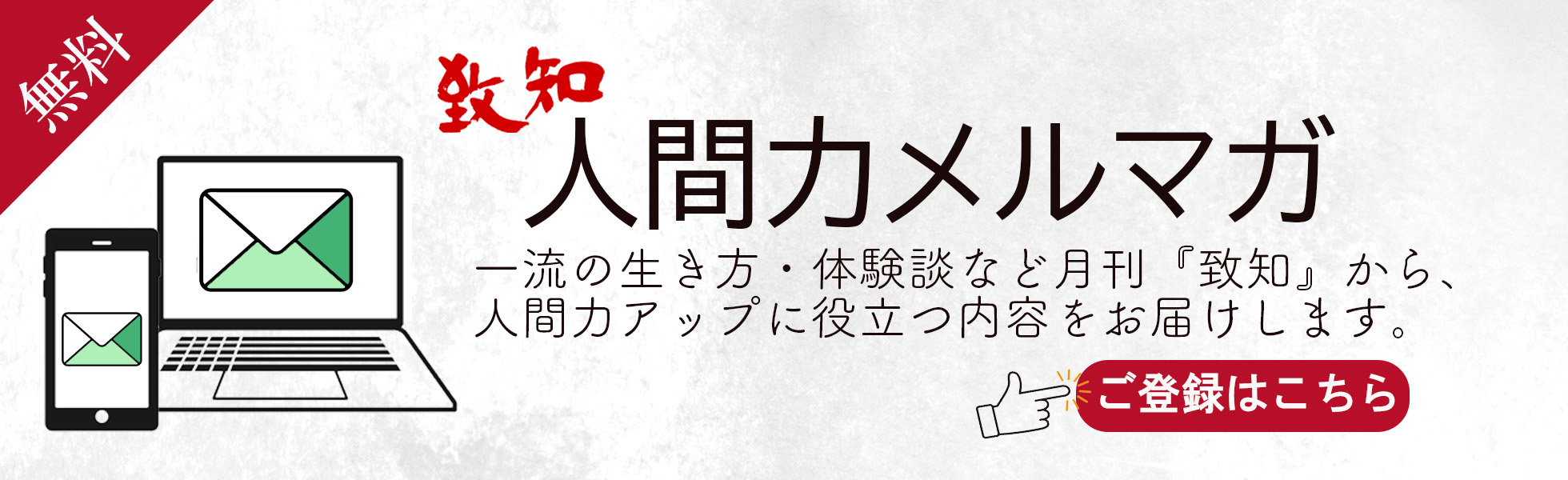2023年11月25日
 歴史には表と裏があります。多くの場合、戦の勝敗が決すると勝者にばかりスポットライトが当たりますが、敗走した兵たちにもまた、ドラマがあるものです。これは戦国時代、豊臣秀吉の養女として育てられ、宇喜多秀家の妻として生涯を全うした豪姫の物語。隠れた歴史の実話に心が温まります。語り手は博多の歴女こと白駒妃登美さんです。
歴史には表と裏があります。多くの場合、戦の勝敗が決すると勝者にばかりスポットライトが当たりますが、敗走した兵たちにもまた、ドラマがあるものです。これは戦国時代、豊臣秀吉の養女として育てられ、宇喜多秀家の妻として生涯を全うした豪姫の物語。隠れた歴史の実話に心が温まります。語り手は博多の歴女こと白駒妃登美さんです。
無念の敗走、その果てに
〈白駒〉
戦国武将・宇喜多秀家とその妻・豪姫。日本史上、ひときわ輝く夫婦の物語です。
前田利家とまつ夫妻の四女・豪姫は、子のなかった豊臣秀吉とねね夫妻のもとで、養女として大切に育てられました。一方、宇喜多秀家は十歳で父・直家を病で失うと、後を託された秀吉の手で立派な武将に育て上げられます。
二人にとって秀吉は育ての親であるとともに、結婚をとりもってくれた恩人でもあったのです。
その秀吉が死ぬ間際のこと。側室の淀殿との間で晩年にもうけた秀頼の行く末を案じた秀吉は、豊臣政権を支える五大老を枕元に呼びます。そこには徳川家康、前田利家、毛利輝元、上杉景勝ら重鎮が居並ぶ中、ただ一人、二十代の宇喜多秀家の姿もありました。
「返す返すも頼みまいらせ候」
と何度も頼む秀吉を目の当たりにして、今度は自分が秀頼様をお守りする番だと、秀家は心に誓ったことでしょう。
それから2年後の慶長5(1600)年、関ヶ原の合戦においても、秀家は何の迷いもなく石田三成率いる西軍につくと、その中軸として約6時間に及ぶ合戦を戦い抜くのです。
しかし秀吉への恩返しを誓った秀家の奮闘虚しく、相次ぐ裏切りの末に西軍は敗北。敗軍の将となった宇喜多秀家に科されたのは、八丈島への流罪でした。
豪姫は夫とともに八丈島に渡ることを切望しますが、許されません。当時は夫婦が何らかの理由で別れて暮らす場合、息子は父方に、娘は母方に引き取られるのが常でした。そのため豪姫は娘とともに前田家へ、二人の息子は秀家に伴われて八丈島へと向かったのです。
人の思いは時空を超える
自然環境の厳しい八丈島での暮らしは、秀家にとって苦難の連続でした。そんな秀家を何とか助けたいと願った豪姫は、前田家を通じて幕府の許可を得ると、毎年のように米や金子、衣類、雑貨、医薬品などを仕送りしたのです。
ある時豪姫は、絵師に描かせた自分の肖像画を荷物の中に紛れ込ませ、八丈島に送りました。その肖像画はいまも秀家の子孫がお持ちだそうですが、その肖像画の写しが、豪姫の菩提寺である大蓮寺(石川県金沢市)にあります。
色使いも含めて実に綺麗に描かれているのですが、よく見ると額の辺りだけ色が薄く、消えかけているのが分かります。これは八丈島に流されたまだ幼い息子たちが、毎日のように涙を流しながら「母上、母上……」と額の辺りを撫でていたためにそうなったのです。
若くして秀家と離れ離れとなった豪姫でしたが、その後は再婚話をすべて断り、金沢で61年の生涯を閉じました。いつかまた愛する家族と一緒に暮らしたいという豪姫の祈りは、残念ながら天に届くことはありませんでした。
もっとも、彼女のもう一つの祈りを天は聞き届けてくれたようです。
来る日も来る日も家族の無事を祈った豪姫。彼女が亡くなった時、八丈島に流された3人はまだ健在だったのです。それどころか人生50年といわれていた時代に、秀家は八丈島で49年生き長らえ、83歳で生涯を閉じました。きっと人の思いというのは時空を超えて、相手に届くのでしょう。
その後、八丈島に住む宇喜多家への仕送りは、加賀藩によって途切れることなく幕末まで続けられました。しかも新政府によって罪を解かれた宇喜多一族を船で迎えに行き、東京に住む家を用意して、生活の面倒までみたというのです。
いまも参拝に来る人がいること
幕末から明治にかけては、主に薩摩藩、長州藩が中心となって、大きく時代が展開していきました。
一方、経済力であれば徳川家に次ぐ実力を持ちながら、誰からも期待すらされない存在だった加賀藩。私はこのことをずっと情けないことだと思っていたのですが、この一連の物語を知ったことを機に、考え方が大きく変わりました。
「不易流行」という言葉があるように、物事には時代によって変えていくべきものと、変えてはいけないものがあります。あの時代、薩摩藩や長州藩が流行の部分を担ったのに対して、不易の部分にあたる、大切な人を思いやり、守り抜くことの尊さを示してくれたのが加賀藩であったと、私は思うようになったのです。
秀家と豪姫の時代から既に400年余りが経ちましたが、いまも大蓮寺にある豪姫の肖像画に「あの時はありがとうございます」と手を合わせに来る八丈島の人がいるといいます。「あの時」というのは、八丈島が飢饉に見舞われた時のことで、秀家は豪姫からの仕送りを、惜しげもなく飢えに苦しむ島民たちに分け与えていたのです。
秀家と豪姫から受けた恩を400年にわたって語り継ぐとともに、500キロ離れたお寺までお参りに訪れる島民たち――。私はその姿に、恩を尊ぶ日本人の美しさが見事に表れていると思うのです。
(本記事は月刊『致知』2016年9月号 特集「恩を知り 恩に報いる」より一部を抜粋・編集したものです) ◎各界一流の方々の珠玉の体験談を多数掲載、定期購読者数NO.1(約11万8000人)の総合月刊誌『致知』。あなたの人間力を高める、学び続ける習慣をお届けします。 たった3分で手続き完了、1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。
※購読動機は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください
◇白駒妃登美(しらこま・ひとみ)
昭和39年埼玉県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、大手航空会社の国際線客室乗務員として7年半勤務。平成24年には日本の素晴らしい歴史や文化を国内外に発信する目的で株式会社ことほぎを設立。「博多の歴女」として、講演、社員研修、ラジオ・テレビ出演など、年間200回に及ぶ。著書に『子どもの心に光を灯す日本の偉人の物語』『親子で読み継ぐ万葉集』(致知出版社)など多数。