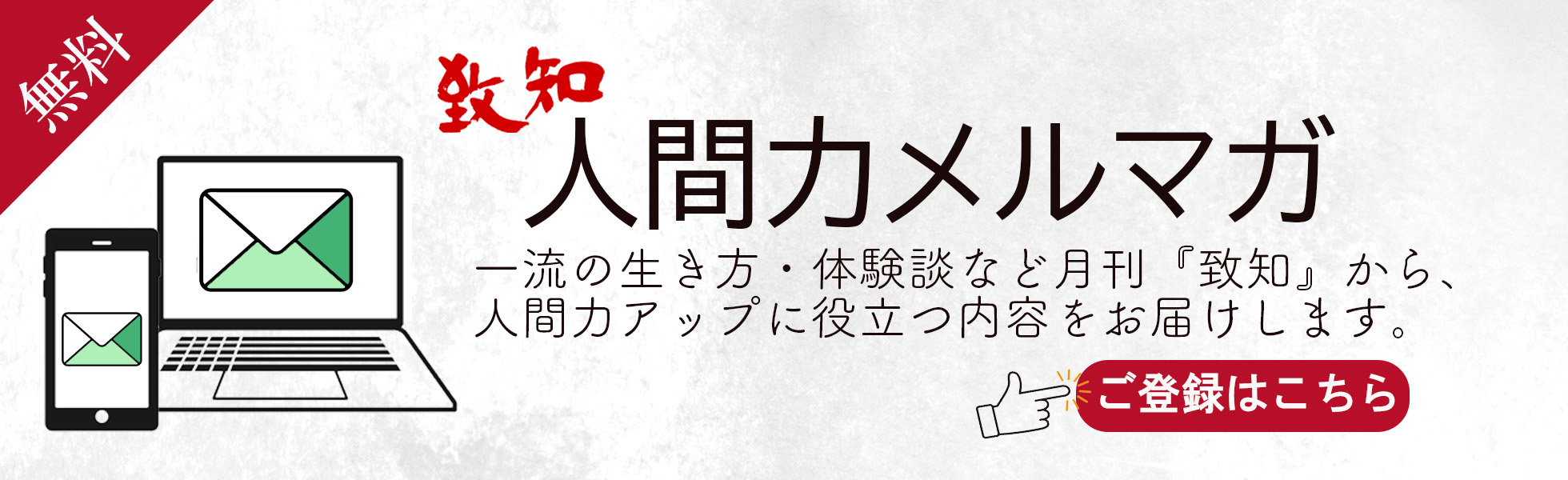2023年05月30日

現代の碩学と称された故・渡部昇一先生。弊誌『致知』でも「歴史の教訓」の連載(通算235回)や計66点もの書籍の刊行、20年以上に及ぶ連続講座でのご講話など、多くの教えをいただきました。その渡部先生に、真珠湾攻撃から私たちが学ぶべきことを紐解いていただきました。
◎各界一流の方々の珠玉の体験談を多数掲載、定期購読者数NO.1(約11万8000人)の総合月刊誌『致知』。あなたの人間力を高める、学び続ける習慣をお届けします。 たった3分で手続き完了、1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。
※購読動機は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください
バレンツ海海戦と巡洋艦ベルファースト
ある財団の関係でロンドンに行ってきた。
スケジュールの合間にはイギリス側の財団の接待で、テムズ河をグリニッジまで下って戻ってくるというクルージングをやった。船から眺めるテムズ河畔は、むかしは倉庫街だったが、いまは高級なマンションが立ち並んでいる。
その景観を楽しみながらテムズ河を下っていくと、大分下流に来た河の真ん中に一隻の軍艦が係留されていた。船腹の艦名は「ベルファースト」と読める。
「あの船は何ですか」と聞くと、先方の財団の人たちが立ちどころに巡洋艦ベルファーストの説明をしてくれた。彼らは元ブリティッシュ・カウンシルの所長、元駐日大使、それに財団の会計責任者といった顔ぶれである。
軍人ではないし、特に軍事に詳しいという人たちでもないと思う。それが微に入り細にわたって巡洋艦ベルファーストとその戦いについて説明するのである。
私にも多少はその知識があったので、大いに話が弾んだ。あまり知られていないことだが、第二次大戦中、アメリカはイギリス経由でソ連に軍事物資を補給し続けた。イギリスの輸送船団がアメリカからの軍事物資を積み、ノルウェーの北をまわり北極海を通ってソ連に送り込むのである。
もちろん、ドイツは阻止しようとする。ノルウェー北方のバレンツ海がその主戦場になった。1943年の12月末近く、軍事物資を満載したイギリスの輸送船団が1隻の戦艦と数隻の駆逐艦に護衛され、ソ連に向かった。一方、ドイツ海軍は巡洋戦艦シャルンホルストと駆逐艦5隻がバレンツ海で待ち受けていた。
ところがその日は大変な嵐だった。そのためにドイツの駆逐艦5隻は早々とバレンツ海を離れた。だが、巡洋戦艦シャルンホルストは停まっている。
船速の遅い輸送船団を一隻の戦艦を中心にした護衛艦隊で護るのは断然不利である。
にもかかわらず、イギリスの護衛艦隊は敢然と巡洋戦艦シャルンホルストに挑んでいった。そして、嵐の中を衝いて、5発の魚雷をシャルンホルストに命中させ、ついに撃沈してしまったのである。
このバレンツ海海戦を戦った巡洋艦がベルファーストなのである。その功績を讃えて退役後もテムズ河の真ん中に係留してあるというわけである。
それにしても、軍人でも軍事専門家でもないイギリス側の財団の人たちが、ベルファーストとシャルンホルストの性能や装備、それぞれの指揮官の軍歴や人柄、戦法と戦闘の経緯など、実に詳しいのには驚かされた。
これがイギリスの知識人というものかと改めて感じ入ったことである。
欧米では軍事知識はインテリの必須条件
欧米では軍事知識があることがインテリの条件なのである。少なくとも軍事知識がない人間は指導層には入れないというのが常識になっている。私が客員教授で初めてアメリカの大学に行ったときだった。教授室から眺めると、軍服を着た学生たちが盛んに軍事教練をやっている。それもかなりのハードさである。
その大学はごく普通の名門大学で、軍人の学校ではない。なのに、なぜ軍事教練をやっているのかと思ったら、それはROTC(ロトシー)という大学教育の中に組み込まれた制度で、その単位を取ると予備士官になれるのだという。
日本では軍事教練などと言えばたちまち拒否反応が起こるが、向こうは制度に組み込まれて、誰もが何の違和感もなしに受け止めている。そういう空気も軍事知識がインテリの必須条件であることとはつながっているのだろう。
バレンツ海海戦と巡洋艦ベルファーストについて滔々と語るイギリス側の人たちを見ていて、彼我の軍事についての感覚の違いを考えないわけにはいかなかった。
同時に、彼らの話を聞きながら、少なくとも50年前までのイギリスにはネルソン精神が生きていたのだな、ということも思った。ネルソンとは言うまでもなく、世界の7つの海に覇を唱えたイギリス海軍の代表的英雄、ネルソン提督である。
ネルソンの戦歴は壮絶で輝かしい。ナポレオン全盛の1798年、ネルソン率いるイギリス艦隊は地中海のアブキール湾でフランス艦隊に大打撃を与えた。1805年にはトラファルガーの海戦でフランス・スペイン連合艦隊を撃滅した。これらの戦いでネルソンはすべて陣頭に立ち、隻数で不利だろうと、火力で劣ろうと、とにかく攻撃に次ぐ攻撃で敵を撃破するという戦い方をした。
そのために彼は右目を失い、片腕を切断し、ついにトラファルガーの海戦では勝利が確かになった瞬間に敵弾を浴び、戦死したのである。ネルソン精神とは、どんな状況下でも全力を尽くして攻撃し、徹底的に相手をやっつけるまでやめない戦い方にほかならない。
徹底的にやっつけるまで攻撃をやめない
戦後、私はずうっと気になっていたことがあった。大東亜戦争での日本海軍の戦い方がどうにも腑に落ちなかったのである。そこで紹介者と共に源田実さんのお宅に訪ねていくつかの疑問点を質問したことがある。
源田実さんは大東亜戦争の口火となったハワイの真珠湾攻撃で機動隊の航空参謀を務め、戦後は参議院議員をなさった人である。いろいろお聞きしたあとで締め括りに、私は「日本はなぜ負けたのか」と質問をした。その答えが印象的だった。源田さんはこう言われたのである。
「ネルソン精神を忘れたからだよ。それに尽きる」
ネルソン精神。久しぶりに聞く言葉だった。源田さんはネルソン精神について、こんな話をされた。ネルソン提督のころは、大砲を撃つとものすごく煙が出たそうである。海戦で撃ち合いになると艦が煙に包まれてしまって、何が何だか周囲の状況がわからない状態になる。
すると、この戦い方でいいのかどうか、艦長に迷いが生じる。だが、ネルソンはきっぱりと言った。
「とにかく敵を見て撃ち続けろ。そうする限り、その判断は正しいと私は評価する」
だから、イギリス海軍は躊躇することなく、敵を見つけて撃ちに撃つ戦い方に徹した。見敵必殺である。
ネルソン率いるイギリス艦隊がナポレオンの勢力下にあったコペンハーゲンを攻撃したことがあった。コペンハーゲンは砲台を構えている。ネルソンはその前面で艦隊に錨を下ろさせた。砲台は弾丸が当たっても沈まないが、船は沈む。なのに砲台の前面に投錨するのは、無茶といえば無茶である。だが、ネルソンは決然と命令した。
「敵の砲台を沈黙させるのが早いか、こちらが沈むのが早いか、どちらかしかない、撃て」
そして、ついに砲台を沈黙させてしまったのである。これがネルソン精神である。ドイツの駆逐艦が全部離脱してしまうような大嵐のバレンツ海で、イギリスの巡洋艦ベルファーストは敵の巡洋戦艦シャルンホルスト目掛けて突っ込み、果敢に攻撃して撃沈してしまった。まさにネルソン精神の発露だったのである。
第二次大戦でもネルソン精神は大いに発揮された。こんなふうである。
氷河にえぐられて奥深い入江をつくるフィヨルドは、ノルウェー独特の地形である。ドイツはノルウェーを占領すると、フィヨルドに駆逐艦を隠し置き、北極海を通過する艦船を攻撃した。もちろん、イギリス海軍も座視していない。フィヨルドに突っ込んで攻撃した。しかし、なかなか撃滅することができない。すると、次にイギリスは戦艦を突っ込ませたのである。狭いフィヨルドでは大きな戦艦は旋回することができない。攻撃されれば回避するのは難しい。それでも敢えて戦艦を突っ込ませた。やはり戦艦は被害を被った。
だが、それによってそこにいたドイツの駆逐艦の全部を撃滅してしまったのだ。当時の最新鋭戦艦ビスマルクは、ドイツ海軍の誇りであった。そのビスマルクが巡洋艦オイゲンを従えて航行中、北海でイギリス海軍のフッドとプリンス・オブ・ウェールズに遭遇、海戦になった。フッドは戦艦大和以前では世界最大の戦艦で、プリンス・オブ・ウェールズはのちに日本によってマレー沖で撃沈されることになる新鋭戦艦である。
ビスマルクの砲撃は正確だった。フッドは轟沈、プリンス・オブ・ウェールズは大破した。もはや勝敗の帰趨は明らかである。だが、大破したプリンス・オブ・ウェールズは、まだ沈んでいない。ならば、ビスマルクは撃沈するまで追撃すべきである。
ところが、勝利に浮かれたのか、逃げるプリンス・オブ・ウェールズを追うでもなく、あたりをフラフラ周航するだけだった。これに対してイギリスは、トーベイという海軍大将が全艦艇に、ビスマルクを探し出して撃沈せよ、と命じたのである。
これに応じてアフリカ沖にあった艦艇までも、さらには空母まで馳せ参じ、ビスマルクを見つけて撃沈してしまった。持てる戦力を出し切って徹底的にやっつけるまで攻撃をやめない。これがネルソン精神なのである。
私は大東亜戦争を思い返した。なるほど源田さんの言うように、日本はネルソン精神を忘れていたな、と思ったことだった。
(本記事は弊社刊『渡部昇一の時流を読む知恵』〈渡部昇一・著〉から一部抜粋・編集したものです)
【◎渡部昇一氏からの『致知』へのメッセージ◎】
「私は一人のリーダーを待望するよりも、むしろ意識ある日本人の総合力こそが日本を変革していく原動力になっていくと思います。
それを牽けん引いんする一つの媒体が他ならぬ『致知』だと思っています。
この月刊誌の読者が増えることは、日本をよくすることに確実に繋がっていくでしょう。
『致知』の購読者が二十万人、三十万人と増え、代表的国民雑誌として定着することを期待してやまない理由もそこにあります」

生前、蔵書の並ぶ書棚の前にて
◇渡部昇一(わたなべ・しょういち)
━━━━━━━━━━━━━━━━
昭和5年山形県生まれ。30年上智大学大学院西洋文化研究科修士課程修了。ドイツ・ミュンスター大学、イギリス・オックスフォード大学留学。平成13年より現職。著書多数。著書に『渡部昇一の少年日本史』(致知出版社)など多数。
◎各界一流の方々の珠玉の体験談を多数掲載、定期購読者数NO.1(約11万8000人)の総合月刊誌『致知』。あなたの人間力を高める、学び続ける習慣をお届けします。 たった3分で手続き完了、1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。
※購読動機は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください