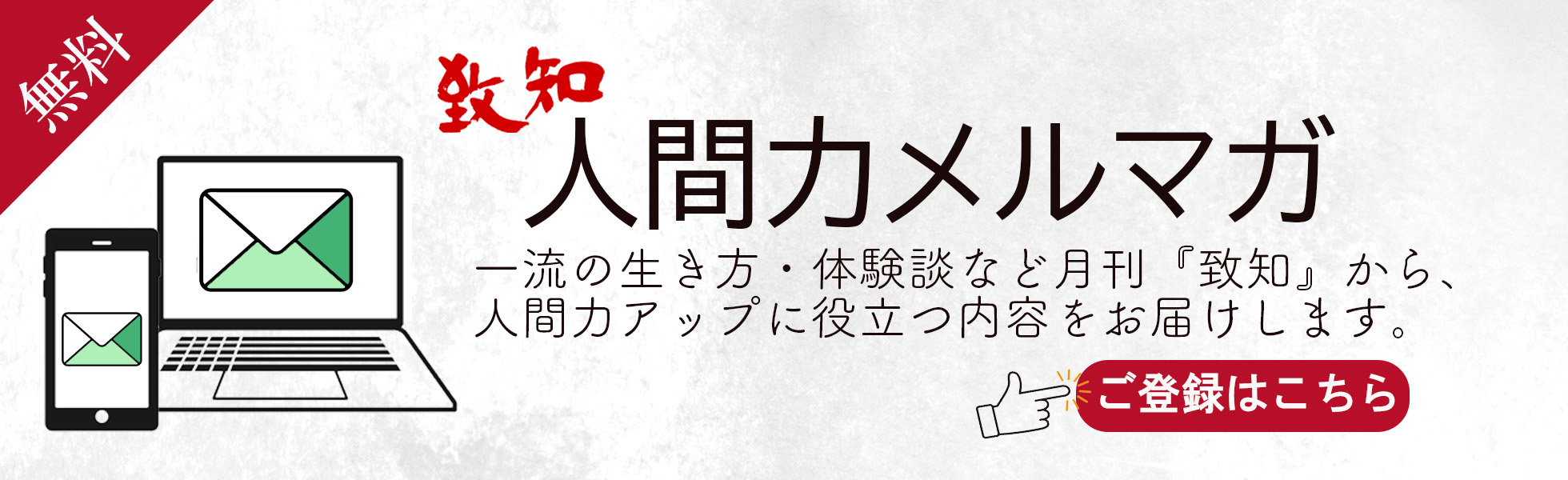2023年05月13日
 これまでに約1500本もの洋画で字幕を担当してきた、押しも押されもせぬ字幕翻訳者の戸田奈津子さん。しかし意外にも、出世作となった『地獄の黙示録』を手掛けたのは43歳の時だったといいます。85歳のいまなお字幕翻訳の道ひと筋に歩み続ける戸田さんに、苦しい下積み時代と、人生の転機をお話しいただきました。
これまでに約1500本もの洋画で字幕を担当してきた、押しも押されもせぬ字幕翻訳者の戸田奈津子さん。しかし意外にも、出世作となった『地獄の黙示録』を手掛けたのは43歳の時だったといいます。85歳のいまなお字幕翻訳の道ひと筋に歩み続ける戸田さんに、苦しい下積み時代と、人生の転機をお話しいただきました。
〔撮影=本間 寛〕
◎各界一流の方々の珠玉の体験談を多数掲載、定期購読者数NO.1(約11万8000人)の総合月刊誌『致知』。あなたの人間力を高める、学び続ける習慣をお届けします。 たった3分で手続き完了、1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。
※購読動機は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください
翻訳に関することなら何でもやった
――字幕の存在を意識し始められたのは、いつ頃ですか。
〈戸田〉
『第三の男』にシビれまくっていた高校生の頃です。最初は主役のジョセフ・コットンが目当てだったのが、何度も観るうちに映画そのものの魅力に取り憑かれてしまいました。
そのうちに少しは字幕の台詞も覚えるようになります。「今夜の酒は荒れそうだ」という台詞があって、女性だけの環境で育った私には、この男っぽい台詞が実に格好よく聞こえたものです。原文は「I shouldn’t drink it. It makes me acid.」で、直訳すれば「これ(酒)を飲んではいけない。これは私を不機嫌にするから」なのですが、それを「今夜の酒は荒れそうだ」と訳すセンスに感動しました。
このことを通して字幕とは直訳するのではなく、台詞のエッセンスを上手に日本語に置き換えるということが分かってきたんです。
――それで字幕翻訳者を志された。
〈戸田〉
大学3年生で就職を決める時には「字幕の翻訳をやりたい」と思うようになっていましたね。当時、英文科の学生に一番の人気は客室乗務員で、教員や公務員になる学生も多くいましたけど、私は全然魅力を感じませんでした。
字幕翻訳という職業があるなんて、その頃は誰も知りません。字幕翻訳の仕事がしたいと思っている私ですら、どこでどういう仕組みで字幕ができているのか、どこにアプローチしたらいいのかなど全く分かりませんでした。コネなんか、もちろんありませんしね。
――で、どうされたのですか。
〈戸田〉
映画の最後に映し出される「日本語字幕 清水俊二」という名前を頼りに、清水先生に手紙を書くことにしました。電話帳で先生の住所を見つけて思いの丈をしたためたところ、数週間後、お返事が届いて「映倫の事務所においでなさい」と。そりゃあ嬉しかったですよ。結果的に「この仕事に就くのは難しい」というお話で、まぁがっかりはしましたけど、「ここで諦めはしないぞ」という気持ちだけはしっかり持って帰りました。
ちょうど大学の教務課から「第一生命保険の社長秘書にならないか」と連絡があり、パン代を稼ぐつもりで就職を決めましたが、1年半で辞めました。もともと会社勤めは性格に合っていませんでしたから。それからは、いまでいうフリーターですよ。通信社の原稿を書いたり、化粧品会社の資料を英訳したり、翻訳に関することなら何でもやりました。
――そういう中でも、字幕翻訳者になる夢は諦めなかった。
〈戸田〉
ええ。清水先生には暑中見舞いや年賀状にかこつけて「字幕への夢は諦めていません」とさりげなくアピールしていました。先生もそんな私のことを気に留めてくださったのか、『鉄腕アトム』など輸出用のシナリオを英訳する仕事をくださいました。
映画の字幕は1秒間に3、4文字、1行に10文字を2行まで、と字幕のイロハを教えてくださったり、「試しにやってごらん」と渡された翻訳を褒めてもらったのもその頃です。
ただ、字幕翻訳の世界に師弟制度はありませんから、自分の道は自分で拓くしかない。アルバイトを続けながら、ようやく洋画界への道が拓けたのは大学を出て10年後でしたね。配給会社から洋画のあらすじを伝えるシノプシスの仕事を依頼されるようになったのですが、本格的に字幕を手掛けるのは、さらにその10年後でした。
運命を変えたコッポラ監督のひと言
――下積みの時代が20年間続いたのですね。
〈戸田〉
シノプシスの仕事をするようになってからも、翻訳や馴れない通訳の仕事を請け負ったり、いろいろな仕事をしてきましたが、本当にやりたい字幕の仕事にはなかなかありつけませんでした。
字幕のデビュー作は、小さなドキュメンタリー作品を別にすれば、1970年公開の『野性の少年』という映画です。だけど、まだ一人前として認められたわけではなく、字幕の仕事は年に1、2本で、鳴かず飛ばずの状態が何年も続きました。
――辞めようとは、思われませんでしたか。
〈戸田〉
辞めようと思ったことは一度もないですね。他に魅力ある仕事は何も見つからなかったし、自分にはこの道しかないと思っていました。人間の感情の中で「好き」という感情ほど強いものはありません。
その頃、日本は高度成長期でしたから割合景気もよくて、どんなに食べられなくてもホームレスになれば生きていけるという思いはどこかにありました。底辺をいつも見ていたように思います。
20年間の下積みといっても私自身はそんなに苦労したとは思っていません。他の人だったら20年間も仕事がなかったら、どん底まで落ち込むことがあるかもしれない。たまたま私はそういう心の持ち方、考え方をしなかったということです。
――本格的に字幕を手掛けられるようになったのは、フランシス・コッポラ監督の『地獄の黙示録』(1980年)からですね。
〈戸田〉
ええ。私がコッポラ監督と最初に会ったのは、その4年前で、彼は『地獄の黙示録』の撮影のためにロケ地のフィリピンを往復する途中、よく日本に立ち寄っていました。私が頼まれたのはそのガイド兼通訳で、フィリピンの撮影現場を訪ねた幸運もありました。映画が完成すると、コッポラ監督は無名の私を字幕翻訳者に推薦してくれたんです。
――人生の転機となる出来事でしたね。
〈戸田〉
彼は私が映画好きということをよく知っていましたし、自分では覚えていませんが、何かの会話の中で「字幕の仕事をしたい」と言っていたのでしょうね。ご存じのようにこの映画は世界的に大ヒットしましたから、私も字幕の業界から暗黙のお墨付きをいただくことができたわけです。
(本記事は月刊『致知』2021年9月号 特集「言葉は力」より一部抜粋・編集したものです)
◉『致知』2021年9月号では「言葉」をテーマに、戸田奈津子さんへロングインタビュー! ご活動の原点から字幕翻訳の神髄、日本語の問題まで縦横に語っていただきました!!