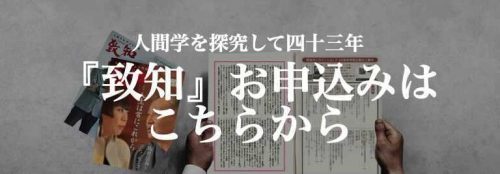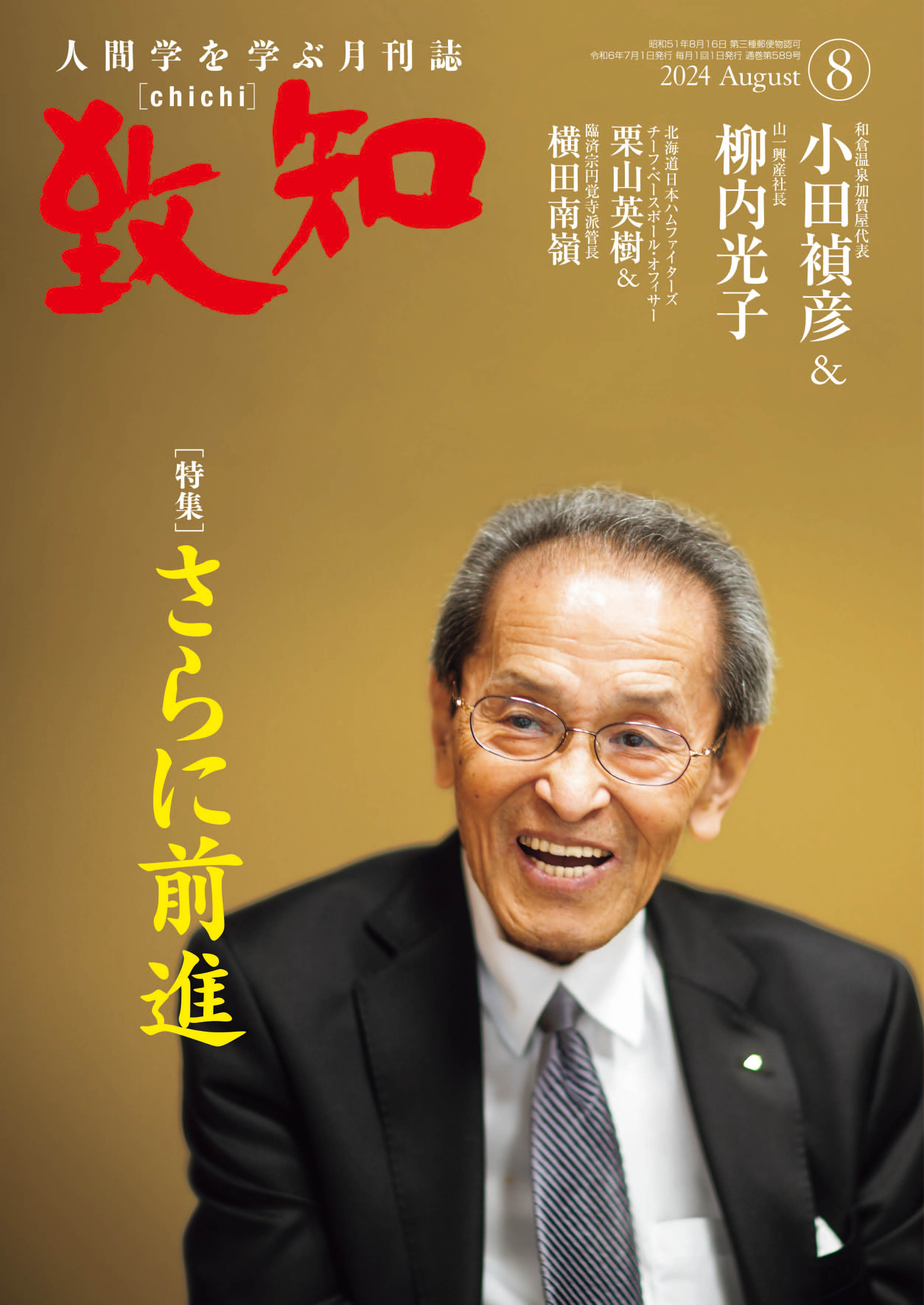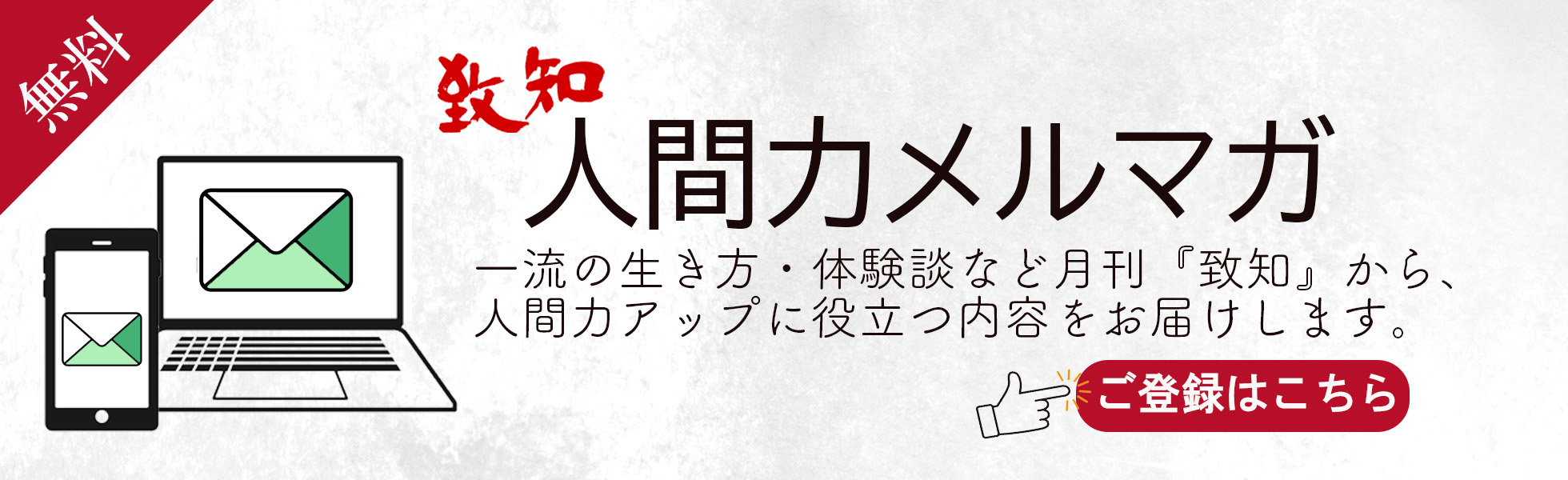2021年09月07日

左が竹村氏、右が安岡氏
中国古典の教えを分かりやすく人々に紐解いてきた易経研究家の竹村亜希子さんと、論語教室の第一人者で昭和の碩学・安岡正篤師のご令孫である安岡定子さん。自らの人生・仕事に古典を生かしてきたお二人に、先人たちの英知が詰まった古典を読み解く〝コツ〟とその魅力を語り合っていただきました。
◎各界一流の方々の珠玉の体験談を多数掲載、定期購読者数NO.1(約11万8000人)の総合月刊誌『致知』。あなたの人間力を高める、学び続ける習慣をお届けします。 たった3分で手続き完了、1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。
※購読動機は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください
体験に引き寄せて古典を読む
〈安岡〉
竹村先生は、講座でいつもどのようなことを心掛けていらっしゃいますか。
〈竹村〉
いくつかあるんですけど、『易経』は古典の中でも一番古く、難解とされていますから、年配の方のほとんどは一度、挫折してから来られるんです。
孔子が「50歳になったら易を勉強したほうがいい」と言っていることもあって興味を持つ方も少なくないのですが、『易経』はめんどうな約束事がやたらと多いですから、一頁(ページ)目から順に読もうとすると必ず嫌になります。だから私は「分からないことを楽しんでください。覚えようとしないでください」と言っています。
〈安岡〉
まずは拒否反応をクリアするところから始められるのですね。
〈竹村〉
そして『易経』はすべて、原理原則を喩え話として書かれた物語、ドラマであること。その喩え話を自分の身近なことに引き寄せて想像してもらいます。
自分の過去にあったことに結びつける。それが思いつかなければ世の中で起きている出来事や、家族のことなどに引き寄せながら想像を膨らませていく。これが『易経』を読む一番のコツです。
その上で2、3人のグループをつくって10分ほど分かち合う。自分とは違う考え、別の見方があることを知って思い込みが外れ、世界が広がっていきます。
その講座の中で一つでも腑に落ちることがあればそれが出発点になります。腑に落ちたら必ず『易経』の地下水脈まで行きますし、そうなったらこっちのものですね。
また『易経』は、変化の法則の根拠を自然においているから、観る力を養えば、すべて自然が教えてくれるとも話しています。
もう一つ、これは『易経』に限りませんが、人生や仕事の答えは古典の中にあるのではなく、古典の教えを自分のものにした時に得られるというのが私の考えです。大切なのは「化す」こと、化学反応を起こして自分のものにして実践することです。座学ではないのです。化学反応が起こせるのはその人自身なのですから、私はできるだけ教えるのでなく、伝わるようにを心掛けているんです。
〈安岡〉
それはとても大切なことですね。私の場合は伝えるというよりもむしろ一緒に楽しむという気持ちが強いように思います。自分の思いや知識をどう伝えるかは相手によって違いますが、私は自分が持っているものはすべて出し尽くしたいと思っているんです。知識や教養はいくら出し尽くしても枯渇するものではありませんし、出し惜しみしてはいけないですね。相手にとって、どうしたらそれが100%納得してもらえるものになるかは常に考えていますね。
〈竹村〉
『易経』の「山水蒙」(さんすいもう)という教育の基本姿勢を説いている卦があります。山がもともとあるのだけれど、霧で消されて見えない、墨画や山水画の世界の喩えです。その霧が晴れればもともとあるものが見えてくると。
また「我より童蒙(どうもう)に求むるにあらず。童蒙より我に求む」とあって、先生のほうから教えようとしてもそれは学びにはならない、生徒が「教えてほしい、学びたい」という気持ちが起きた時に初めて学びになる。先生はそのお手伝いをするだけだと。生徒が知的好奇心を起こして学べば、生徒本来の力が引き出され、自分で考えるようになるといいます。
教える側として、そこはとても留意する部分ですね。
人生を変えた大事故
〈安岡〉
私は最近、「古典は自分が帰る場所である」という祖父の言葉をしみじみと実感することが多くなりました。古典から何を最も教わったかと聞かれたら、まずそう答えるでしょう。
しかし、若いお母様方や学生さんたちにとってどうかといえば、それはなかなか難しいところですね。苦難を避けたい、幸せな人生でありたいなど『論語』に求められるものは様々ですけど、一つ言えるのは、どう考えても苦難を取り除くことなどできないのが人生だということです。孔子ほどの人物でも長い不遇の時代があり、辛い思いもたくさん経験しているわけですから。
祖父は「万象の悩みの答えが『論語』にはある」と言っていますが、何事か起きた時に乗り越えることができる、どん底にある時に取り乱すことなく、じんわりじんわりと心が癒やされて立ち直ることができる、その力を与えてくれるのが古典なのだと思うんです。
祖父は「人間、そんなに差なんかありゃせんわ」とよく言っていました。一人ひとりの能力に大きな差がないとしたら、困難にぶつかった時に、一緒に乗り越えていく仲間がいる、喜びや感動を分かち合える人がいるというのもとても大事な要素かもしれませんね。
〈竹村〉
私は古典を学ぶ楽しみは、自分の思い込みが外れて楽になり、自由な世界観が広がるところにあると思っているんです。
『易経』を学んだ方の中には「怖いことがなくなった」とおっしゃる方が少なくありません。当然、生きていると怖い現象は何度も起きてくるわけですが、「『易経』には時中(じちゅう)という、その時にピッタリのことをすれば物事は亨(とお)る、という解決策が具体的に書かれている」「不遇な冬の時代は避けるべきものではなく、春を迎えるための準備期間」と前向きに捉えることができるようになるんですね。
それを『易経』では「冬の大地に習いなさい」という言い方をしています。また来る春に備えて豊かな土壌づくりをしなさいと。そう発想を転換すると、「楽天知命」という『易経』の言葉の通りの不思議な安心感が生まれるのではないかと思います。
私自身も、過去にあった辛い出来事をあれこれ思い出して悶々としていた時、「あっ、違うんだ。あれは本当はこういう意味があったんだ」と気づいて思い込みから解かれ、心が軽くなった経験があります。世界が広がり自由になる感覚をこの時、覚えたんですね。
(本記事は月刊『致知』2018年12月号 特集「古典力入門」より一部を抜粋したものです)
★2018年12月号「古典力入門」では竹村さんと安岡さんに中国古典の魅力、人生・仕事への生かし方を分かりやすく語り合っていただいています。これから古典を勉強してみたい方、また、もっと深く学びたい方にぜひ読んでいただきたい珠玉の対談です★