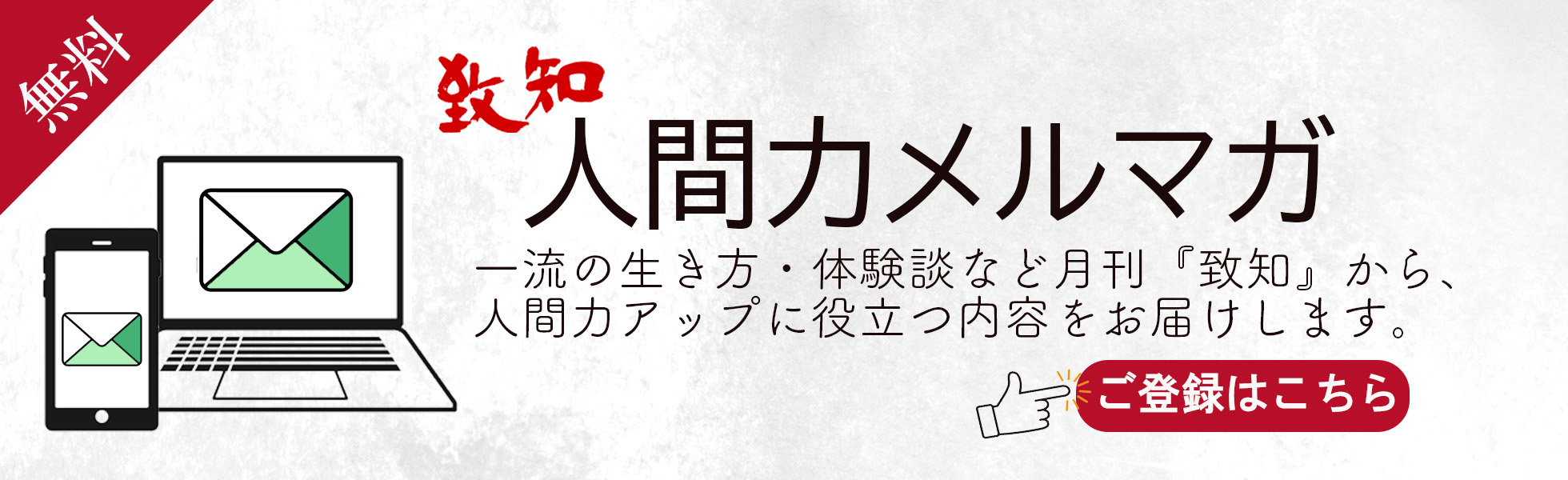逸話に見る森信三師 独居自炊の生活へ
歴史的評価を受ける反面、先生は人生悲愁の極みともいえる苦難を味わわねばなりませんでした。 それは長男惟彦氏(四十一歳)の急逝でした。 事業(不動産業)の蹉跌によるものでした。 七十七歳という高齢の身で、突如として多年生活を共にした子息を喪われたのですからその悲しみは言語に絶するもので、悲歎のどん底につきおとされた思いでした。
やっと書き記された『逝きしわが子を偲びて』の一文には万斛(ばんこく)の想いが込められ、痛恨哀切の一語に尽きます。
「彼は親らしからぬわたくしに代わって、次男と三男を成人させたのと、厖大なわたくしの著書を出すために、この二度とない人生の半ばまで、生活の全精魂を傾け尽くしてこの世を去ったともいえるわけで、現在わたくしが痛恨身の置き処のない思いをしているのも、全くその故である。(中略) 憐れなりしわが子よ!! 今や永遠なる安らぎの彼岸より、この哀われなる父のかすかな贖罪の微衷を、はるかに見守ってほしいのである。嗚呼」
至らなかった親としてわが子への罪ほろぼしとして、先生は単身、未解放部落の立ち退き寸前の家屋へ入居されることになりました。
(寺田一清編著『森信三小伝』より)