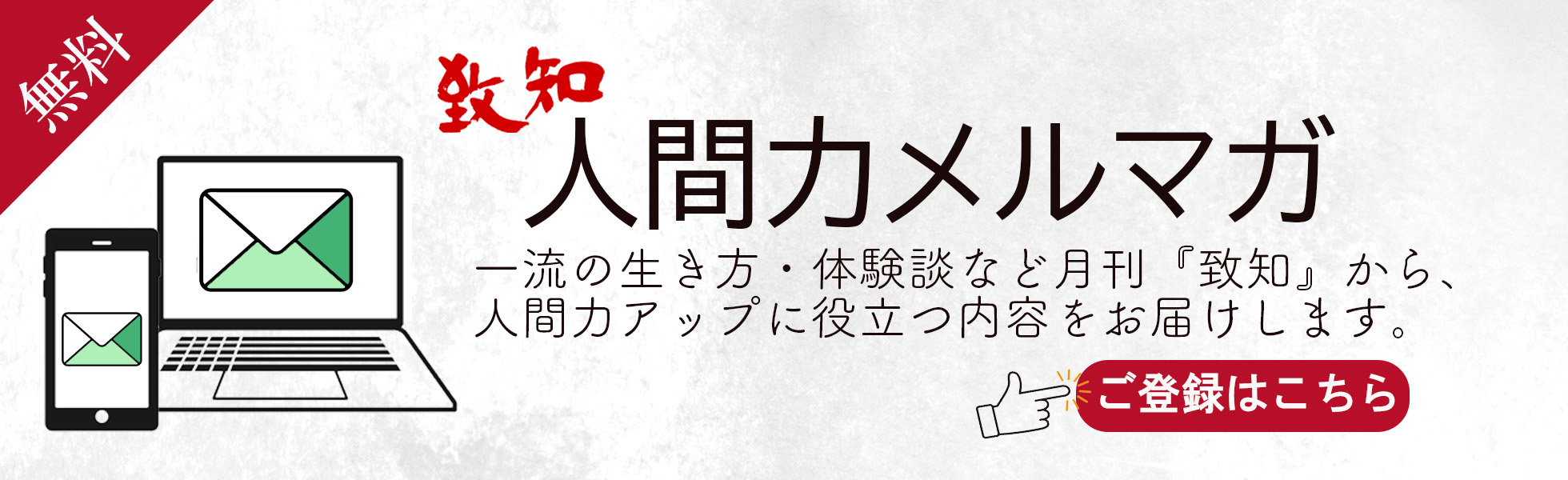逸話に見る森信三師 二宮翁夜話で開眼
昭和三年の九月のことで、すでに先生は三十三歳、大学院生の頃です。 天王寺師範の専攻科一回生の教え子として道縁の深かった山本正雄氏から、その年の夏休みに氏が尊徳翁の遺跡廻りの際に買い求めた二宮尊徳翁の『報徳記』と『二宮翁夜話』の二冊を贈呈されたのです。
その『二宮翁夜話』を開けば、その第一頁に 「それわが教えは書籍を尊まず、ゆえに天地をもって経文とす。 予が歌に〝音もなく香もなく常に天地(あめつち)は、書かざる経を繰り返しつつ〟とよめり。 かかる尊き天地の経文を外にして、書籍の上に道を求むる学者輩の論説は取らざるなり。云々」 と喝破されているではありませんか。 この一語によって先生が大学入学以来抱き続けてきた多年の迷いは濶然(かつぜん)として氷解したのでした。
それまでにも、西欧の哲学書の単なる紹介や解説だけでは真の哲学ではないとは解っていました。 しかし、アカデミズムの残滓(ざんし)が、まるで尾骶骨(びていこつ)のように付着していたのです。 それが一瞬にして霧消したのでした。
先生は尊徳翁の語録によって、生涯を貫く学問観の根本的立場を授かったのです。 これが「真理は現実の唯中にあり」という一語に表わされた学問観です。 有為転変の現実界こそ真理の宝庫であり、いかなる古典的名著といえども、真理のイメージを示す栞(しおり)というか手引書にすぎないことを確認したのです。
(寺田一清編著『森信三小伝』より)