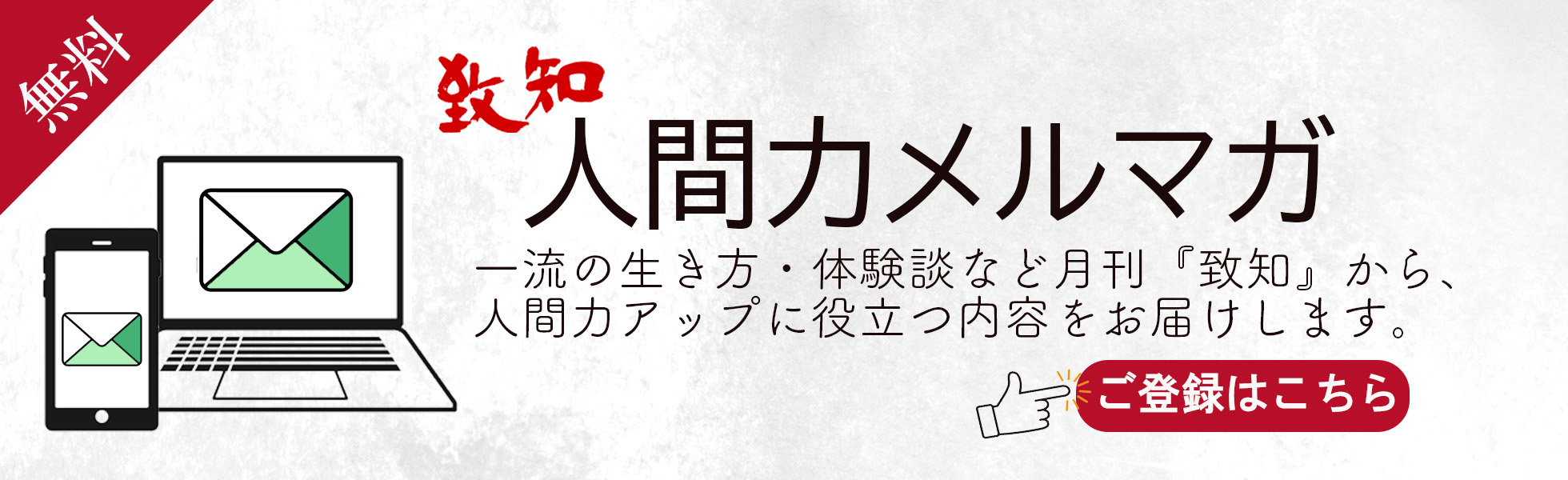2024年05月26日

日本人ピアニストの母とスウェーデン人の父との間に生まれ、リストの難曲「ラ・カンパネラ」の演奏などで社会現象を巻き起こしたピアニストのフジコ・ヘミングさんが2024年4月21日、お亡くなりになりました。92歳でした。16歳の時に中耳炎で右耳の聴力を、35歳にドイツでのリサイタル直前に左耳の聴覚を失うという困難に見舞われながらも、いかにして感性を揺さぶる演奏で「魂のピアニスト」と呼ばれるまでに至ったのでしょうか。月刊『致知』2002年6月号で語られたご自身の人生哲学をご紹介します。心よりご冥福をお祈り申し上げます。
◎各界一流の方々の珠玉の体験談を多数掲載、定期購読者数NO.1(約11万8000人)の総合月刊誌『致知』。あなたの人間力を高める、学び続ける習慣をお届けします。 たった3分で手続き完了、1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。
※購読動機は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください
バーンスタインとの出会いから帰国まで
1970年。その頃、ヘミングさんが住んでいたウィーンでバーンスタインの演奏会があった。曲目はバッハの大作『マタイ受難曲』。ヘミングさんは立見席でそれを聴いた。大きな感動だった。
たまらなくなって、ヘミングさんは楽屋を訪ねた。バーンスタインは快く会ってくれ、彼女のピアノを聴くという。温かみのある人間性に誘われて、彼女は弾いた。終わると、バーンスタインは彼女を抱きしめて言った。「君は素晴らしいピアニストだ」
バーンスタインをはじめ、マガロフ、チェルカスキー、マデルナたちの推薦で、ヘミングさんのリサイタルがウィーンで開かれることになった。ポスターが町に張り出された。
ところが、彼女は発熱で倒れてしまった。気がつくと、聞こえていた左耳の聴力も失われていた。まったく音のない世界。彼女はふらつく体で1回だけステージに立った。だが、あとのステージはキャンセルするほかはなかった。チャンスは去っていった。
「どういうわけなんでしょうね。帰国のことはチラリとも考えなかった。2年間療養して、どうにか左耳の聴力が半分ぐらい回復して、さて、これからどうして生きていこうかと思った。それで音楽教師の資格を取って、ピアノを教えて暮らしていくことにしたの。……相変わらずお金はないから、数少ない生徒にピアノを教えて、あとは猫を相手にピアノを弾く生活。毎日毎日ピアノばかり弾いていたわ」
ヘミングさんが帰国したのは1995年。その2年前に母が亡くなっていた。帰国したのは、東京・世田谷の下北沢にある母の家を人でに渡したくないためだった。
話があって、母校東京芸大の旧奏楽堂で演奏会を開いた。ヘミングさんのピアノは聴く人の胸を打ち、大評判になった。
それを伝え聞いたNHKテレビがヘミングさんの日常生活を撮影、1999年末にその生き方をドキュメンタリー番組で放映した。予想外の反響だった。演奏会依頼が殺到、CDも発売され、ヘミングさんは一気にブレイクした。
自分と一つになっているものがあるか
――これまでを振り返って、ご自分の人生をどのように思われますか。
〈ヘミング〉
運命ね、運命。そうとしか言いようがない。
――運命というと?
〈ヘミング〉
夢というと、なんだかほんわりして、ロマンチックな感じがするでしょ。だけど、もっと厳しいもの、自分と一体になったものを夢というなら、私は確かに夢を持ち続けた。神様はちゃんとそれを見ていてくださって、いま分け前を与えてくれているんだと思う。この神様の思し召し、それが運命ということよ。
――ヘミングさんにとっては自分と一体になったもの、夢とはなんですか。
〈ヘミング〉
もちろんピアノですよ。食べるものがなくて、猫の餌だけは与えて、自分は砂糖水だけを飲んで、それでもピアノはやめなかった。
誰も聴いてくれる人がいなくても、猫しか聴いてくれなくても、私はピアノを弾いて、弾いて、弾いてきた。それはピアノが私そのものだから。ピアノがなければ私はない。そういう意味では、ピアノを私に与えてくれたすべてに感謝のほかはありません。そして、私のピアノを聴いて感動してくれる人がいる。それは私がわかってもらえたことです。こんなありがたいことはありませんね。
夢を持つ、夢を追いかけるなんていうのは、夢と自分との間に距離があるでしょう。そうではなくて、自分と一つになっているものがある。そういうものがあると、運命が巡り巡って、神様は必ず配慮してくれる。そんな気がします。
逆にいうと、自分と一つになっているものがないと、運命もまたそれなりのものでしかなくなってしまう、ということじゃないのかな。そんなふうに思いますね。
――いまヘミングさんは大変なご活躍です。生活は変わりましたか。
〈ヘミング〉
本質的には変わりませんね。もっともお金の面では、いま11匹の猫と1匹の犬がいますが、その餌代に困るようなことはなくなって、ゆとりが出ました。ドイツではいつもお金の心配がついていたし、日本に帰ってからも、うちの上の階を貸しスタジオにして、そこから入るのが5~6万円。それに1回5千円でピアノを教えていたけど、これはあてにならない。月収はせいぜい7万円。それで暮らしていたんです。
それに比べると、いまはお金に困らなくなりました。そんなに私は必要がないから。困っている人のために寄付しています。
私ね、ドイツでこんな経験があるんです。あるとき、ショーウインドーですごく気に入ったセーターを見つけたの。聞けば、40マルクだという。食べるのに困っていたけど、たまにはいいかと思って、そのときは持ち合わせがなかったから、明日来るからとっておいてと頼んでお店を出たら、ジプシーの少年が寄ってきて、お金をくれと言う。その目がとても純粋に澄んでいたものだから、20マルクあげちゃった。これでは暮らしていけないと思ったけど、お店には買うと約束したんだから、仕方がない。次の日出掛けていきました。すると、前とは違う店員がいて、そのセーターは20マルクだという。ああ、私が少年に20マルクあげたのを神様が見ていて、ちゃんと配慮してくれたんだな、と思いましたね。
お金とはそういうもの。困っている人がいて、余っている人がいれば、あげる。それが巡り巡って、必ず自分に返ってくるものですよ。
――最後に、いつまでピアノを弾かれますか。
〈ヘミング〉
ピアノというのはね、最後はテクニックじゃない。人間は機械じゃないんだから、間違ったっていいじゃない。それよりも大切なのは魂で弾くことよ。ポンと鍵を叩くと、私の人格が音になって流れ出していく。私の人間性が貧しかったら、見透かされる。とても怖い。だから、ステージに上がるときはいつも足が震えます。それを乗り越えるには、よほどの体力が要る。だから、家では体操を欠かさないし、演奏会の前には20分歩きます。それから食事。私はベジタリアンで、最後に肉を食べたのは1983年だったかな。ジャガイモはいいですよ。体の中がきれいになる。
こうして万全の準備をして、私は弾く。いつまで弾けるかなんて、知りません。考えません。
何も考えずに弾く。だって、私はピアノで、ピアノは私なんだから。私にとってピアノを弾くことは生きることなんだから。
(本記事は『致知』2002年6月号 特集「夢を実現する」より一部を抜粋・編集したものです)
◇フジコ・ヘミング(Ingrid Fuzjko af. Georgii-Hemming)
ドイツ・ベルリン生まれ。日本人ピアニストの母と画家で建築家のスウェーデン人の父を持つ。5歳で日本へ移住。東京芸術大学ピアノ科卒業。NHK毎日コンクール賞入賞。ウィーンでのコンサート直前に高熱をこじらせ耳が聴こえなくなるなど、幾多の波乱を乗り越え、プロデビュー。平成11年にリリースしたアルバム『奇蹟のカンパネラ』はクラシック界において異例の売り上げを記録。情感たっぷりの独特な演奏スタイルから国際的に絶大な人気を誇り、「魂のピアニスト」と呼ばれる。