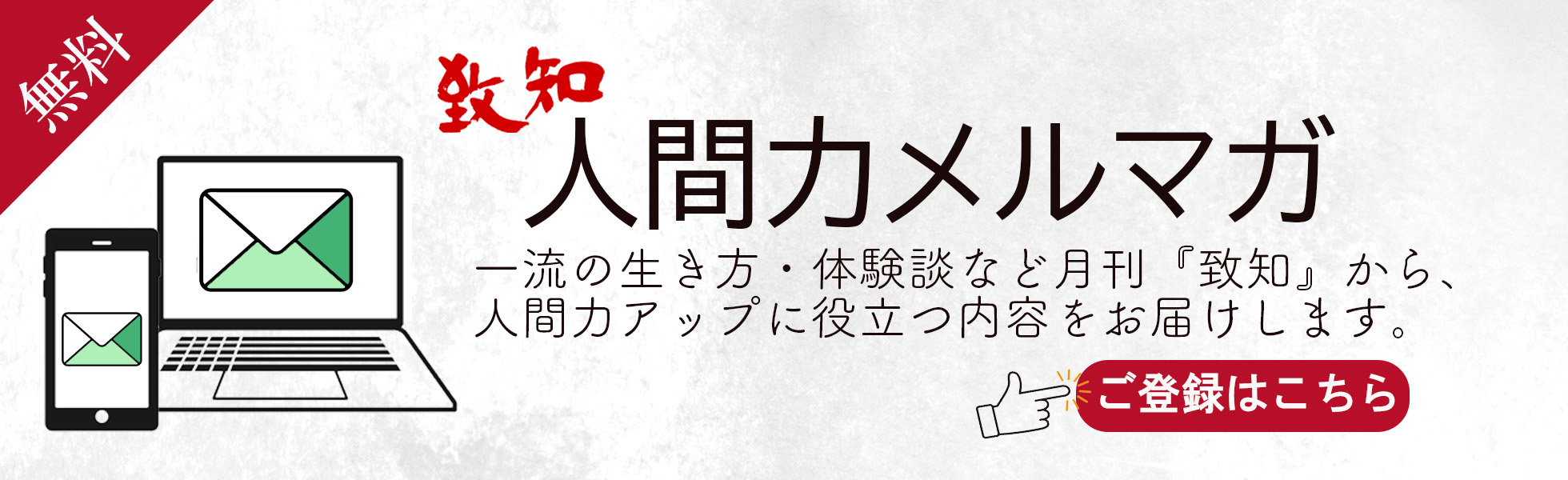2020年09月21日

20年以上に及ぶ認知症の母の介護体験から、人々の心に灯をともす珠玉の詩を生み出してきた詩人・藤川幸之助さん。その詩業は、「NHK・Eテレ・ハートネットTV」や『朝日新聞』の「天声人語」などでも取り上げられ、全国各地での講演会では、毎回涙を流す人が続出するほど感動を呼んでいます。『致知』に掲載されたインタビューから、藤川さんの詩業、詩魂の根底にあるものに迫ります。
★感動の声が続々!『自選 藤川幸之助詩集「支える側が支えられ 生かされていく』の詳細・ご購入はこちら
母は必死にいまを生きている
母が認知症になった30年前には、病気への理解がまだ進んでいませんでした。認知症の家族を人目につかないよう家から出さないという家庭もありました。でも父は、「何が恥ずかしいものか。俺が愛して愛して結婚したお母さんだぞ。病気が心臓、肺にくる人がいるようにお母さんは病気が脳にきただけだ」と、いつも母の手を固く握って散歩に出ていました。
認知症の母がどうやって散歩するかというと、がに股で歩きながら数分ごとに立ち止まり「あー、あー」と声を上げ、人とすれ違えば誰構わず触ろうとする。2人の散歩についていく時、私は恥ずかしくて仕方がありませんでした。
ある日、散歩中に小学生くらいの子供が足元の小石をぱっと拾って、「ばーか」と言いながら母に投げつけ、逃げていったことがありました。いつものことなのでしょうか、父は母に寄り添ったまま堂々と歩き続けましたが、私はかっとなってその子を追いかけようとしました。
すると父は、「病気を知らない子を叱ってはだめだ」と私をこう諭してくれたのです。
「あの子よりも問題があるのは幸之助だ。おまえはお母さんのことをいつも恥ずかしがっているだろう? がに股で歩こうが、あーっと声を上げようが、それはおまえの母親が認知症を抱えながら必死に生きている姿なんだぞ。息子のおまえにはそれが分からんのか」
認知症になっても、人間はその時その時を必死に生きている。父の言葉を思い出すと、いまでも涙が込み上げてきます。この言葉が後に母の介護に向き合うことになる私の心を支えてくれました。
また、詩人としての講演活動で各地を訪れた時に、私はお土産屋さんで売っている小さなキューピー人形を母によく買っていきました。なぜ人形を買うようになったかというと、認知症が分かった頃の母がいつも家にあったキューピー人形を抱っこし、真顔でその人形にキスをしたり、オムツを替えたりしていたからです。
当時の私には、自分は正常な世界にいて、母は異常な世界にいるのだという思いがあり、「何でそんなことをするんだ」と母を叱ってばかりいました。しかし人形を離さない母の姿を見ていると、もしかしたらあの人形は私か兄、幼くして亡くなった姉の誰かなのかもしれないとふと感じたのです。
私は「できる、できない」「分かる、分からない」で向き合っていましたが、母には「感じる、感じない」は残っていた。母の心は若い頃の自分に戻り、若い頃の世界をしっかり生きている。頭の中に広がっている世界に生きているという意味では母も私も同じ。そう思えた時、正常な世界と異常な世界という区別が消えていきました。
その体験から生まれたのが『徘徊と笑うなかれ』という詩です。
母さん、あなたの中で
あなたの世界が広がっている
あの思い出がこの今になって
あの日のあの夕日の道が
今日この足下の道になって
あなたはその思い出の中を
延々と歩いている
手をつないでいる私は
父さんですか
幼い頃の私ですか
それとも私の知らない恋人ですか
妄想と言うなかれ
母さん、あなたの中で
あなたの時間が流れている
過去と今とが混ざり合って
あの日のあの若いあなたが
今日ここに凛々しく立って
あなたはその思い出の中で
愛おしそうに人形を抱いている
抱いている人形は
兄ですか
私ですか
それとも幼くして死んだ姉ですか
徘徊と笑うなかれ
妄想と言うなかれ
あなたの心がこの今を感じている
実の母親を捨ててしまった
(藤川)
母を心から愛し、献身的に介護していた父が心臓の発作でぽっくり逝ってしまったのは、母が認知症になって9年目の1997年でした。後には父がお世話になった方々への感謝の手紙がたくさん残されていたのですが、私に宛てた遺書には、「母の介護は幸之助に任せる」と書いてありました。
母の介護は兄が担い、自分は手伝う程度でいいだろうと高を括っていましたから、いざとなると「なぜ私だけが」という思いが込み上げてきました。しかし、父が命を懸けて頼んだことだからと自分を納得させ、母の介護にしぶしぶ向き合うことにしたのでした。
とはいえ、母を長崎に連れてくるわけにもいかず、まずは熊本の施設に預け、遠距離での介護を始めました。そのことに対して、「おまえは実の母親をそんなところに入れるのか」と、周りから随分冷たい言葉を浴びせられました。
母を初めて施設に預けた日のことはいまでも忘れません。一日母と過ごして、長崎に帰ろうとしたら、母は私の後ろをずーっとついてきます。そして、施設の玄関まで来て、「また来るから、さようなら」と声を掛けると、母が私の服の裾をぐっと握ったのです。手を引き離してもまた握る、それが十数回は続いたでしょうか。認知症だから何も分かっていないと思っていた私は混乱し、「お母さんの家はここなんだ!」と声を上げ、もう涙が止まらなくなりました。
そうすると母は驚いてぱっと手を広げた。その瞬間、施設の方が母を優しく抱き締めてくれ、私はそのまま走って車まで行き、「自分は母を捨てた!」と泣きながら長崎まで帰ったのです。辛くて悲しくて仕方がありませんでした。
学校の授業中でも、「自分がこうして教員になれたのも、母が一所懸命頑張ってくれたからだ。そんな母を自分は捨てた」という思いが込み上げ、黒板の前でチョークを持ったまま涙が止まらなくなります。そんな私を支えてくれたのが子供たちでした。何の事情も知らない子供たちが涙を流している私の傍にきて、「先生、頑張らんか! 頑張らんか!」と太ももや背中をさすってくれるのです。
この時、自分は子供たちを教えていたと思っていたけれど、実は教えられ、助けられていたのはこの私のほうだったとやっと分かりました。知らず知らずのうちに多くの人たちに助けられ、支えられて生きているのが人間なのです。
母が私を通じて詩を書いている
(藤川)
当時は土曜日の午前中まで学校の授業がありましたから、土曜日の授業を終え、午後2時頃に長崎を出発。7時頃に施設に着き、親戚の家などで母との時間を過ごして翌日にまた長崎まで戻る。そうした介護の日々が続きました。
土日が介護で潰れるため仕事がどんどん溜まってくる。母の認知症が進むにつれて、徘徊したり、排泄物を撒き散らしたり、わけの分からない言葉や行動も増えてくる。オムツ代や施設費で月に何十万円も消えていく――こんな状況ではもう詩は書けない。詩を捨てて、いま目の前にいる母と精いっぱい向き合うしかないのかと絶望しました。母が死んでしまえばいいと考えたこともありました。
ところが、いままで生業にしたいと思っていた詩を掌を開いて手放し、認知症の母と向き合うことに精いっぱいになってみると、不思議と母との関係性から解き放たれていく自分を感じました。オムツを替え、排泄物を拭き、垂れてくる涎の臭いにうんざりし、わけの分からない話にずっと付き合い、徘徊すれば泣きながら探す、そうした母との時間から自ずと生まれてくる詩があったのです。母から離れ、一人になると、書こうと思わずとも自ずと詩が生まれてくる。母が私を通じて詩を書いているのではないかとさえ感じました。
母を放り出して詩を握り締めたままだったら、いまほど多くの詩は書けなかったでしょう。母の介護という体験は、手枷足枷ではなく、母から私への「問い」ではなかったか。その問いに私なりに答えを出すことによって、自分の詩人としての行くべき道が明らかになっていったように思うのです。
(本記事は月刊『致知』2019年11月号「語らざれば愁なきに似たり」から一部抜粋・編集したものです。『致知』には人間力・仕事力を高める記事が満載! 詳しくはこちら)
◇藤川幸之助(ふじかわ・こうのすけ)

昭和37年熊本県生まれ。小学校の教師を経て、詩作・文筆活動に入る。認知症の母親に寄り添いながら命や認知症を題材にした作品をつくり続ける。また、認知症への理解を深めるため全国での講演活動にも取り組んでいる。『満月の夜、母を施設に置いて』『徘徊と笑うなかれ』(共に中央法規)、『マザー』『ライスカレーと母と海』(共にポプラ社)、『支える側が支えられ 生かされていく』(致知出版社)『赤ちゃん キューちゃん (絵本こどもに伝える認知症) 』(クリエイツかもがわ)など著書多数。