『致知』に寄せられたお客様の声
『致知』を読んでのうれしいお便りがたくさん届いています。 ご感想の一部を紹介いたします。
-

生きるとは、「周りの人の幸せをつくること」と気づくことができた
茨城県 農業 鈴木美香さん(26歳)『致知』との出逢いによって私は2度人生を見つめ直すことができました。
1度目は、先輩に紹介していただき初めて『致知』を知った大学4年生の時。就職活動中だった私は、自分が楽しく仕事ができそうな会社ばかり面接を受けていました。しかし『致知』に登場される方々は自分本位ではなく、ともに働く社員はもちろん、その家族、お客様、ひいては自分が生まれた国のためという意識をお持ちです。それまで自分のことにしか目がいかなかった私にとって衝撃でした。同時に、いまの自分がいるのは両親や周りの方のおかげであることにも気づかせてもらい、感謝の念を持つことができました。社会人となったら周りの人のために生きよう。そう心新たにさせられ、その後の就職活動においても信念を持って臨むことができ、素晴らしい会社に出逢えたのは、自分を見つめ直すきっかけをくれた『致知』のおかげと思っています。
2度目は結婚を機に仕事を辞めてからです。東京から茨城に移り、旦那の家業である苺農家を手伝うことになりました。東京では志高い仲間とともに勉強会などに参加する日々でしたが、家事や仕事で足を運ぶことができなくなり、目の前の仕事に淡々と打ち込む毎日が続きました。以前は常にバッグに入れていた『致知』も読む機会が減り、未開封のまま本棚にしまわれていきました。そんな時期が数か月続いたある日、ふと本棚を見ると目に入ったのは、致知出版社から出ている鍵山秀三郎先生の『凡事徹底』の本でした。「凡事徹底」とは「当たり前のことを人ができないくらい一所懸命にやる」という意味です。
いま私は「生きる」という当たり前であり、一番大切なことが雑になっていないかと考えさせられました。生きるとは何か、そのヒントをもらうべくすぐに読まずにためていた『致知』を開きました。 再度『致知』と出逢い、多くの言葉のシャワーを浴びて、改めて生きることを深く考えさせられました。いま私にとって生きるとは、自分のいる環境において周りの人の幸せをつくることです。そのために何ができるか考え、少しずつですが邁進している次第です。 『致知』を読み始めて早5年。人生の転機にはいつも『致知』がありました。これからも『致知』とともに人生を歩み、仕事や家庭において一隅を照らす人となれるよう精進していきたいと思います。 いま、『致知』の輪は国内のみならず国外へと大きく広がっています。 それは確実に、それぞれの地域に根を下ろしています。
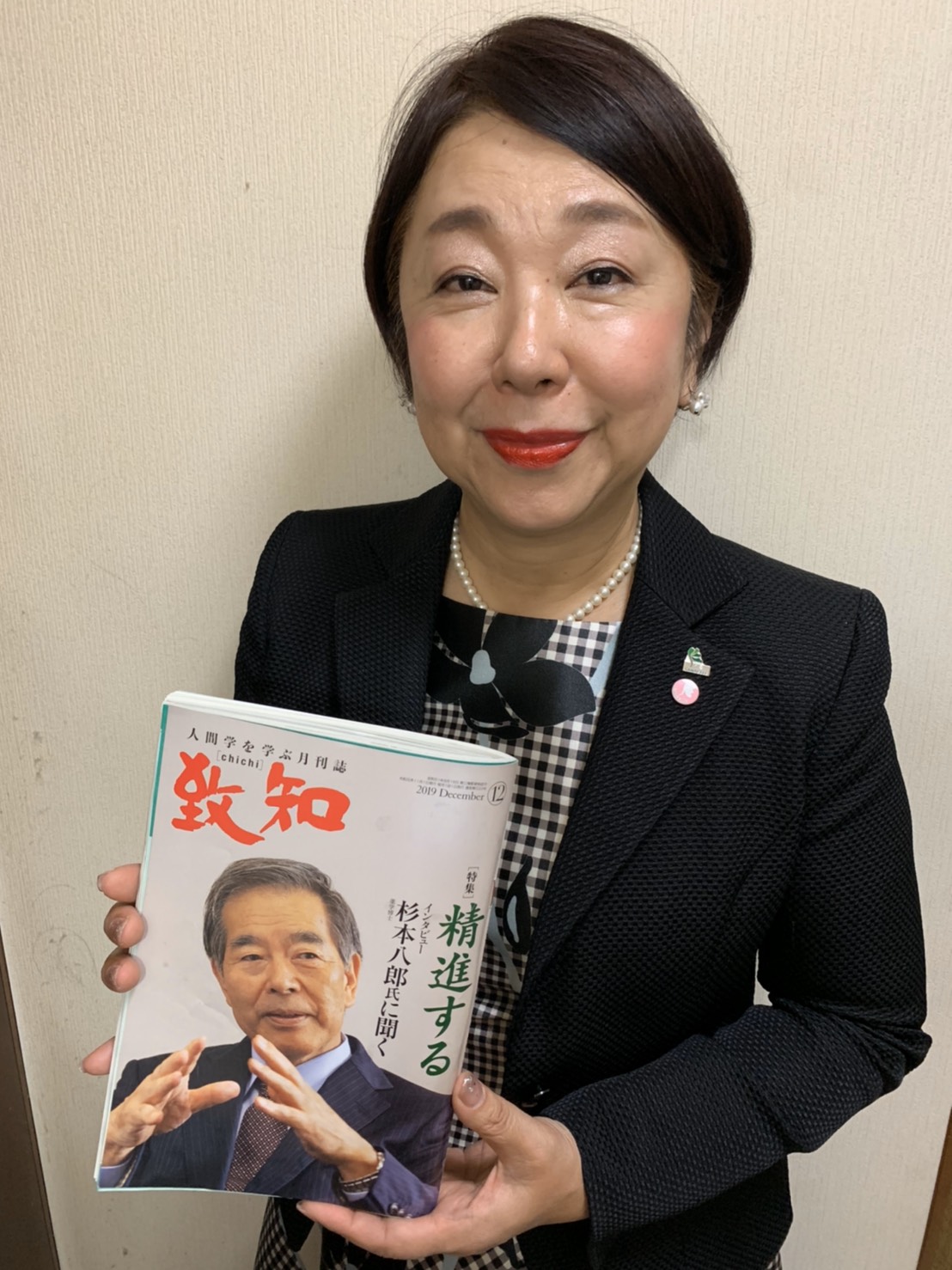
「フォーミー(私のために)」だった自分から「フォーユー(あなたへ)」に変わった
埼玉県自営業 上原 昌恵 様『致知』との出逢いはいまから5年前。大変お世話になっている会社の社長の奥様から、思いがけず致知出版社「新春特別講演会」のチケットをいただいたことがきっかけでした。私自身もいろいろと模索をしていた時期でもあり、新たなお仕事へのスタートの時でもありましたので、心弾む思いで参加させていただきました。偉大なお二人の話を聞くうちに、心がスーっとしたような想いでした。私はすぐに『致知』の購読を決めました。
毎月届くのが楽しみで楽しみで、どこに行くにも持ち歩き寸暇を惜しんで読んでいます。自分の成長にいま何が必要なのか? 仕事で成功するためにどうしたらよいのか? 器を大きくするにはどうしたらよいのか?私にとっての課題は山積でした。その答えを見つけたくて読みました。すると、いつの頃からか心の中がどんどんすっきりしていくのです。求めていた答えが不思議と『致知』の中にあり、行き詰まっていた自分を解放できました。なかなか言葉で伝え辛いのですが、『致知』は汚れてしまった魂の垢を取り除いて、もともとの魂に少しずつ戻してくれ、私の使命を思い出させてくれる気がします。
世の中には人生を変えると言われるようなセミナーがたくさんあります。それはそれでいいと思います。ただ『致知』がそれと違うのは、生まれた時に持ち合わせていた誠実、正直、優しさ、そのようなシンプルな生命を思い出させてくれることです。私自身どんどん心がシンプルになり、「フォーミー(私のために)」だった自分から「フォーユー(あなたへ)」に変わっていけたように思います。『致知』に日々触れることで、その気づきが早く訪れることを願い、私の周囲の大事な方々にも『致知』をお伝えせずにはいられません。
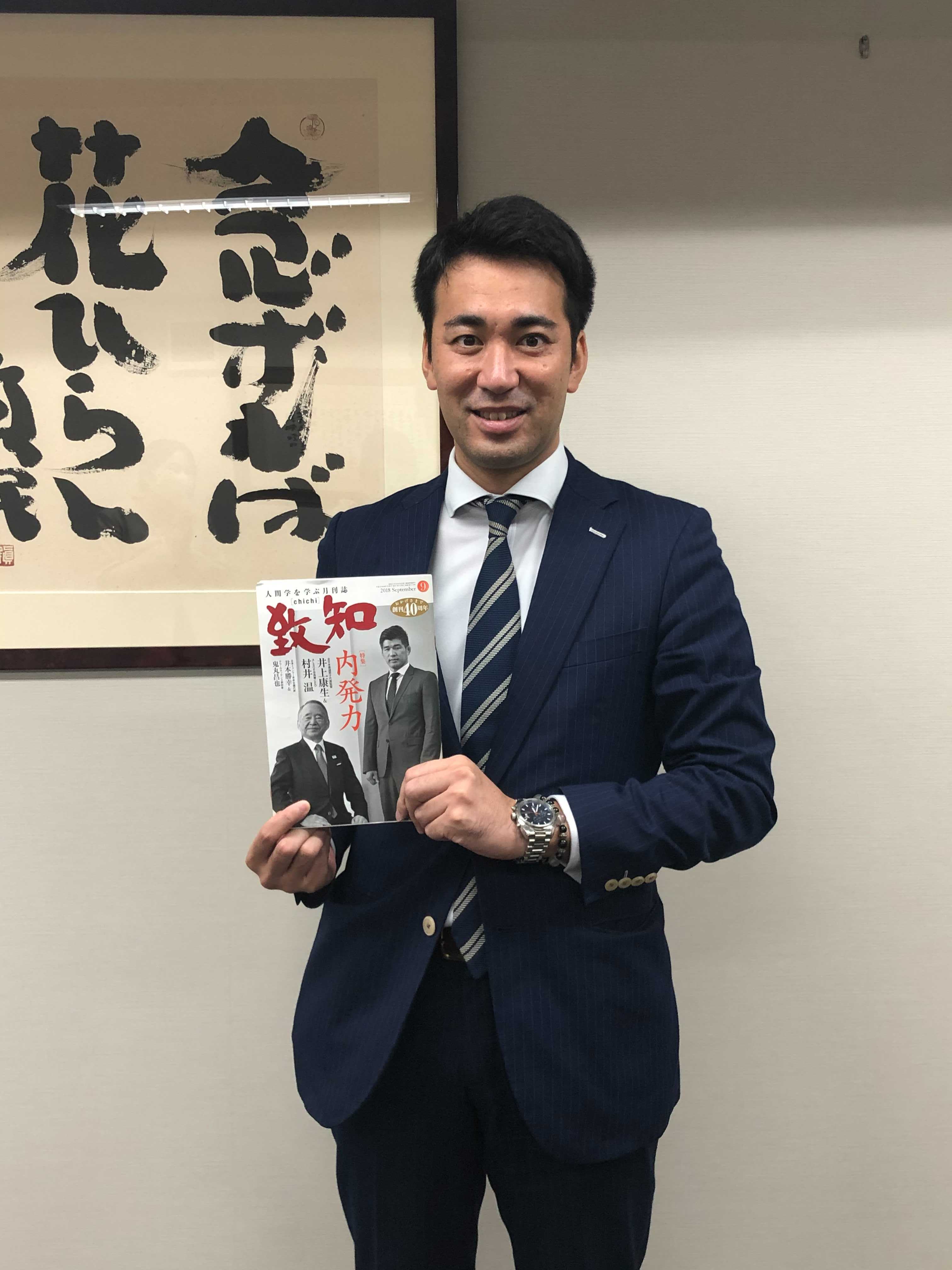
『致知』は社会人の教科書
奈良県 株式会社スポーツフィールド キャリアサポート推進室室長 吉浦剛史 様(32歳)大学卒業後、大和ハウス工業に入社。学生時代、勉強を全くせずスポーツ一本で社会人になった自分とは違い、ほとんどの同期が有名大学出身。入社時に体育会出身の同期と優秀営業マンになろうと決意しました。「売れる営業マンになるにはどうしたらいいか、建築以外にどんな勉強をしたら良いのか」と考えていた時、目に留まったのが支店長室にあった樋口武男会長の推薦図書『致知』でした。「せめて自分の会社の会長が推薦している本は読んでおかないと同期の中で1番にはなれない」と思い、購読を開始。
最初はスポーツ関連の記事しか読んでいなかったのですが、少しずつ前後の記事を読み始めました。そして、致知出版社主催の「20代30代のための人間力養成講座」に参加しました。藤尾社長の講演を聞いて、「『致知』が伝えたいことは何か。何を発信したくて『致知』があるのか」と考えながら読むようになりました。社会人になって勉強し始めた自分にとって、『致知』はまさに「社会人の教科書」でした。『致知』を読み続け1年目と3年目に優秀営業マンとして表彰していただきました。これは、まぐれではないと確信し、自分が好きなスポーツを仕事にしようと転職しました。
『致知』は深山の桜という例えをされた方がおられます。「土手に咲いている桜ではなく、深い山奥に咲く桜。しかし、いい花を咲かせている限り、うわさを聞き、人は必ず、その深山に足を運んでくれる。そして、その深山に道ができるようになる」というお話です。『致知』は深山の桜だからこそ、これからも簡単に手に入ってしまう書店で販売してほしくないし、『致知』のブランドが下がらないよう「この人は!」という人にしか『致知』を紹介しません。
最近、社内一の営業マンに「この人が読んでおいてくれないと我が社の営業の質が下がる」と購読を勧め、毎月感想の共有をしています。
これからも『致知』に学び、周囲を照らしていきます。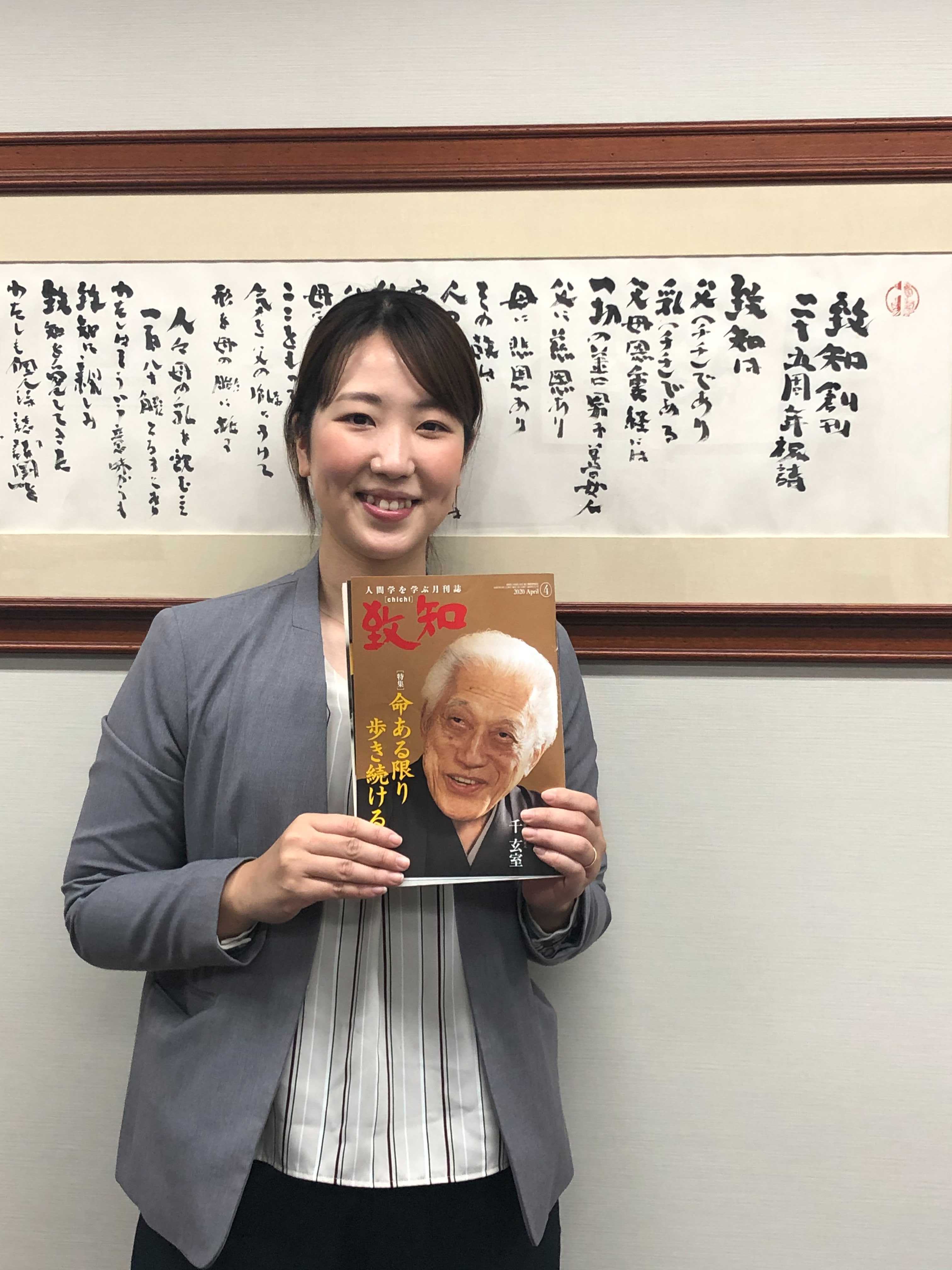
「何のために働いているのか」見失いそうだった自分の考え方を変えてくれた
千葉県 株式会社スポーツフィールド 関東Div.新卒採用支援事業Sec.長 田中 渚 様(31歳)「何のために働いているのか」見失いそうになり転職を考えていたある日、吉浦剛史さんが中途で入社してきたんです。私と年齢が一歳しか変わらない吉浦さんがイキイキと働いていたので、「自分も変わりたい。営業を教えてほしい!」と思い、「どんな本を読んでいるんですか?」と吉浦さんに聞いてみました。その時に紹介された本が『致知』でした。てっきり営業のノウハウ本を紹介してくれるのかと思っていたので、拍子抜けしましたが、借りて少しずつ読んでいるうちに、もやもやしていた気持ちが次第に晴れていくのを感じました。
『致知』を読み始めて2か月後、吉浦さんと致知愛読者の元U17サッカー日本代表監督で現在は学校法人ヴォーリズ学園副学園長の松田保先生と私の3人で致知出版社主催の「新春特別講演会」に参加しました。その車中で「なぜ『致知』を読むのか」と松田先生に伺ったところ、「『致知』は人として生きていく上で大切なものを教えてくれるから読んだ方がいい」と仰っておられ、私も「人間学についてもっと学びたい!」という思いが高まり、年間購読をスタートしました。
今まで自分で決断し一つのことを成し遂げたことがあまりなかった私ですが、本格的に『致知』を読み始め、いろんな人の生き方に触れることで、「自分のためにもっと生きていい。自分に誇れる生き方をしたい」と思うようになりました。また、自衛官である父親や主人に対して、どこか誇りと自信を持てなかった自分がいましたが、国のために働く自分の父親と主人を誇らしく思えるようになったことも大きな変化です。吉浦さんに『致知』を紹介されていなかったら、今の私はいませんでした。また、結婚して、子供を産んで仕事に復帰してからも『致知』は自分の在り方をいつまでも省みるきっかけになっており、今後も読み続けたいと思います。
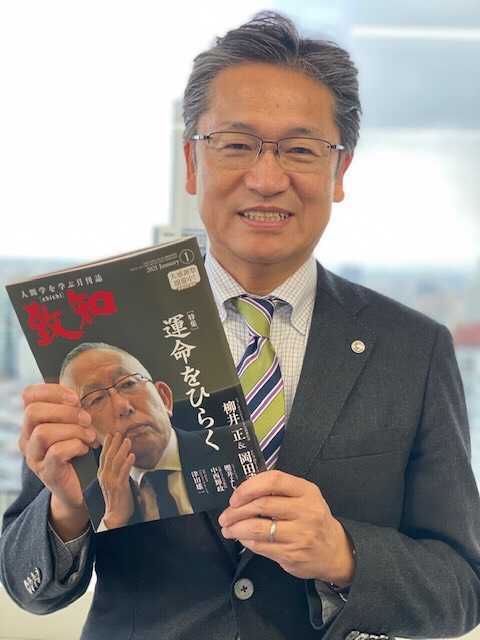
『致知』によって自分自身、そして勉強会の仲間が成長した
北海道 プルデンシャル生命保険株式会社 高塚 伸志 様(57歳)『致知』とは、2度出会っています。1度目は、20年以上前に行われた『致知』編集長の講演会です。講演内容に感動し、すぐに読み始めました。しかし、みるみるうちに積読になり、2年程で購読を止めてしまいました。数年後、尊敬している先生から『致知』をお薦めいただいたのが2度目の出会いです。その先生のご縁で藤尾社長にお会いした際に、「『致知』を読んでいるかどうかは毛穴の感覚で分かる。全部読まなくていい。総リードだけ読みなさい」と言われ、その言葉に発奮し、再び読み始めました。不思議なことに、心を入れ替えると、毎号の総リードでは今の自分にぴったりの言葉が心に染み込んできます。
現在、『致知』を読み続けて16年になります。困難や大変なことが起きても以前より驚かないようになりました。自分よりもはるかに大変な困難を乗り越えてきた『致知』にご登場の一流の方々の体験談を、疑似体験することで、一旦立ち止まり、自信をもって一歩踏み出せるようになりました。現在もライフプランナーとして働かせていただいているのも『致知』があってこそです。
また、5年前に始めた有志で始めた『致知』勉強会である『社内木鷄会』も大きな財産です。 メンバーの中には、売り上げが大幅に伸びる方、マネージャーとして活躍する方などもいて、次世代を担う人材育成の場となっています。コロナ禍で、リアルでなかなか人と会えない中、『致知』という同じ釜の飯を食べることが、ご縁のある方との心を通わせる懸け橋になっています。まさに『致知』は「絆チケット」です。これから先、「成長・学び・貢献」を軸として、『致知』からのご縁を大切に『致知』と共に歩んでいきます。







