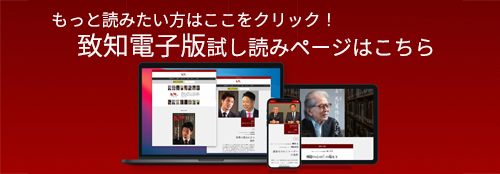2024年05月10日
◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。 かな書道の名門・正筆会の会長を務める黒田賢一氏。22歳という若さで日展に入選するなど早くから頭角を現してきた現代かな書道の第一人者です。書家人生の原点となった、師・西谷卯木氏との邂逅を振り返っていただきました。
かな書道の名門・正筆会の会長を務める黒田賢一氏。22歳という若さで日展に入選するなど早くから頭角を現してきた現代かな書道の第一人者です。書家人生の原点となった、師・西谷卯木氏との邂逅を振り返っていただきました。
1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください
両腕があるのは相対、片腕になるのは絶対
──書の道に入られたきっかけをお聞かせください。
〈黒田〉
子供の頃、近くの公民館で住職さんが習字を教えておられ、そこに通い始めたのがきっかけです。遊び半分でしたが「きれいな字が書けるね」と褒めてもらえるのは嬉しかったですね。
高校を出ると姫路市役所に就職しました。割に時間があるものですから余暇に何かやりたいと考えた時、心を駆り立てられたのが書道でした。その頃就いた前田古潭先生がたまたま漢字ではなくかなを専門にやっておられたことも私の人生には大きかったですね。
ある時、前田先生から「日展の審査員で西谷卯木(にしたにうぼく)というかなの先生が月に一度来られているから、君もそこに行ってみるか」と勧めてくださいました。
西谷先生は「この子はちょっと面白い字を書くな」と思われたのでしょうか、何回か指導を受けるうちに「神戸の自宅教室に来るように」と声を掛けてくださったんです。この時、私は19歳でした。以来、西谷先生には亡くなるまでの14年間、ずっと師事させていただきました。
──よき師に恵まれましたね。
〈黒田〉
西谷先生は正筆会を創始された安東聖空先生の一番弟子で、神戸の空襲で焼夷弾の直撃を受けて左腕を失われました。片腕をなくして書家として生きていくのは大変な逆境なんです。
ある時、師匠の安東先生がご自身の左腕を括って、書作をしてみられたと聞いたことがあります。両腕があれば横の線を引くと少し右上がりになるんですね。ところが、左腕がないと自然と右下がりになってしまう。安東先生はこの体験を通して、西谷先生が書家として片腕を失ったことがどれだけ大きなハンディかを痛感される。
実際、片腕だと紙一つ取り出すのにもとても不便です。紙に皺が寄っても両手であればすぐに広げられるのに片手ではそうはいかない。紙を固定するのも容易ではない。私が思う以上に大変なご苦労をされたことと思います。
しかし、西谷先生はそのハンディをうまく利用して、右下がりでありながら美しい流れを出す独自の西谷芸術を確立されるんですね。
──ハンディを逆手に取って自身の芸術を確立された。
〈黒田〉
ええ。その西谷先生に安東先生はおっしゃったそうです。
「両腕があるのは相対、片腕になるのは絶対。絶対に勝るものはない」と。
よく絶体絶命という言葉を使いますが、この絶体絶命の窮地を切り抜けるにはギリギリの状態に身を置いて命を懸けてやらなくてはいけない。
安東先生は西谷先生へのそんな激励の意味を込めて、絶体絶命と掛けた「絶対」という言葉を使われたのではないかと私は思っています。
本記事では、「かな文字の魅力を伝え続けて」「書のよさを決めるのは品格」など、黒田氏の書家としての原点から、かな文字との出逢い、書作をする上での心構えなどが紹介されています。「作品には作者の人間性が投影される」との言葉通り、書作やあらゆる仕事をする上で、いかに人間性を磨くことが大切かを教えられます。
◉『致知』2024年5月号 特集「倦まず弛まず」◉
インタビュー〝「書こそ我が人生 命ある限り歩み続ける」〟
黒田賢一(書家、正筆会会長)
↓ インタビュー内容はこちら!
◆かな文字の魅力を伝え続けて
◆両腕があるのは相対、片腕になるのは絶対
◆師の必死の形相に書家のあり方を知る
◆著名な書の大家にアプローチ
◆書のよさを決めるのは品格
▼詳細・お申し込みはこちら
◇黒田賢一(くろだ・けんいち)
昭和22年兵庫県生まれ。10代でかな書家の西谷卯木に師事し、22歳で日展初入選。44歳でかな書道研究会・正筆会理事長となり、以降兵庫県書作家協会会長、正筆会会長、日展理事などを歴任。日展では2度特選を受賞した他、『静寂』で内閣総理大臣賞、『小倉山』で日本藝術院賞を受賞した。日本藝術院会員、文化功労者。