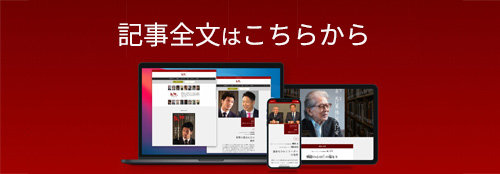2023年06月12日
 コロナ禍という言葉が耳慣れして久しい現在、降りかかる様々な事件や災害に対し、政府の対応の遅れが度々話題に上ります。なぜ、日本は危機へ迅速に処することが難しくなっているのか。気鋭の論客として活躍する先崎彰容氏(日本大学危機管理学部教授)が、この問題の本質を鋭く衝いています。対談のお相手は、ジャーナリストの櫻井よしこ氏です。
コロナ禍という言葉が耳慣れして久しい現在、降りかかる様々な事件や災害に対し、政府の対応の遅れが度々話題に上ります。なぜ、日本は危機へ迅速に処することが難しくなっているのか。気鋭の論客として活躍する先崎彰容氏(日本大学危機管理学部教授)が、この問題の本質を鋭く衝いています。対談のお相手は、ジャーナリストの櫻井よしこ氏です。
外圧があって初めて変わろうとする国
〈先崎〉
前略)お話のように吉田茂以来の日本の経済政策は、130億ドルを出したのに全く感謝されなかった湾岸戦争での対応で行き詰まったわけですが、僕が一番憂慮しているのは、今回のコロナ禍でデジタル構想、経済安全保障という言葉が出てきたように、危機的なことが起きないと従来のやり方を変えられないのが日本人の習性のようになっている点なんです。
ペリー来航の時も敗戦の時もそうだったかもしれないけれども、危機があって初めて現状を変えていこうという機運が生まれる。今後、戦争状態になってようやく憲法改正が議論されるのではないか、というのが僕の抱く危機感ですね。
しかし、あらゆることがそうであるように、危機や混乱の最中に改正しようとすると、改悪になりかねないんです。だからこそ、平時から状況に応じて改正すべきなのであって、実際、後手後手でやっていくとどうなるかということを僕らは今回のコロナ禍のいろいろな場面で見せつけられました。
例えば、20年以上前の平成13年にIT基本法が制定されています。ところがいまも裁判所に行くと裁判官や弁護士たちが大きな黒いバッグに分厚い資料を入れて、鉛筆をなめなめページを捲りながら仕事をしている。そういうことがいまなお東京のど真ん中でも行われています。
それが正しいと思って疑いもしなかった。IT基本法を主導した総務省が、このコロナ禍に音頭を取ってデジタル庁をつくっている。一番遅れた霞が関周辺の村社会は、本当に自ら先頭を切って社会構造を変えられるのでしょうか。
〈櫻井〉
危機の中ではまともな改革ができない、平時の時にこそやるべきだというご指摘、その通りだと思います。ところが、平時になると、日本人は安心してしまって、ちっとも動かないわけですね。
このコロナ禍で政府が国民に交付金を支給する時も、どこに誰が住んでいるかを行政が全く把握していませんでした。全住民の情報把握ができてない。日本は平時に議論して仕組みを変えるということができにくい。危機が起きるまで待ちましょうという体質が身についてしまっている。
原因は日本人の「マインド」の遅れ
〈先崎〉
東日本大震災の時にも痛感しましたが、もしわが国が軍事的な危機に陥れば、この国は負けます。日本の脆弱性が今回のコロナ禍ほどあからさまになったと感じたことはありません。僕はこのコロナ禍が日本人が目覚める最後のチャンスではないかとも思っているんです。
ここで一つぜひお伝えしておきたいのですが、いまの給付金の遅れに関して岸田さんは著書でデジタル化の遅れが原因だったと書かれています。だけど、本質はそうではない。日本人のマインドの遅れなんです。私権制限をするのは国家権力の悪用だという権力VS市民という二項対立の構図、権力を叩きさえすれば済むという考え方がメディアを中心にいまなお続いていることこそが問題の本質なんです。
〈櫻井〉
とても大事なご指摘ですね。
〈先崎〉
反権力の構図ではいまの社会を全く読み解けないし、時代を正しく掴めない。このコロナ禍で安倍政権が独裁どころか、地方自治体との折衝に苦慮したことは、それを端的に示しています。
戦後の基本的な思想の矛盾は、権力を悪と位置づけて政治の世界を論じてきたことです。しかし、政治というものの役割は権力を正しく運用することにあるはずです。私たち国民は何らかの権利の制限を受けることで、非常時における自由を確保できる。コロナ禍でも、権力を行使することを悪と捉える論調があまりに強調されたために、そういう自由闊達な議論ができないままでした。
(本記事は月刊『致知』2021年12月号 特集「死中活あり」より一部を抜粋したものです)
◉本記事では国際情勢、危機管理に精通するお二人に
・エネルギー問題の本質が見えてきた
・岸田首相の挙措動作
・自由と民主主義は絶対的なものなのか
・最大の危機は日本人自身にある
・日本のリーダーが掲げるべき旗とは
など、日本が直面している難題への処方箋、日本が進むべき道を語り合っていただきました。櫻井さんと先崎さんの対談全文は「致知電子版」でもご覧いただけます。試し読みはこちら
◇櫻井よしこ(さくらい・よしこ)
ベトナム生まれ。ハワイ州立大学歴史学部卒業後、「クリスチャン・サイエンス・モニター」紙東京支局勤務。日本テレビニュースキャスター等を経て、現在はフリージャーナリスト。平成19年「国家基本問題研究所」を設立し、理事長に就任。23年日本再生に向けた精力的な言論活動が評価され、第26回正論大賞受賞。24年インターネット配信の「言論テレビ」創設、若い世代への情報発信に取り組む。著書多数。最新刊に『亡国の危機』(新潮社)がある。
◇先崎彰容(せんざき・あきなか)
昭和50年東京都生まれ。東京大学文学部倫理学科卒業。東北大学大学院博士課程を修了、フランス社会科学高等研究院に留学。現在、日本大学危機管理学部教授。専門は日本思想史。著書に『国家の尊厳』『未完の西郷隆盛』『違和感の正体』『バッシング論』(いずれも新潮社)『ナショナリズムの復権』(ちくま書房)など。
◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――
《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。
※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください