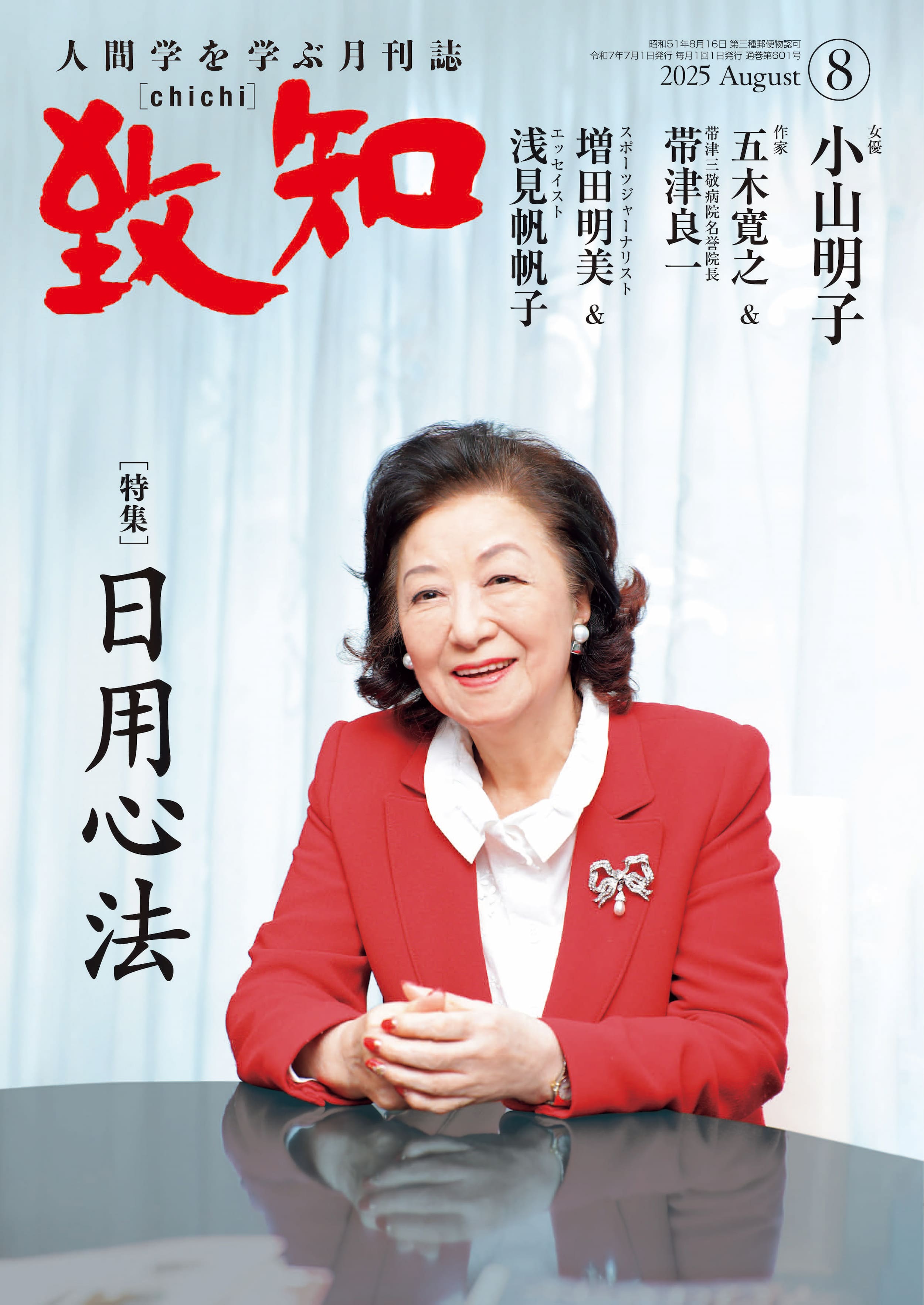2022年02月02日
 生涯に約500の企業育成に携わり、社会公共事業や民間外交に尽力した渋沢栄一。生誕180年を超えたいまなお、その生き方や教えは多くの経営者らに受け継がれています。そんな渋沢翁の令孫として生まれ、生前の祖父に温かく見守られて育ったというエッセイストの鮫島純子さんに、間もなく白寿を迎える半生を振り返り、当時の思い出を語っていただきました。
生涯に約500の企業育成に携わり、社会公共事業や民間外交に尽力した渋沢栄一。生誕180年を超えたいまなお、その生き方や教えは多くの経営者らに受け継がれています。そんな渋沢翁の令孫として生まれ、生前の祖父に温かく見守られて育ったというエッセイストの鮫島純子さんに、間もなく白寿を迎える半生を振り返り、当時の思い出を語っていただきました。
◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。
1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください
榮太樓飴を口に入れてくれた祖父
私は1922年、祖父の家近くで生まれました。祖父終焉の自宅はいま飛鳥山公園(東京都北区)の一部になっていますが、幼い頃は両親とともに行き、従兄たちと合流して遊ぶのが楽しみでした。
祖父は70代で、営利事業から既に手を引いていましたが、それでも国際親善や教育活動、困窮者の相談、手伝いなど忙しく、自宅には訪問者が出入りしていました。
その頃の祖父はいつも和服姿で、大きな籐椅子に腰掛け、孫たちの遊んでいる姿をただ黙ってニコニコと見ていました。「ごきげんよう」と挨拶をすると、「よう来られたな」と言いながら孫たちの頭を一人ずつ撫でて、食籠に入った榮太樓飴(えいたろうあめ)を一個ずつ口に入れてくれます。
もちろん、私たちは祖父が日本の近代化に貢献した経済人であることなど知りませんし、何か教えを請いたいという思いもありません。私が祖父の生き方を教えられたのは、中高生になってから父を通してであったような気がします。
父は祖父が手掛けなかった製鉄製鋼を官営から民営に移し、懸命に働いた人ですが、祖父を「大人」と呼んで尊敬していました。自宅の居間には、祖父の直筆による
「人の一生は重荷を負いて遠き道をゆくが如し。いそぐべからず不自由を常とおもえば不足なし云々」
という徳川家康公の遺訓を掲げ、それを常に服膺し、私たちへの戒めにも用いていました。
休日になると、永年忠勤の運転手さんの運転で近郊の緑地あちこちに私たち家族を連れていってくれました。私は家族一緒のただ楽しい一日でしたが、関東大震災の後、東京が過密化する中で、各所に広い緑地を備えて非常時に住民の安全を確保しなくてはいけないと主張していた父にとっては、実はこれも仕事の調査だったのだと思います。空き地の周囲を私たちが何歩歩いたかを数え、距離や面積を計測したりもしていました。
祖父がそうだったように、我が家も父の出勤前から父を訪ねてくる方たちがいました。父はそういう人たちを励ましたり、時には諫めたりして親身になって相談に乗っていましたが、公に尽くす祖父の生き方を見習って、広い視野で利他の生き方を、図らずも私たちに背中で見せてくれていたのです。
深く遠い慮り
海軍横須賀鎮守府の主計長だった夫とお見合いし結婚したのは1942年、大東亜戦争初期の、まだ国中が日本の躍進に沸いている最中でした。
しかし、開戦前、有力政治家と親交が深かった父が、戦争回避に向けて奔走する姿を見ていた私は、この戦勝ムードにどうしても馴染むことができませんでした。製鉄会社で働いていた父は、鉄の生産量から考えても日本に勝ち目がないことが十分分かっていたのです。
結婚8か月目、本来の職場・航空機製作所に戻ると、夫の転勤で名古屋の中心部に住むことになりました。夫が長期出張中の1944年12月、知多半島震源の大地震があり、私は1歳の下の子を抱いて慌てて庭に飛び出しました。2階に駆け上がって昼寝中の2歳の上の子を救い出し、大揺れの中、命は守られましたが、年が明けた1月3日、追い打ちのように名古屋市は初の空襲を受け、我が家も焼夷弾の雨に見舞われたのです。
焼夷弾が降り注ぐ中、素掘りの壕から飛び出した子供を片手に、もう一方の手で濡らした筵を引きずって必死に火を消し廻りました。幸い近所の皆様が駆けつけて手助けしてくださったことで借家は焼けずに済みましたが、信じられないような力が出せたのは自分でも驚きでした。これが火事場の馬鹿力かといまになって思います。
そんな私たちを心配していただいたのでしょう。「こんな街中は危ないから郊外にあるうちの茶席に越していらっしゃい」と声を掛けてくださったのは、昔、祖父を徳川慶喜公の家来に取り持ってくださった平岡円四郎さんのお孫さんに当たる方です。
円四郎さんは誤解から水戸藩攘夷派に暗殺されますが、ご遺児を不憫(ふびん)に思った祖父は、明治初期に家を建て、恩人の遺児を保護しました。その方の娘さんが名古屋近郊で料亭を営んでおられ、祖父への恩返しとして家を提供してくださったのです。祖父の施しが、年月を経て徳も積まぬ私が恩恵を受け、ご縁をありがたくいただいた次第でした。
祖父は困った方に直接金品を与えるより、その方の特技を引き出しお働きに生き甲斐を感じるように仕向けたようです。平岡さんの場合も、書道の先生として孫たちの家庭を回ることで、謝礼以上のご援助をする、という形にしていたようです。
父の一高の同級生がご尊父の急死により進学を断念せざるを得なくなったという話を父から聞いた時も、祖父は息子たちの学生寮を設け、その方を学生長というかたちの謝礼でご郷里の支援をしました。本人が遠慮を感じないよう、またプライドを損なわぬよう祖父なりの慮りがそこにはあったようです。私はそのご子息から聞かせていただき、この思いやりに感銘しております。
(本記事は月刊『致知』2018年11月号 特集「自己を丹誠する」より一部を抜粋・編集したものです) ◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。
◇鮫島純子(さめじま・すみこ)
大正11年東京生まれ。昭和17年結婚。祖父は渋沢栄一、父は栄一の四男で実業家の渋沢正雄。著書に『なにがあっても、ありがとう』(あさ出版)『毎日が、いきいき、すこやか』(小学館)『祖父・渋沢栄一に学んだこと』(文藝春秋)など。