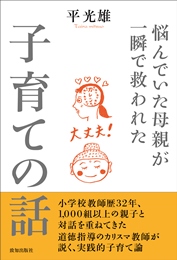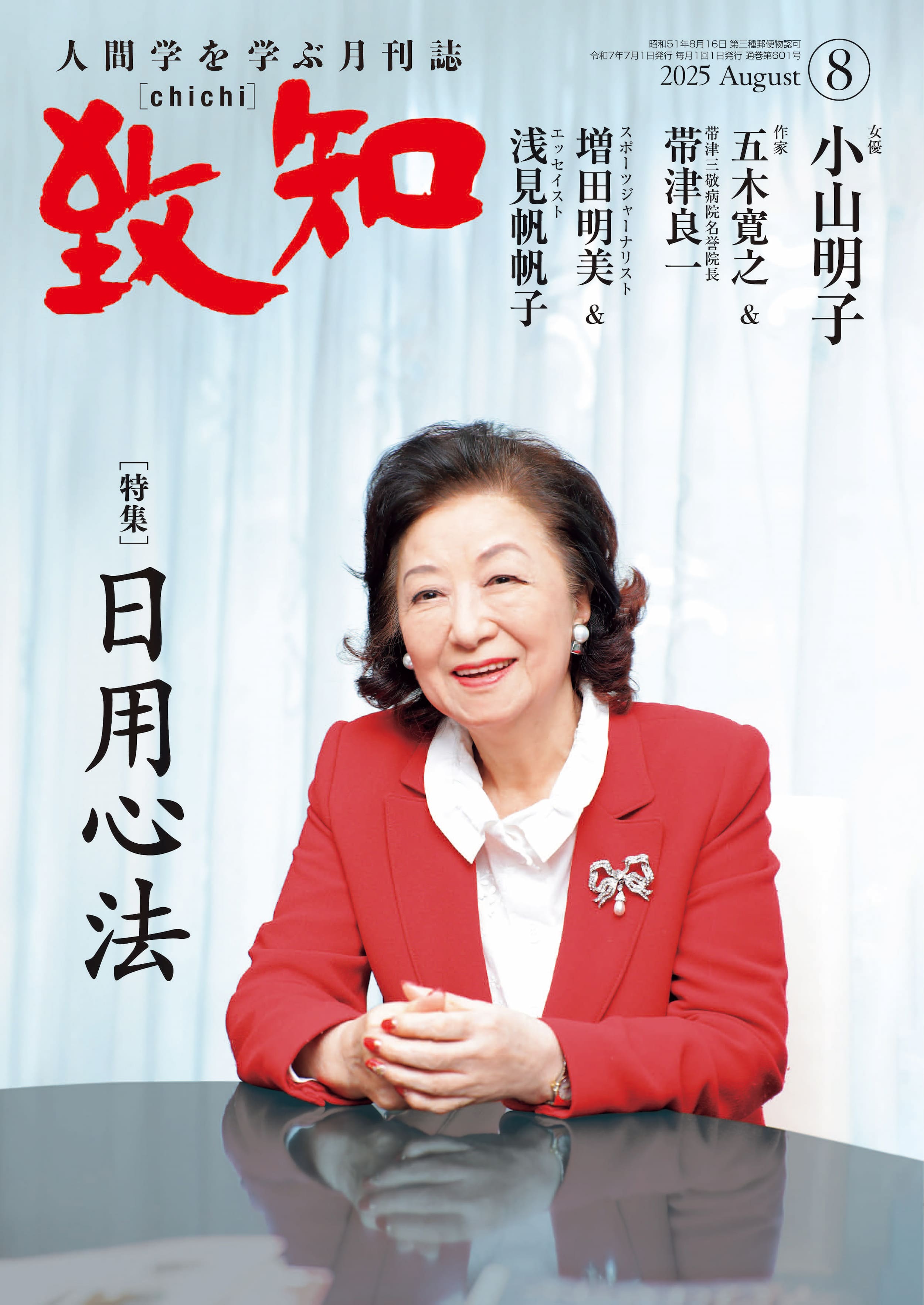2019年12月20日

学級崩壊に瀕したクラスを立て直す経験もしてきた小学校教師歴32年の平光雄氏。反抗期の子どもにどう対処するかなど、このカリスマ教師が実践的子育て論を説いた一冊『悩んでいた母親が一瞬で救われた道徳の話』から、子育てに悩む親たちの目を劇的に開かせた30の逸話の一部をご紹介します。
☆あなたの人間力・仕事力を高める記事や言葉を毎日配信!公式メルマガ「人間力メルマガ」のご登録はこちら
心のコップに水を貯める
子どもが何か問題を起こしたとき、こういう親もよくいます。
「そんなこと、言われなくてもわかっているはずなんですけどね。」
「そんなこと、わからないはずないですよね。」
そうかもしれない。しかし、そうとは限らないかもしれない、ということも多いのです。
たとえば、何も指導せずに、幼い子に初めて「テスト」をしたら、平気で隣の子の答案を「カンニング」する子がたくさんいてもおかしくはないでしょう。
それはそうでしょう、「カンニングが悪い」という価値観がないのですから。
仮に、それまで「周りの人を見て行動しなさい」というような指導を強く受けていたら、むしろ教えを守ったわけで、叱ったとしても「ボク、隣の子と同じことを書いただけだよ」ときょとんとするでしょう。子どもにとってみれば、屁理屈、言い訳というわけではありません。
妙な例を出したのは、これが規範意識の典型であるからです。
道徳的な価値は、どれもが自然発生的に生まれてくるものではありません。
どのルールも、人殺しや盗みなどのように、自然な情として「悪」と感じられるものを禁じたり罰したりしているわけではありません。
だから、それが「いけないこと」と教えていないことは、叱っても響かないということも起こりうるのです。
たとえば、作業の丁寧さや慎重さなどは、それができていないと叱る前に、どれだけそれが大切かを教えているかによって、心への響き方は大いに変わってくるのは当然だということです。
心の中に、それまでに「作業の丁寧さ」や「慎重さ」がたとえば、学業の上でどれほど大切かという価値観ができており、その上でそれができていないと叱ったならば、心の中の価値観とその言葉が「感応」し合います。そうなると叱責の効果は大です。
「感応」が全くない場合を「馬の耳に念仏」というのです。
そうならないためには、普段から子どもの心の中に、必要な価値観を培っていくことです。それはあたかも心の中にコップがあって、そのコップに一滴ずつ水をためていくようなイメージです。
最初は言っても言っても効果がないかもしれません。そのときは、まだ水が溜まっていないからなんですね。内側との「感応」がないからだ、と思うことです。
先の「作業の丁寧さ」ならば、普段から折に触れて、「丁寧さ」の価値を貯めていく。テレビを見ながら、「イチロー選手は、試合前も試合後も、グローブやバットの手入れを欠かさないんだってね。だからこそ、名選手なんだね…」「本田選手は…」「浅田真央選手は…」というように、日常的に貯めていくのがいいでしょう。
そうすると、次に子どもが「手抜き」をやって、叱ったときには響きます。
私は、これを折に触れて教室でやっていました。たとえば、子どもたちが何か作業をしているとき…独り言のように、「なんでもやる以上、最後まで丁寧にやることが大事だよなぁ」とか「何でも心込めてやらなきゃね…」など独り言のように言いながら、子どもたちの心の中のコップに少しずつ水を貯めていく。
そうすると、次に叱るにしても、「雑だよね」「これ、心こもってないよね」などと、とても簡潔に済むという利点もあります。
しつこく言う必要はなくなります。むしろ、長々説教を続けてしまう、しかも効果がないというのは、普段の「水貯め」ができていないから、なかなか相手に響かないことが原因かもしれないと思ってみることも必要ですね。
説得するにはTPOを考慮して
子どもが高学年になると、「親のいうことをちっとも聞かない」という悩みを抱える親が多くいます。もちろん、それは自立心が育っている証拠で、「何でもいうことを聞く子」よりはるかに頼もしいのですが、悩んでいる親に「それでいいのですよ」と言ってだけ済ますわけにはいきません。
親として「どうしても伝えたいこと」もあります。また、なくては困ります。
そこで、悩む親には、こんな話をしてきました。
○さんは、自立心も育ってきているんだから、これは親として喜ばしいことでもあるんですね。ま、気に食わないことだろうけど。でも、いつまでも「何でもハイハイ言うことを聞く子」よりずっといんですよ。
…といって、済ますわけにはいかないこともありますよね。
そんなときは、簡単にいうと「子どもの機嫌がいいとき」を狙って話すんです。思春期の子は、気に病むことが多い。将来への不安や、友人関係のこと、自分の能力への疑念…そんなことで心の中が溢れているんです。その上、親が何かを注入したいといっても「いっぱい、いっぱい」の心にはなかなか入りません。
そのうえ、親は、説得をするタイミングを間違えていることが多いんです。
説得は「説得場面」たとえば、子どもの何か不都合な状況に対して、叱責したり、お説教したりする場面で、説得しようとしたって、特に反抗期を迎えた子なんかには全く心の中に入りゃしません。
それは、心の中の「巾着袋」の口をぎゅっと締めてしまった状態と言ってもいい。口を締めて「嵐」か「不快」な時間が通り過ぎるのを待つだけです。ほぼ無駄です。
「説得」は「説得場面」より、「日常的説得」の方がはるかに有効です。
大事なことは、「日常的説得」でする。
いくら激しい反抗期の子どもでも、日常生活の中で機嫌のいいときはあるものです。そんなときは、「巾着袋」の口は緩んでいます。そのときがチャンスです。大事なことをさらっと話すんです。
テレビを観ながら、ドライブしながら、さらっと、親としてぜひ伝えたいことを小出しにして巾着袋の中に放り込む。これは入ります。だだ、「小出し」であることもお忘れなく。親は欲張りすぎ、性急すぎることが多いですから。
「説得だな」「説教だな」と感じられないようにそこは大人として、自制心をもって工夫してください。感じられたら、そのとたん、口を締めますから。
親としてどうしても心に残して欲しいようなことは、心の「巾着袋」の口が開いているときに言うようにすることです。特に反抗期、思春期の子には。
口をこじ開けようとしたって、無駄というだけでなく、過剰な反発を招くなどの弊害も多いのです。
親として「何を言っても聞かない」と言って諦めるのはいけません。諦める前に説得するTPOをかえることを考えることが大切です。
(本記事は『悩んでいた母親が一瞬で救われた子育ての話』〈致知出版社刊〉を一部抜粋・編集したものです)
◇平 光雄(たいら・みつお)
昭和32年愛知県生まれ。58年青山学院大学文学部教育学科(心理学コース)卒業後、愛知県で小学校教諭となり、今年で学級担任30年目となる。平成10年より話力総合研究所(東京本郷)に通い、永崎一則氏のもとで話力学を学ぶ。著書に『戦争とくらしの事典』(共著・ポプラ社)など。