2025年05月14日
◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――
平均年収は30年以上横ばいが続き、エンゲル係数も2024年に28.3%の高水準を記録するなど、極めて厳しい状況に置かれている国民生活。民に配慮した国家運営が求められるいまこそ、政治家は「ギブ&テイク」を原則として国を治めた、偉大な先人の姿に学ぶ必要があると數土氏は語ります。(本記事は月刊『致知』2025年5月号 巻頭の言葉「予うるの取りたるを知るは政の宝なり」より抜粋・編集したものです)
《期間限定》充実した2026年を送るための新習慣として、月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を開催中。
民から慕われた先人に共通するもの
〈數土〉
約2,700年前、古代中国は春秋戦国時代の斉の国で、傑出した人物が宰相(首相)に登庸されました。名は管仲(管子)。その地位にあること40年。弱小で混乱の中にあった斉を超一流国、覇権国に押し上げました。その管仲が説いたのが、表題の言葉です。
「予うるの取りたるを知るは政の宝なり」
(与えることは、取ることである。この原則を知ることが政治の要諦なのだ)
管仲の政治の基本は、領民生活の優先でした。領民が苦しく、貧しいうちは、租税を可能な限り軽減する。斉の君主、桓公は彼を信頼して長らく国政を託し、領民も彼を支持しました。
『史記』を編纂した司馬遷は、管仲を史上最も優れた政治家と絶賛し、『三国志』で有名な諸葛孔明も、敬意を表すべき政治家として管仲を挙げています。孔明は管仲に比肩し得るのは自分としており、両者とも財務の精査に人一倍余念がなかったことは注目に値します。
一方、1,300年前の日本では、初めて国史が編纂され、『古事記』、『日本書紀』が成りました。それらによれば5世紀頃、第十六代の天皇は、民家の竈から煙が立っていないのを見て民の窮乏を察知し、これを救うため3年間徴税を禁じました。3年後、一息ついた民が納税を申し出るもさらに3年間徴税を控え、民が潤って後に初めて宮殿を修復し、続いて河内平野の開発、開拓と必要な公共工事を推進。国家財政を立て直し、民から大いに慕われ、後に仁徳と諡されました。
政治家は国民への配慮を第一に
〈數土〉
さて、現在の日本。元気、明るさいま一つ。日本国民の平均年収は、1990年代の460万~470万円から30年以上ほとんど変わらず、2023年の実績は460万円。完全に世界に取り残されてしまいました。
他の数値もよくありません。
国民負担率は2022年に48・4%と過去最高を記録。エンゲル係数も2024年には43年ぶりに28.3%という高水準。国民が極めて厳しい状況にあることは容易に推測できますが、国政に参画している政治家は、この現状をどのように感じているのでしょうか。
さすがにこのような状況下、「103万円の壁」が問題として提起されました。野党の国民民主党が、所得に対する課税下限値を103万円から178万円に引き上げることを提案。自民、公明、国民民主の3党幹事長の協議で「103万円の壁は178万円を目指して来年度から引き上げる」と合意しました。
しかしその後紆余曲折を経て、3月の衆議院本会議では、所得税の課税最低限を160万円に引き上げるなどの修正が加えられて可決されました。この問題についてはまだ様々な議論があり、今後の動向が注目されます。
壁の引き上げによって、人手不足解消の期待が持てます。そうなれば、経済学における乗数効果「雇用乗数」が「減税乗数」をさらに大なるものにすることが期待できます。
実際に名古屋市は、河村たかし市政の15年間で約1,500億円を減税し、2024年には過去最高となる6,276億円の税収を計上したと報告。減税による乗数効果が小さくないことを示唆していると思います。減税と聞いて「財源は?」と後ろ向きに捉えるのではなく、こうした事例も十分研究した上で判断すべきではないでしょうか。
本年、日本国民にとって看過できない数値、「租税支出透明性指数」(GTETI)なるものが公表されています。これはドイツとスイスの権威あるシンクタンク、IDOSとCEPが共同設立している「租税支出研究所」が発表している指数で、G7国のほとんどが10位以内にある中、日本は104か国中94位と最下位グループです。
我が国民は租税の使われ方についてほとんど知らされておらず、また知ることが簡単ではないのが現状です。国会の予算委員会はいったい何を審議してきたのでしょうか。茶番劇だと国際機関に指摘されたも同然です。自分の保身ばかり、口先ばかりでなく、苦しい国民生活に第一の関心を持つ政治家になってもらいたいものです。
前段でご紹介した2,700年前の管仲、1,600年前の仁徳天皇は、弱者や貧者に対してはテイク&ギブではなく、ギブ&テイクを原則にした人でした。つまり、取ることよりも与えることが先、「取るためにはまず与えよ」ということです。偉大な先人が身を以て示した政の要諦を決して忘れてはなりません。
「致知電子版」なら過去約9年分(100冊以上)のバックナンバーが読み放題!! 詳細はこちらか、下のバナーをクリック↓
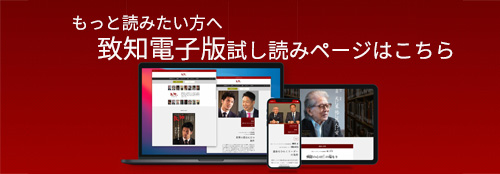
◇數土文夫(すど・ふみお)
昭和16年富山県生まれ。39年北海道大学工学部卒業後、川崎製鉄入社。常務、副社長などを経て、平成13 年社長に就任。15年経営統合後の鉄鋼事業会社JFEスチールの初代社長となる。17年JFEホールディングス社長に就任。経済同友会副代表幹事、日本放送協会経営委員会委員長、東京電力会長を歴任し、令和元年より名誉顧問。著書に『徳望を磨くリーダーの実践訓』(致知出版社)。














