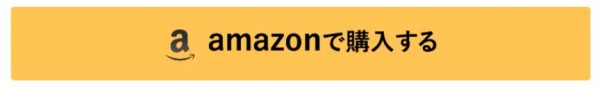2025年10月15日
◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。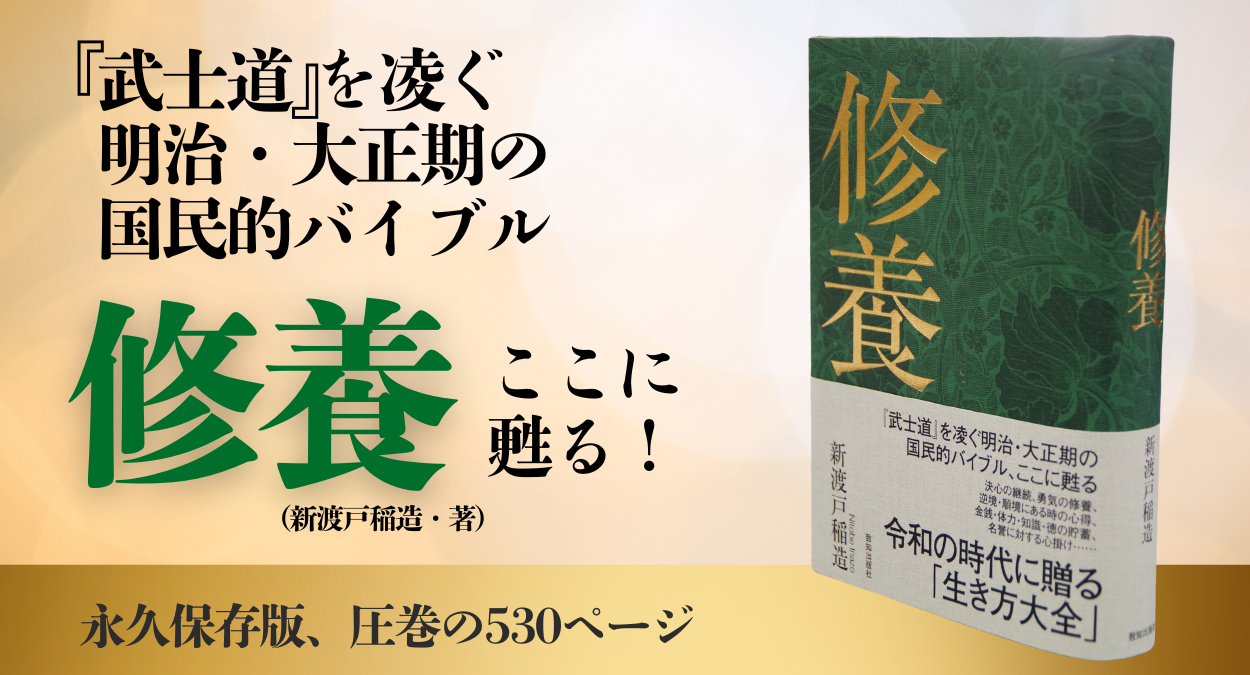 1911(明治44)年、当時49歳の新渡戸稲造が著した代表作『修養』。同年9月の初版から昭和9年6月までに、実に148版を重ね、『武士道』を凌ぐ驚異的なロング&ベストセラーとなりました。百年以上前に書かれた本でありながら、「勇気の修養に必要な心得」「弱点も克己して善用せよ」「逆境・順境にある時の心得」など、その内容には普遍性があり、令和の時代における「生き方大全」とも呼べる一書です。本書の序文を一部ご紹介します。
1911(明治44)年、当時49歳の新渡戸稲造が著した代表作『修養』。同年9月の初版から昭和9年6月までに、実に148版を重ね、『武士道』を凌ぐ驚異的なロング&ベストセラーとなりました。百年以上前に書かれた本でありながら、「勇気の修養に必要な心得」「弱点も克己して善用せよ」「逆境・順境にある時の心得」など、その内容には普遍性があり、令和の時代における「生き方大全」とも呼べる一書です。本書の序文を一部ご紹介します。
1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください
序
僕はかつてこういう談を聞いたことがある。
昔、某という博学の儒者があった。万巻の書を読破し、何ひとつ通ぜざることとてはなかったが、いかんせん活用の才なく、該博の学問も空しくこれを死蔵して少しも利用することができなかった。やがて年老ゆるに従い、記憶力衰え、ただに読んだ書巻のことのみならず、見たこと聞いたことまでも、ことごとく忘れ、ついには人に逢うても、しばらくたてば、その人の姓名も容貌も茫然として忘れ、後には自分の年齢さえも忘れてしまい、はなはだしきに至っては、人と語っても、目上の人と目下の人との差別もつかず、男にも女にも、老人にも子供にも、一切区別して話すことができなくなった。
世人はこの人を嘲って忘却先生と呼んだという。
この談を聞いて以来、僕は書籍を閲するごとに、これも必ず早晩忘れてしまうのであろうと思わぬことはない。もとより僕には忘却先生の博学なければ、先生の例を引いてただちに自分に当てはめんとするは、いささか謙譲の徳を失するの嫌いあるも、忘却の一点においては、残念ながら、僕実に先生に一歩も譲らぬものであることを自白せざるを得ぬ。現に折々は閑にまかせて、書棚の中から古蔵書をひき出し、書中にかつて繙閲した当時、批評を記入した跡を見るごとに、こんなものを、いつ読んだろうか、よくこんなに読書したものであると、自分ながらも不思議に思うことがしばしばある。僕もおいおいと知らぬ間に年をとり、まきに五十の坂を越えんとする。かつて見聞したことを青年に分かつに及ばずして、早くすでに忘却先生の轍を踏むかと思えば、遺憾いかばかりであろう。
そこで一つには従来聞きかじったことを青年に分かち、また今日まで事に当たり物に触れて自ら感じたことをありのままに述べ、もって後進の参考に供したい考えから、「実業之日本」の余白を借り、毎月二回卑見を述べて読者にまみえて来たが、陳言も積もって今やすでに百回になんなんとする。これは自分の専門学の余暇に、ただ偶爾の随感随想を述べたるに過ぎざれば、自ら浅薄なりと思う点も多く、またこの点にも少し深く立ち入って説きたいと思う事柄もあるが、初めからかなり通俗を旨とし、車ひく人、柴刈る野の人にも、なお解し得る程度に話したいと思い直しては、 込み入ったことを省き、もっぱら平易を主とし、浅く平たく綴ったのである、ために識者がこれを見たら、あるいは笑うべきこともあまたあるであろう。また実際、折々友人からも、談話のあまりに通俗平易に流るることは、自分の位地職務等に対して感心せぬ、も少し趣をつけたらよかろうと、忠告を受けたこともないではない。あるいは談話中に、往々自分の経験を述べ、常識あるものはほとんど掩うて人目にさらすべからずとするがごとき赤恥を顧みぬこともある。
これらの事柄は自分ながらも気づかぬわけでもないが、ここがすなわち忘却先生に酷似した点で、談話しつつある間、相手が少年か老年かも忘れ、あるいはいかなる位地に今日自分がいるかも忘れ、またこれが恥辱か名誉かさえも忘れ、興に乗じて物語った次第であるから、本書を読む者にして、もし奇怪に思うことがあったなら、これ前述した僕の欠点に出でたることを思うて諒としてもらいたい。
本書は、時々事に感じたことを随録したものであるゆえに、整然たる順序もなく、ただ一つの偶語に過ぎぬ。毎回号を改むる雑誌においてはともかく、改めてこれを一の単行本とする価値の有無に至っては、自ら疑うところであるが、あまたの読者よりの懇望もあったので、恥ずかしとは思いながら、一束として世に公にした。
もし本書にして、一人にても二人にても、迷う者のために指導者となり、落胆せんとする者に力を添え、泣く者の涙を拭い、不満の者の心をなだめ得るなら、これぞ著者望外の幸いであり、 また年齢をも恥をも忘れた甲斐があったと思い、深く読者に感謝する。
明治四十四年七月
新渡戸稲造
『修養』好評発売中!
詳細はこちら↓
◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください