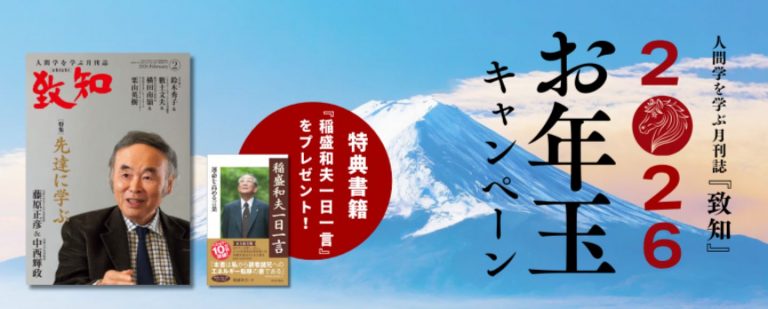2022年08月24日
 車いすといえば、体の不自由な人の移動を補助するもの。しかし鈴木堅之さん(TESS社長)の手掛ける「足こぎ車いす」は、乗れば動かなかった足が動き、リハビリに活用すれば歩けるようになるケースもあるといいます。もともと頓挫したプロジェクトを元教師の鈴木さんが引き継いだ当初は、誰からも相手にされなかったそうですが、この画期的な車いすはどのように完成したのでしょうか――。
車いすといえば、体の不自由な人の移動を補助するもの。しかし鈴木堅之さん(TESS社長)の手掛ける「足こぎ車いす」は、乗れば動かなかった足が動き、リハビリに活用すれば歩けるようになるケースもあるといいます。もともと頓挫したプロジェクトを元教師の鈴木さんが引き継いだ当初は、誰からも相手にされなかったそうですが、この画期的な車いすはどのように完成したのでしょうか――。
引き取り手のない事業を引き継いで
〈鈴木〉
国が大学ベンチャー千社計画というのを進めていて、東北大も産学協同で会社を立ち上げるというので、私は何とか足こぎ車いすを普及したいと考えて、教員を辞めてその会社に入れていただいたのです。
――事業は順調でしたか?
〈鈴木〉
その会社は経営や医療など、各分野のプロが集まり、大きな資本金を入れて立ち上げられた会社でした。ところが、私は営業スタッフとして宮城県全域を回って足こぎ車いすを紹介したんですけど、どこへ行っても断られてしまうんです。
いくら足が動くと言ってもなかなか信じていただけないし、そもそもベンチャーという存在自体に胡散臭いイメージがあって、結局その会社は経営を打ち切ることになりました。
――それでどうされたのですか?
〈鈴木〉
自分で足こぎ車いすの事業を引き継ぎたいと考え、大学と先生にお願いしたら、どうぞどうぞとあっさり譲っていただけました。一流のプロが集まってできなかったことが、元学校の教員にできるわけないだろうと、警戒心を抱かれなかったのが幸いしたようです。そうして知人の家の2階を間借りして始めたのが、現在のTESSなんです。平成20年、31歳の時でした。
――いよいよご自身が経営者となって、足こぎ車いすの事業を主導していくことになったのですね。
〈鈴木〉
けれども、最初のひと月で資金がショートしてしまいました。とにかくお金の確保と、販売ルートと、製造場所を早急に確保しなければなりません。当時の私は営業も大してできませんでしたし、製造のことも財務のことも分かりませんから、企画書を書いて銀行に行っても門前払いです。
途方に暮れているところで会社に加わってくれたのが、元製薬会社の営業のプロでした。前の会社で一緒に仕事をしたことがあったのですが、他の仕事をメインに活動していたために、足こぎ車いすのことをあまり理解されていなかったんです。
ところが、足の不自由な患者さんが元気に漕いでいる映像を見せたらえらく感動して、ぜひこれを広めたいということで、勤めていた会社を辞め、共にTESS設立に動いてくれたんです。
財務に関しては、『青年社長』という企業小説に、実在の格好いい経営コンサルタントの方が出てきましてね。こういう人がいたらいいなと思って、伝を辿って足こぎ車いすのことを話しに行ったら、ものすごく感激されて、これは世の中に広めなきゃダメだと、会社に入ってくれたんです。
――心強い賛同者が次々と集まってきたのですね。
〈鈴木〉
ところが資金の目処がなかなかつきません。さすがにもうダメだと思っていたら、知人から商工会議所に相談するように言われて話しに行くと、そこでも大変感激されて、私を金融公庫に連れて行ってくださり、新しく創設される挑戦融資制度の第一号として融資いただくことができたんです。
気難しい経営者の心を動かす
――経営の基盤が整うまでに大変なご苦労があったのですね。
〈鈴木〉
製造を請け負ってくれるところもなかなか見つかりませんでした。福祉用具屋さんも自転車屋さんも町工場も全部ダメで、もうどうしようもなくなって依頼したのが、オーエックスエンジニアリングという車いすの会社でした。
事故で半身不随になった元レーサーの石井重行さんが始められた有名な会社で、一度断られていたんですが、実家がその会社の近所にあるという人がいたので、一縷の望みをかけて仲介をお願いしたところ、会ってくださったんです。
大変気難しい人だと聞いていたのですが、挨拶をしても返事もくださらなくて、ご本人は話を聞いてくださらない。代わりに技術担当の人に一所懸命説明するんですが、「ふーん」としかおっしゃらなくて、表情も変えないでずっと煙草を吸っているんですよ。
これはダメだなと思いながら帰ったんですが、1週間経って念のために電話をしてみたら、「遅い、本気度が足りないんじゃないのか」とおっしゃるんです。
もう図面ができているというのですぐに見に行ったら、めちゃくちゃ格好いいんですよ。きっと高くて、つくるのに時間もかかるだろうなと思ったら、2か月でつくってやると。提示された価格も、挑戦融資制度で確保した金額とピッタリ同額でした(笑)。
――実際の出来映えはいかがでしたか?
〈鈴木〉
約束の2か月後に東北大の病院の前で待っていたら、石井さんは小さな乗用車でやって来て、車いすのままトランクを開けてひょいと下ろすんですよ。これまで試作していたものに比べて、ものすごく小さいし、軽いんですね。
半田先生がそれに乗ってリハビリ室へ行くと、病院にいた子供たちが「乗せて、乗せて!」と群がってきて、大騒ぎになりましてね。
患者さんに乗っていただいたら、全員が見事に漕ぐことができました。それまでムスッとされていた石井さんも、そこでようやく満足そうに微笑んで帰っていかれたんです。
残念ながら石井さんはもうお亡くなりになりましたが、あれ以来オーエックスエンジニアリングさんとはずっと一緒に仕事をさせていただいています。
生前の石井さんには随分親しくさせていただき、後からおっしゃるには、私が最初に足こぎ車いすの説明に伺った時、そんなことがあるわけないと思ったそうなんです。業界でも有名な技術者集団の自分たちが、本気でつくってもムリだということを示してやろうと思って製造を請け負ったんだと。
ところが、患者さんが嬉しそうに漕ぐ姿を見て、あの時は本当に感動したなぁと。二人で何度も振り返っては、喜びを分かち合ったものです。
(本記事は月刊『致知』2018年11月号 特集「自己を丹誠する」より一部を抜粋・編集したものです)
◉『致知』2022年9月号の特集は「実行するは我にあり」。誰が反対しようと、いくら無理だと言われようとも自らが実行する気概を持ち、実際に道を切り開いた鈴木さんの体験に通じるものは多くあります。
本号でも、たゆまぬ実践・実行によって活躍する各界の人物に焦点を当てています。記事ラインナップはこちら(記事下部に一覧あり)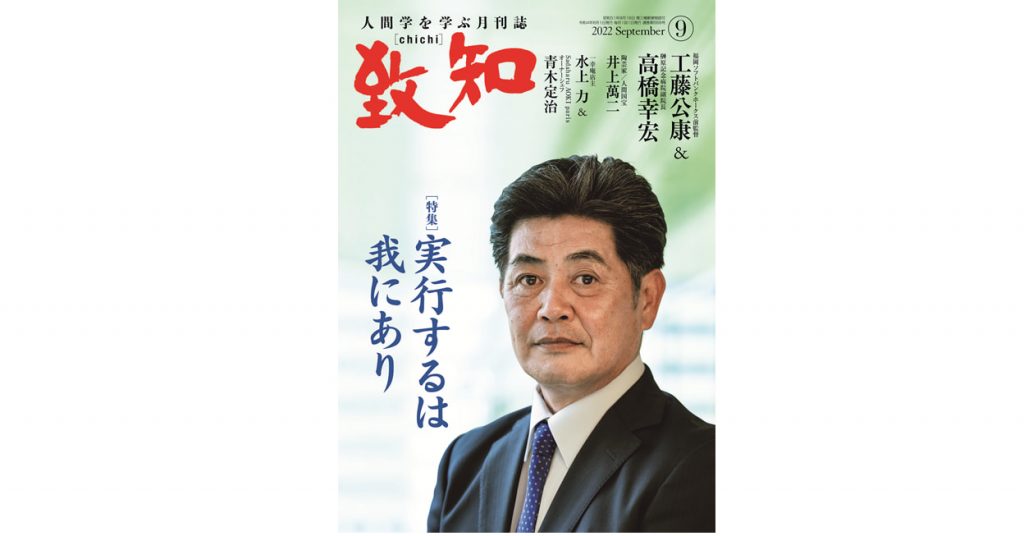
◇鈴木堅之(すずき・けんじ) ◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――
昭和49年静岡県生まれ。平成8年盛岡大学文学部卒業。知的障碍者更生施設、理学療法士養成学校を経て、13年山形県内の公立小学校教員となる。15年医療ベンチャー企業FESに入社。半田康延教授と足こぎ車いす初号機に出会う。20年東北大学発ベンチャー企業TESSを設立。社長に就任。著書に『風きって進め 魔法の足こぎ車いす』(日本評論社)がある。
《1月1日より期間限定》充実した2026年を送るための新習慣として、月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を開催中。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください