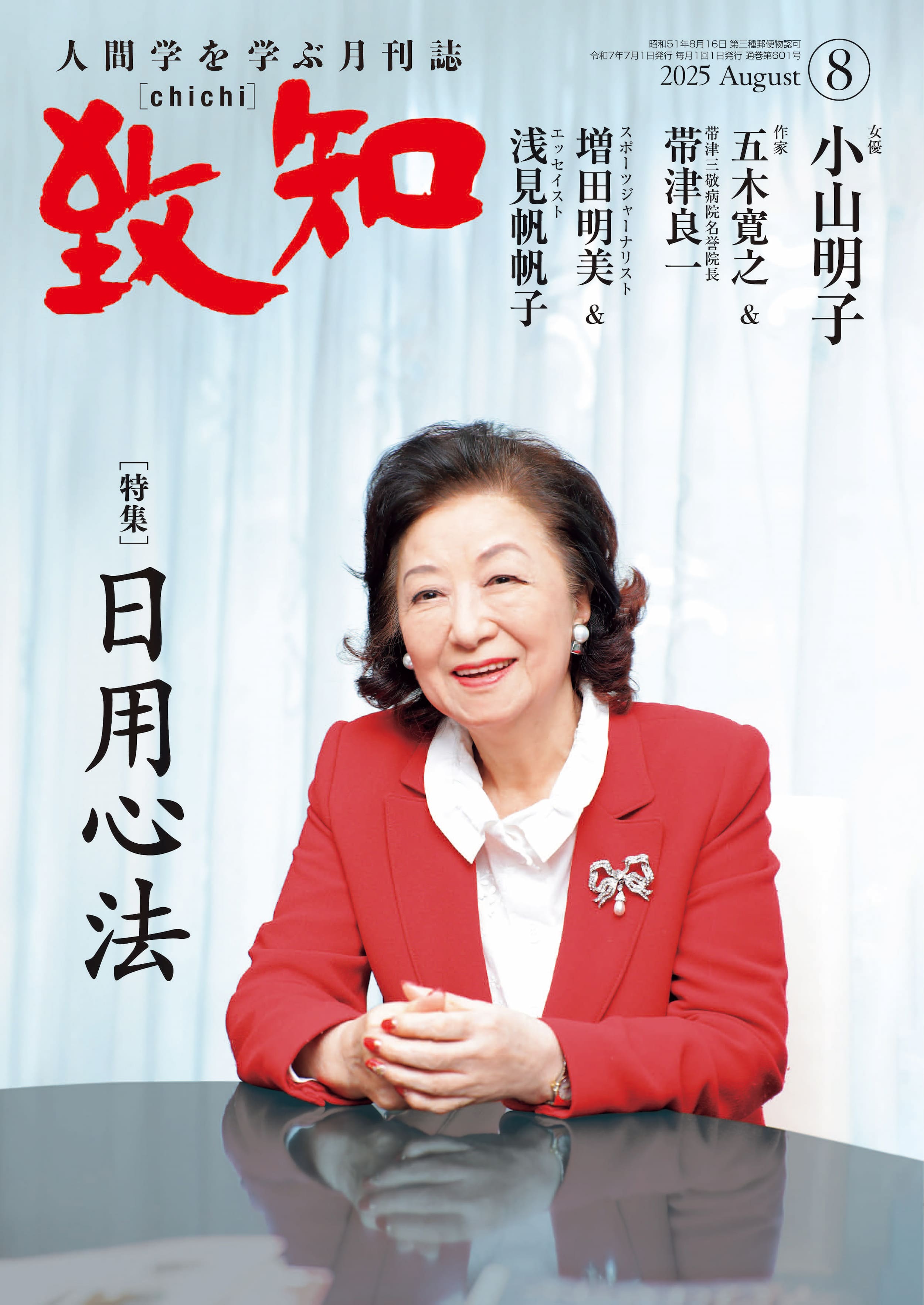2020年06月17日
 歌舞伎俳優の十二代目 市川團十郎さんは平成16年、息子の十一代目 市川海老蔵さんの襲名披露公演の最中、白血病に倒れられました。しかしその後、地獄のように壮絶な治療・休養を経て、僅か2年で舞台復帰を果たされます。江戸歌舞伎最高位の名跡を継承し、常に日の当たる場で活躍し続けてきた團十郎さんは、いかなる思いで苦難と向き合っていたのか。亡くなったいまなお名優と仰がれるその役者魂に迫ります。
歌舞伎俳優の十二代目 市川團十郎さんは平成16年、息子の十一代目 市川海老蔵さんの襲名披露公演の最中、白血病に倒れられました。しかしその後、地獄のように壮絶な治療・休養を経て、僅か2年で舞台復帰を果たされます。江戸歌舞伎最高位の名跡を継承し、常に日の当たる場で活躍し続けてきた團十郎さんは、いかなる思いで苦難と向き合っていたのか。亡くなったいまなお名優と仰がれるその役者魂に迫ります。
◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。
1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください
これ以上やったら死ぬというギリギリの治療
――突然発病し、いったん快復した後に再発。死への恐怖はありましたか。
〈市川〉
白血病は少し前まで不治の病といわれ、確かに治る確率が高まったとはいえ、人によってはいまでも命を落とす病気です。お医者さんからは治る見込みは7割と言われましたが、格闘家のアンディ・フグさんが同じ型の白血病だったと聞けば「ああ、あの人はお亡くなりになった……」なんて思うことはありました。
しかし、治るか治らないかは私には分からない。やるだけのことをやって、それで命を失うことになるなら、それも天命ではないかと。ただ病を嘆き悲しむのではなく、最後までやるべきことはちゃんとやっておきたい。そういう思いは持っておりました。
――前向きに治療に取り組もうと思っていらっしゃった。
〈市川〉
はい。ただ、再発したら抗がん剤治療だけではなく、もう移植しかないと言われておりました。移植にもいろいろ種類があるのですが、私の場合は抹梢血自家移植といって、自分に自分の細胞を移植しました。
要するに、まずはかなり強い抗がん剤を使って一時的に寛解の状態にもっていき、その時に骨髄から「造血幹細胞」という、血液をつくり出す大本の細胞を機械で取り出して保存しておきます。今度はさらに強い抗がん剤を自分で血液をつくる能力がなくなるまで投与し、そこに取り出した造血幹細胞を入れるわけです。それがうまく骨髄に入って生着すると、新たに血液細胞をつくり始めると。
また、他の病は脳に薬が届かないように治療するらしいのですが、白血病は特別で脳まで回るよう薬を投与します。少しでもその匙加減を間違えると痙攣したり、癲癇のような症状になる可能性もある。人によっては内臓に障害が出ることもあって、そうすると今度はそちらを治す薬を投与する、といった具合ですから、とにかく大変難しい治療法であることは確かです。
――お話を聞く限り、かなり危険な治療法のように感じますが……。そのような苦しい治療の中で支えになったことは何でしたか。
〈市川〉
ファンの皆様をはじめ、周囲の皆様には大変な励ましをいただきましたが、中でも特にといえば、やはり家族の存在に助けられた部分は大きいです。もしも親兄弟もなく、たった一人だったら、寂しかっただろうと思いますよ。会いに来て、いろいろと言ってくれる家族がいることは、私にとって大きな財産だと感じましたね。
――舞台復帰をされる時の心境はいかがでしたか。
〈市川〉
さて、復帰作は何にしようかといろいろ考えましたが、舞台から遠のいていましたし、治療をしたばかりで体力的に自信がない。そこで市川家の「歌舞伎十八番」中でも動きの少ない「外郎売」を選びました。
ただ、ご存じのように「外郎売」の口上は、アナウンサーの訓練に使われるほど長い早口言葉があります。治療で頭に薬を入れていたから、果たしてどの程度務められるか、直前まで不安でした。
ところが、幕が開いたら下座の音楽が聞こえないくらいの万雷の拍手と、大向こうからの掛け声で迎えられました。嬉しかったですねぇ。舞台に戻ってきたことをこんなに喜んでもらえる自分は本当に幸せ者だと感じました。
父であり師である先代から家の芸と魂を継承
――市川團十郎家は「市川宗家」といわれる歌舞伎界の名門家ですが、ご自身の中での歌舞伎との出合いは、いつ頃、どのような形でしたか。
〈市川〉
5歳くらいから連れられて父の舞台は観ておりましたが、印象的だったのは叔父の尾上松緑の「蘭平物狂」の舞台に、同じ年の従兄弟の初代辰之助君が子役として出ているのを見てびっくりしたんですね。ああ、すごいな、いいなと思いました。
――子どもの頃、歌舞伎やそのお稽古はお好きでしたか。
〈市川〉
幼い時は何の抵抗もなかったし、大人の中に入って仕事の真似事をしながら一種のプライドのようなものを感じていましたから、役がもらえることは嬉しかったですよ。
うちでは私が役をいただくと、まず父が母に伝え、母から私に「今度こういう子役があるそうだから、出させてくださるようお父様にお願いに行きなさい」と伝えられるという形を取っていました。そして父にお願いに行くと、「分かった」と。これはうちの倅が小さい頃も同じようにさせました。
ただ、私も子どもの頃は素直に「やらせてください」と言いに行っていましたが、中学生くらいになると母に「分かったよ」と言いながら、父の元にすぐには行かないわけですよ。そうすると父がやきもきしたり、母が困ったりしました。まあ、一種の反抗期です。
――そういう時期を経て、本格的に歌舞伎役者になろうと決心されたのはいつ頃ですか。
〈市川〉
昭和37年に父が十一代目團十郎を襲名しました。実に60年ぶりの名跡復活で大変華やかな襲名公演でしたが、舞台で私がせりふを言った瞬間、拙い言い回しだったんでしょう、お客様にクスッと笑われたんです。
父の晴れ舞台に倅がこんなことではいけない、もっと真剣に芝居に取り組まなくてはと思いました。この時、役者になる決心をしたように思います。
――父であり師匠でもあるお父様からはどんな影響を受けましたか。
〈市川〉
生前の父を知る方は、皆さん、不器用な性格だったと言いますが、確かにそういう面はあったと思います。稽古をしていても、口で説明するよりも先に手の出る質で、「違う、違う」と言って、どこがどう違うのかは言わないで、ボンと叩かれる(笑)。
その父も私が19歳の時、56歳の若さで逝きましたから、父から教わった演目というのは少ないんですね。その中でも特に印象に残っているのは16歳の時に教わった『勧進帳』の弁慶です。
その時の稽古はいつもとまったく違い、まず自分の台本をつくるところから始まりました。毛筆で書かれた台本を丁寧に書き写し、父と一緒に神仏にお参りをし、ようやく机に向かい合わせで正座をして、せりふの稽古に入ったんです。それは神聖な儀式のようで、家の芸とともに父の魂のようなものを伝えられたように感じます。
(本記事は月刊『致知』2007年5月号 特集「場を高める」より一部を抜粋・編集したものです) ◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。
◇十二代目 市川團十郎(いちかわ・だんじゅうろう)
本名・堀越夏雄。昭和21年東京都生まれ。日本大学芸術学部卒業。28年市川夏雄を名乗り初舞台。33年6代目市川新之助を名乗り、44年10代目市川海老蔵を襲名。60年には江戸歌舞伎最高位の名跡である12代目市川團十郎を襲名。平成16年長男の11代目海老蔵襲名披露興行の出演中、急性骨髄性白血病を発病。5か月の休養の後、フランス公演で復帰するも17年8月再発。18年5月に再び舞台復帰を果たす。その後も9年にわたる闘病の末、平成25年死去。