2024年08月02日
 いまや毎年のように大型台風が襲来し、河川の氾濫など各地に大きな被害を与えています。私たちは国土をどう建て直したらよいか――。洪水対策は「国家百年の計」として取り組まなければならないと警鐘を鳴らす中央大学の山田正教授に語っていただきました。
いまや毎年のように大型台風が襲来し、河川の氾濫など各地に大きな被害を与えています。私たちは国土をどう建て直したらよいか――。洪水対策は「国家百年の計」として取り組まなければならないと警鐘を鳴らす中央大学の山田正教授に語っていただきました。
想像を超える大雨が〝越水破提〟を引き起こした
2015年9月10日、台風17号・18号の豪雨による鬼怒川(茨城県常総市)の堤防決壊は、1万戸以上の浸水という広範囲にわたる甚大な水害や地滑りなどの災害を引き起こしました。
直後から、一部のメディアでは治水予算の経年の削減が鬼怒川堤防決壊の原因であるとか、行政の対応が適切ではなかった、上流ダムの管理を誤った、自然堤防の役割を果たしていた丘陵部を削り太陽光パネルを設置したのがいけなかったなど、〝人災〟を強調する情報が飛び交いました。
土木工学や防災工学の研究者として長年教育・研究活動に取り組んできた私は、災害の発生メカニズム、住民の避難行動などに関する調査・情報収集のため、地盤工学、水工学等の専門家から構成された合同調査団の団長として現地に入りました。
その調査から明らかになったのは、一部の報道とは異なり、これといった特徴が見当たらない場所(決壊箇所の堤防の高さは周辺堤防より少し低いようではあるが)で、堤防を乗り越えた水が外側から堤防を崩して破壊する〝越水破提〟が起こっていたという事実でした。
鬼怒川などの一級河川は、一般的に低気圧や台風による雨が合計して250~300㍉前後までなら氾濫せずに耐えられる実力を備えていますが、今回はその倍以上の550㍉から地点によっては1000㍉を超える大雨が、特に鬼怒川上流域に集中的に降ったことが地上雨量計やレーダーから分かっています。
人災という側面よりも、想像を超えた異常な大雨が直接的な原因だったと言えるのです。
100年、200年先を見据えた備えが必要
だからといって、我が国の洪水災害への備えや対策が十分であったわけでは決してありません。ゲリラ豪雨など新しい雨の降り方に対して、これまでと同じ治水対策でよいはずはなく、ハードとソフト両面から政府、自治体、そして地域住民もきちんとした対策を講じておくべきでした。
そのためには、一定の治水予算が必要になりますが、この10年来、治水予算は一貫して削られ続けてきたのです。
さらに問題なのが、予算の削減によって、優秀な人材が土木工学の中の治水分野からどんどん離れていっている現実です。縮小されていく分野を勉強しようと思う若者は少ないでしょう。実際、今回のような甚大な洪水災害が発生し、いざ調査をしようとしても、肝心の現場の人間が足りないのです。
堤防決壊直後から議論されてきた国や県、市町村との情報伝達や危機管理、さらに既述の住民による水防活動、そして住民の避難体制などのあり方についても、治水予算との兼ね合いで考えなければなりません。
私は何も膨大な予算が直ちに必要だと言っているのではありません。治水予算は国全体として100年先、200年先までを見据えて、地下水のように継続的に投入し続けなければ、いざという事態に対処できないことを訴えたいのです。
自然災害とともに歩んできた日本人のDNA
日本人は古来、洪水だけでなく、地震、高潮、津波、土石流、火山の噴火、渇水など、様々な自然災害と向き合ってきました。
そして、その厳しい自然環境を克服するために知恵を絞り、優れた人材を育成し、お互いが助け合って生きていく社会を生み出してきました。それがアジアの国で最初に日本が近代化を成し遂げた所以だとも思います。
昭和初期からつい近年まで、各地域の信頼できる人材を水文観測員として任命し、河川に棹(さお)を差して地道に雨量や水位の定期的な観測をする世界に誇るシステムができあがっていました。しかし、近年の電波や超音波といった自動観測機器の発達に伴い、いまやほとんどの地域で観測員はいなくなっています。
もちろん、科学技術の発展は洪水被害の減少に大きく寄与してきましたが、水位計の計測点は大きな河川でも数㌔㍍から10㌔㍍程度の間隔に1か所程度。同じ水位でも河川の右岸と左岸では堤防の高さなど条件が違う場合が多いため、単純な数字だけに頼り切るのは危険です。
いま一度、自然災害に真剣に向き合ってきた先人たちの歴史と知恵に思いを馳せ、私たち一人ひとりが普段から防災への意識を高めていくことが大切です。
私もまたその伝統を引き継ぎ、次世代に守り伝え、これからもこの国の安全と未来ために、目の前の課題に命を懸けて取り組み続けていきたいと思います。
(本記事は月刊『致知』2016年4月号 連載「意見・判断」を一部抜粋・編集したものです) ◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――
《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。
※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください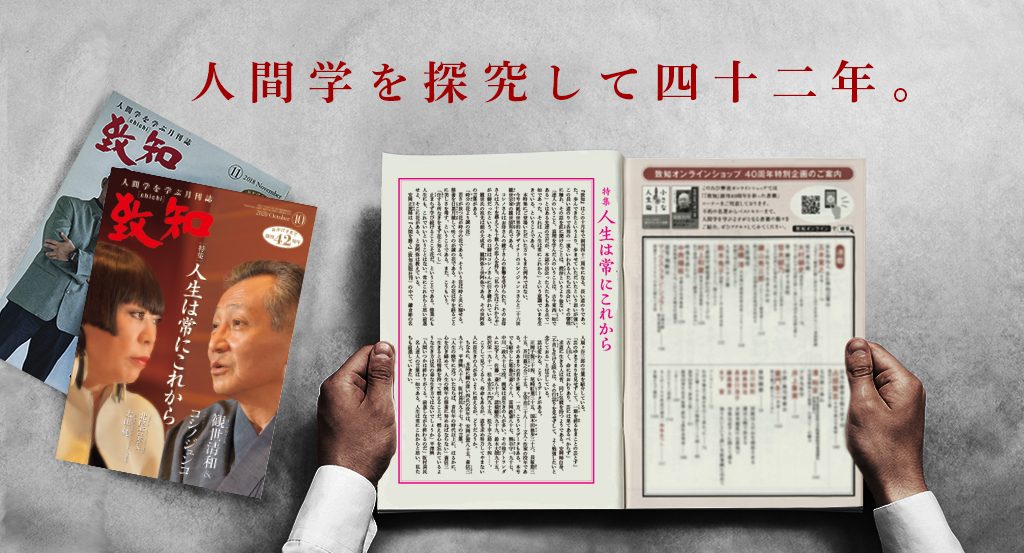 ◇山田 正(やまだ・ただし)
◇山田 正(やまだ・ただし)
昭和26年兵庫県生まれ。52年中央大学大学院理工学研究科土木工学専攻博士課程中退。東京工業大学工学部助手として奉職、博士号取得。防衛大学校土木工学教室助教授、北海道大学工学部助教授などを経て、平成4年より現職。水文・水資源学会会長。23年度水文・水資源学会学術賞、第11回産学官連携功労表彰国土交通大臣賞など受賞多数。














