2025年10月08日
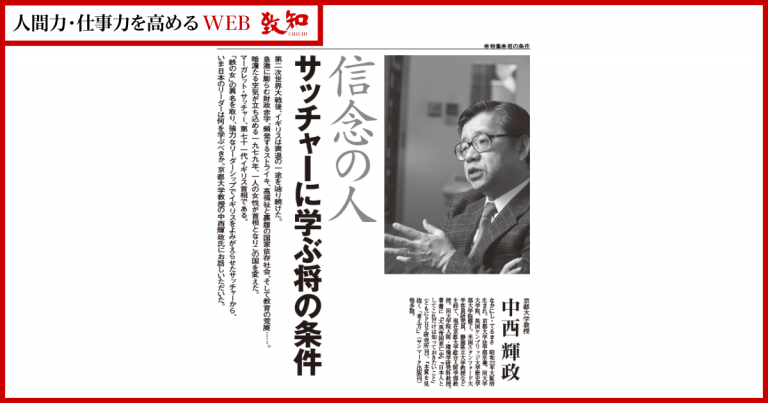 去る2025年10月4日、自民党総裁選挙が投開票され、高市早苗氏が第29代総裁に選出されました。そんな高市氏が尊敬してやまないのがイギリス初の女性首相・マーガレット・サッチャーです。第二次世界大戦後、衰退の一途を辿るイギリスを強力なリーダーシップによって甦らせたサッチャーから、日本のリーダーは何を学ぶべきか。弊誌2008年2月号特集「将の条件」にて、京都大学教授(当時)・中西輝政氏にお話しいただいた内容を一部抜粋してお届けします。(本記事は『致知』2008年2月号 特集「将の条件」より一部を抜粋・編集したものです)
去る2025年10月4日、自民党総裁選挙が投開票され、高市早苗氏が第29代総裁に選出されました。そんな高市氏が尊敬してやまないのがイギリス初の女性首相・マーガレット・サッチャーです。第二次世界大戦後、衰退の一途を辿るイギリスを強力なリーダーシップによって甦らせたサッチャーから、日本のリーダーは何を学ぶべきか。弊誌2008年2月号特集「将の条件」にて、京都大学教授(当時)・中西輝政氏にお話しいただいた内容を一部抜粋してお届けします。(本記事は『致知』2008年2月号 特集「将の条件」より一部を抜粋・編集したものです)
つるべ落としのように悪化した1970年代
〈中西〉
1970年代初め、私は研究のためにイギリスに留学した。日本へ帰国したのが1979年だから、70年代のイギリスがどんな時代だったか、つぶさに見てきたと言っていいだろう。そこにはかつての大英帝国の姿などどこにもなく、「つるべ落とし」のように世の中が悪くなっていった。
何が悪かったかといえば、とにかく景気が悪かった。財政赤字はひどくなり、庶民の生活はどんどん悪化する一方。75年だっただろうか、国際収支も決定的に悪くなり、アメリカの「保証」がないとIMF(国際通貨基金)も外貨を貸せない状態になった。何百年と輸入に頼ってきた砂糖がまったく入手できなくなり、店頭から姿を消してしまった。
これほど財政が逼迫しているにもかかわらず、労働党政権下にあった当時は福祉政策は手厚くなる一方、人々は権利ばかりを主張し、賃金交渉のストライキが頻発。電力会社までがストを起こすことも少なくはなかった。
70年代後半にはほとんどの地方自治体の財政が破綻、ロンドン市内でも地下鉄が止まり、市民はヒッチハイクしながら通勤するようになった。そのうちゴミ収集車までもが動かなくなり、ロンドンのメインストリートであるリージェント通りには2階の窓まで達したゴミの山が築かれた。かろうじて動いていたロンドン名物の2階建てバスも、ゴミ袋の谷間を行き交う有り様である。
この国はもうダメだろう――。それが当時の私の率直な印象であった。私はこの国の歴史を勉強しに来たのであって、現在の凋落ぶりは学問には関係ないのだ、と自分に言い聞かせていたように思う。
さて、私が帰国する79年、この年はイギリスのどん底が極まった感があった。私が住んでいた町では火葬場までもが機能しなくなり、棺が担ぎ込まれても野外に放置するのみ。夏場には異臭はするわ、野犬が吠えるわで、遺族もパニック寸前である。
そんな時、「これではいけない」と立ち上がった人たちがいた。第二次世界大戦に参戦した在郷軍人会のお年寄りたちである。彼らは町の若い男性を集め、火葬場が動いている自治体があると聞けば、自分たちがボランティアで運び出したのである。
「おい、外国人。この町に住んでいるんだからおまえも来い」と、私も駆り出され、100マイルほど離れた町の火葬場まで何往復もした思い出がある。
この時は軍人OBから若者、おばあちゃんまでが総出でこの窮状に対処していた。もしかしてイギリス人の考えが変わり始めたのかもしれない、と感じた出来事であった。
保守党が労働党を破り、サッチャーがイギリス史上初の女性首相に就任したのは、ちょうどこの年である。「イギリスはこのままではいけない」という一般市民の思いが、彼女を首相の座に押し上げたのではないだろうか。
信念の人 捨て身の人
〈中西〉
サッチャーは自らの回想録に「私の出自や経歴は伝統的な保守党の首相とは違っていた。私は彼らほど黙っていても敬意を抱かれることを期待できる立場ではなかった」と書いている。
続けて、首相官邸に入ると一国の首相としての重圧から、最初の数週間は眠れなかった。しかし、“国家統治の連続性”がどうのこうのと言うが、それらはすべてこけおどしである。政権につく前の自分の信念を国民へぶつける。それでダメなら潔く退く。信念を120%明確にしなければ、国民は付いてこないと気づいた、と記している。
信念――これがサッチャーのすべてだったと言ってもいい。サッチャーが命の危機にさらされたのは一度や二度のことではない。なにせIRA(アイルランド共和軍)のテロリストから命を狙われ、実際秘書も2人死んでいる。泊まっていたホテルが爆破され、たまたまサッチャーのフロアだけが瓦礫に埋もれ、鉄筋が落ちてこなかったということもあった。遺書も何度も書いたという。それでも決して相手の要求に屈することなく、自らの政治信条を貫き通した。
民衆が支持したのは、サッチャーの政策そのものではなかったのではないだろうか。「いつ死んでも本望」という、捨て身で政治に臨んだサッチャーの心意気に国民は感動し、支持したのである。市民の多くは難しい政策の話は分からない。しかし、いつの頃からか「サッチャーの言うことなら」と、信頼を寄せるようになったのであろう。
サッチャーが我々に教えてくれているのは、国をよみがえらせるにはリーダーが「捨て身」になって自らの理念を説くことだ、という点に尽きるかもしれない。技術的な政策論では決して国はよみがえらない。理念こそが国の活力となるのである。
イギリス在住の評論家・マークス寿子さんは「日本があの時のイギリスのような衰退ができれば万々歳ですよ」と言う。つまり、もっとひどい衰退の道を辿らなければ日本人は目覚めない、というわけである。
昨今の日本を見ていると、もしかしたら彼女の言葉が的中するかもしれないと感じることが多い。あの頃のイギリスに比べれば、景気はいいかもしれないが、財政赤字はいまの日本のほうがはるかに悪い。さらに深刻なのは日本人の精神状態である。あと10~20年こんな状態が続けば日本人は日本人でなくなり、経済競争力はもちろん、独立も主権もなくなって、どこかの国の文字どおり保護国になるだろう。
それほどの危機に瀕しているのに、一般市民はもちろん、リーダーといわれる人たちまでが、「まだどうにかなる」と思っている。しかし、いま目覚めなければ、日本はどうにもならないところまで来ているのだ。
明治維新や戦後の日本の復興もそうであったように、日本がよみがえる時は必ず民衆から立ち上がってきた。日本人は心で生きてきた民族である。この心が変われば、日本は一遍に変わる。もし日本人の心が変われば、国の再生する日はそれほど遠くないのである。
日本は再びよみがえる。私はそう信じている。だからこそ、民衆の心を揺さぶり、「捨て身」になって日本のために自らの信念を貫くリーダーの出現を望んでやまないのである。
◎中西輝政さんも、弊誌『致知』をご愛読いただいています。創刊47周年を祝しお寄せいただいた推薦コメントはこちら↓↓◎
わけても浮沈の激しい月刊誌の世界で、『致知』が創刊後、間もなく半世紀を迎えてますます多くの読者に支持され続けていることに、私は日本の将来に光明を見る思いが致します。常に変わらず、人間と人生について学び続けることの大切さを多くの日本人に伝えてきた『致知』の役割は、今後も一層大きなものになってゆくことでしょう。
◇中西輝政(なかにし・てるまさ)
昭和22年大阪府生まれ。京都大学法学部卒業。英国ケンブリッジ大学歴史学部大学院修了。京都大学助手、三重大学助教授、米国スタンフォード大学客員研究員、静岡県立大学教授を経て、京都大学大学院教授。平成24年退官。専攻は国際政治学、国際関係史、文明史。著書に『国民の覚悟』『賢国への道』(共に致知出版社)『大英帝国衰亡史』(PHP研究所)『アメリカ外交の魂』(文藝春秋)『帝国としての中国』(東洋経済新報社)等多数。近刊に『シリーズ日本人のための文明学2 外交と歴史から見る中国』(ウェッジ)。
◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――
《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。
※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください















